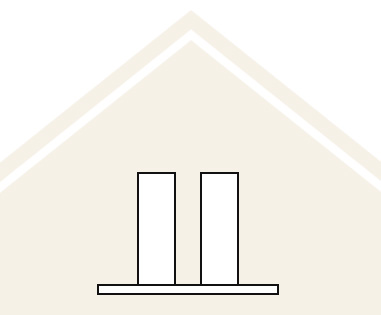迷いながら看取りに寄り添ってきた私が大切にしてきたこと〜『ことばにしてみた訪問看護の看取り』から学ぶ実践のヒント〜
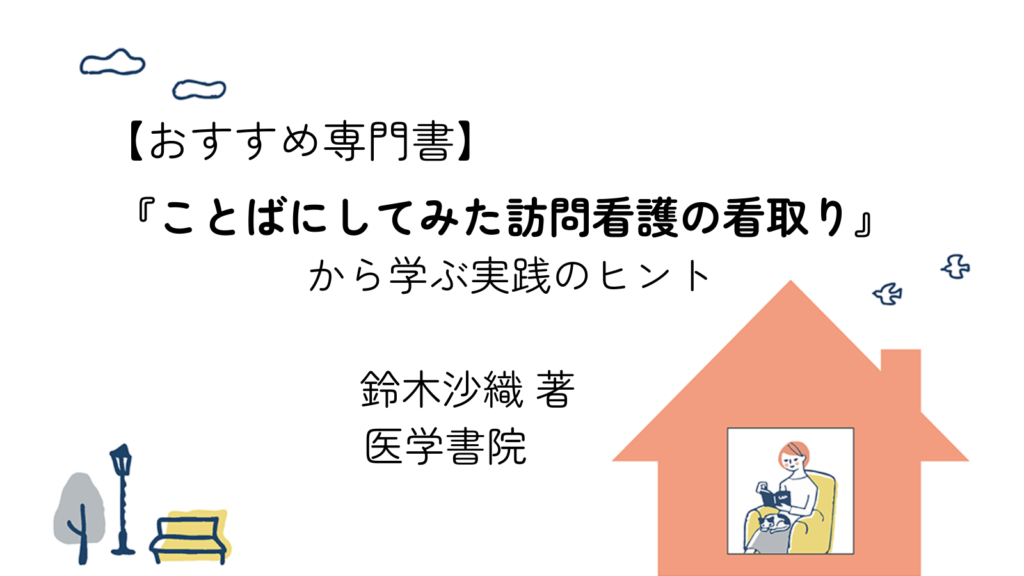
記事内に広告が含まれています。
訪問看護の現場で「看取り」に立ち会うとき、何度経験しても、迷いや葛藤が消えることはありません。「この関わり方でよかったのかな?」「言葉をかけるタイミング、間違ってなかったかな?」そんな思いを繰り返してきた私にとって、ある1冊の本が、静かに寄り添ってくれました。今回は『ことばにしてみた訪問看護の看取り』という書籍を通して、私が“看取り”に向き合う中で大切にしてきたこと、そして現場で役立った実践のヒントをお伝えします。
目次
訪問看護の「看取り」に、正解はない
訪問看護の現場では、人生の終わりに寄り添う場面が少なくありません。「看取り」という言葉の響きに、何とも言えない重さと責任を感じ不安に感じることもあるでしょう。私たちにできることは何かと自問自答しながら、ご本人とご家族の思いに寄り添うことを願い、日々ケアを届けています。けれど本音を言えば、何度経験しても「これでよかったのか」と迷います。沈黙の中で流れる時間、家族の表情、ご本人の呼吸の変化――どの瞬間も、問いの連続です。
そんな私に、言葉を通して静かに寄り添ってくれたのが
『ことばにしてみた訪問看護の看取り』(医学書院)という一冊でした。
『ことばにしてみた訪問看護の看取り』とは?
この本は、訪問看護師として多くの看取りに関わってきた著者が、その体験を“ことば”として丁寧に綴った実践的エッセイです。教科書に載らない、現場の肌感覚がぎゅっと詰まっていて、読んでいると「それ、私も感じたことある」とうなずきたくなる瞬間がたくさんあります。専門用語やテクニックよりも、「どう在るか」「どんな姿勢で関わるか」に焦点が当てられており、迷いながら看取りに向き合う看護師・介護者にとって、心のよりどころになる一冊です。
この本に出会って、救われたことば
ものごとは最初が肝心と言いますが、初めましての印象は特に大切です。初回訪問でどれだけ心を砕くのかがわかるくらいに、著者は多くのページを割いて丁寧に語っています。
「医療者っぽい脅威」を感じさせない
他職種との連携の中で、時折耳にするのが「看護師さんってちょっと怖い」という声です。それがイメージなのか、実際の体験なのかは分かりませんが、小さなつぶやきとして届くことも少なくありません。「人の振り見て我が振り直せ」と言いますが、これは私自身、常に意識していることです。
メラビアンの法則では「第一印象は3〜5秒で決まる」と言われています。特に退院直後のご利用者宅に、初回訪問で多職種が一緒に伺うような場面では、その印象が相手に与える影響はとても大きなものになります。だからこそ私は、その場にいるすべての人が少しでも安心できるように、“ありったけの誠意”を込めて関わることを大切にしています。「この人たちに任せても大丈夫」「困ったら、ここに相談できる」そう思ってもらえるように、「24時間365日、いつでも相談できる窓口があること」を伝えます。それは、単なる制度や仕組みの話ではなく、「ご縁をいただいた方と、これから一緒に暮らしを支えていきたい」という私の気持ちの表れでもあります。
信頼関係をスムーズに築くには、まず“安心できる存在”として感じてもらうことが必要です。だから私は、「医療者っぽい脅威」――つまり、専門性の高さを振りかざすような態度や、緊張感を与えるような言動は、できる限りそぎ落としたいと思っています。看護師である前に、一人の人として、信頼される存在でありたい。それが、私の訪問看護における原点のひとつです。
メラビアンの法則
さらに第一印象を決める要素が以下の3つに分類されています
- 視覚情報(見た目):55%
- 聴覚情報(声):38%
- 言語情報(話す内容):7%
この法則によれば、初対面の僅か数秒で印象を形成し、その大部分が視覚情報に基づいているとされます。
一歩踏み込む
今日初めて会った相手に、すぐに心を開ける人はそう多くありません。それは、訪問看護の場面でも同じです。特に、今までの治療の中でつらい思いをしてきた方、あるいは過去に心ない言葉で傷ついた経験のある方にとって、「誰かを信じる」という行為自体が、大きなハードルになることがあります。だからこそ、私たち訪問看護師には、“最初の一歩”の関わり方がとても大切だと感じます。マインドがなければ、一歩踏み込む意味もなくなります。病状が思っていた以上に進んでいて、ご本人やご家族に“残された時間”の話をせざるを得ない場面もあります。まだ関係性が十分にできていないうちに、意思確認やバッドニュースへの対応を迫られることも、少なくありません。そうしたときに求められるのが、相手を不快にさせないコミュニケーションスキルです。長年現場を経験してきたベテランの訪問看護師さんには、こうした「難しい対話」の引き出しをたくさん持っている方が多くいらっしゃいます。言葉の選び方、沈黙の使い方、声のトーン、相手との間合い…。それぞれが、実に繊細で、丁寧です。「こういうとき、どうしていますか?」「こういう場面、どんな言葉が届きましたか?」そんなふうに、日々の中でアイディアを共有し合えることは、チームとしての大きな財産になると感じています。
応え続ける
ときに、辛さや困難はまるで突然の嵐のようにやってきます。「なんで今…」「どうして私が…」そう思う間もなく、現実は容赦なく押し寄せてきて、まるで視界ゼロの中に放り込まれたような、不安だらけの状態になることもあります。そんなとき、「何を選べば正解か」なんてわからないのは当然です。私たち看護師だって、明日のことは誰にも分かりません。だからこそ、目の前の“今”に全力で向き合うこと。まずは、心と体の穏やかさを取り戻すこと。そこからしか、始められないことがあると思っています。病状や生活状況が刻々と変わる在宅療養の中では、“これがベスト”という一つの正解を見つけることは難しいことも多いです。そのとき必要なこと、できること、望まれていること。それは日々変化します。だから私たちは、臨機応変に対応できる柔軟さを持ちつつ、「今、この人にとって一番楽になれる方法は何か?」を軸に置いて考えます。ときには、その場しのぎに見えることもあるかもしれません。
けれど、その場をしのぐことが、生きる力につながることもあるのです。嵐のような時間の中では、先を見通すのがとても難しいものです。でも私たちは、その中でも少しだけ視線を未来に向けて、「この方にとっての、少し先の安心とは何か」を想像するようにしています。あくまで焦らず、押しつけず。ご本人やご家族のペースを尊重しながら、ちょうどいい“塩梅”で、未来を見守る視点を持ち続けること。それが、嵐の中での訪問看護師としての私の在り方です。
私が看取りで大切にしている3つのこと
この本を読んで、自分自身の現場での関わりを振り返るきっかけになりました。数えきれない看取りの場に立ち会うなかで、私があらためて大切にしたいと感じたことが3つあります。どれも、医療の技術や知識だけではなく、「人として、看護師として、どうあるか」を問われるものです。その想いを、ここに綴ってみたいと思います。
Not doing,But being.〜“何かをする”より、“そこにいる”こと〜
終末期の訪問看護では、医療処置や身体的ケアといった“目に見える関わり”だけでなく、その場その場で組み立てていく柔軟な支援が求められます。特に、精神的なサポートは、状況やタイミングに応じて繊細に組み込む必要があります。ご本人の気持ちだけでなく、ご家族の心配や戸惑いにも耳を傾ける場面も多くあります。訪問看護の本質は、“オーダーメイドなケア”と言っても過言ではありません。まずは静かにアンテナを張り巡らせて、目に見えない“全人的な苦痛”に周波を合わせることから始まります。
私たち看護師は、とかく「何かしてあげたい」と思いがちです。“何か手助けしなければ”という気持ちが、つい先行してしまうのです。でも、そんなときこそ、この言葉が私の中に響きます。
Not doing, but being.
何かをするのではなく、ただ“そこにいる”ことに意味がある。
隣にいるだけで、言葉がなくても、それだけで安心につながる瞬間があります。存在そのものがケアになる。この本を読んで、そのことをあらためて胸に刻みました。
自分ができることは何か?を問い続ける〜ニーバーの祈りに導かれて〜
終末期においては、変えられることと変えられないことがはっきりしている場面もあります。それでも私たちは、全人的苦痛へのアプローチを手放さず、「できること」に全力で向き合います。そんななかで、私が大切にしているのが「ニーバーの祈り」です。
神よ、
変えられないものを受け入れる心の静けさと、
変えられるものを変える勇気と、
その両者を見分ける知恵を我に与え給え。
この言葉に何度も背中を押されてきました。限られた時間のなかでも、そこに意味を見出せるような関わり方がある。たとえ寝たきりになっても、眠る時間が増えても、ご本人が残してくれる“宝物”のような時間は、私たちにとってもかけがえのない贈り物です。また、看取りに向けたケアは、ご本人の人生だけでなく、ご家族のグリーフケアにもつながります。「家で看取ったことを、後悔してほしくない」その思いから、ご家族とも丁寧にコミュニケーションを重ね、特に大切な話は、先延ばしにせずお伝えするようにしています。
すべての看護ケアは患者さん(利用者さん)や家族さんと共に作り上げていくこと
私たちは、あらゆる知識や技術を磨きながら、それを相手に“押しつける”のではなく、“選ぶお手伝い”をする存在でありたいと考えています。ワインに詳しいソムリエが、お客様の好みに合わせて一本を選ぶように――看護師も、ご本人やご家族の人生を尊重しながら、その人らしい最期の物語を共に紡いでいくサポーターでありたい。「これが正解です」ではなく、「いろんな選択肢の中で、どれがあなたに合っていますか?」と尋ねる姿勢。在宅での看取りは、選択肢が多いからこそ迷いがちです。でも、迷うことは悪いことではありません。その迷いに寄り添い、一緒に考え続けることこそが、支援者としての役割だと思います。人は、最期のときまで――そして亡くなった後も、誰かにとっての支えとなる存在であり続けます。そのことを、看取りのたびに教えてもらっています。
「オハナなおうち」で大切にしたい看取りのかたち
私は、「オハナなおうち」という仮想のシェアハウスをコンセプトに、訪問看護や介護、在宅医療にまつわる情報を発信しています。この“おうち”が目指すのは、「ともに支え合いながら、最期まで自分らしく生ききる」ことができる場所。看取りが特別な出来事ではなく、“暮らしの中にあるもの”として自然に受け入れられるような空気感を大切にしています。
言葉にして、思いをつなぐ
だからこそ私は、ケアの現場で感じたこと、学んだことを、言葉にして伝えることを大切にしています。『ことばにしてみた訪問看護の看取り』という本と出会い、そこに書かれた一つひとつの言葉が、まるで優しく背中を押してくれるように感じられました。誰かのことばが、誰かの背中をそっと押す。そんな循環を、私自身の発信でも育んでいきたいと思っています。
おうちで看取るということ
看取りに、明確な“正解”はありません。それでも、ご本人とご家族が、「最期まで一緒に過ごせてよかった」「おうちで看取れて、本当によかった」――そう思ってくださることが、何よりの支えになります。そのために、私たち訪問看護師は、日々の小さな声やまなざしに耳を傾け、時間を重ねていくのです。
寄り添う力を育むために
『ことばにしてみた訪問看護の看取り』は、そんな迷いの中にいる私たちに、
そっと勇気をくれる一冊です。訪問看護の現場にいる方だけでなく、介護者、医療者、そして看取りに向き合うすべての人に、“寄り添う力”の在り方をそっと示してくれるのではないかと思います。そして私はこの本を読みながら、ある言葉を思い出しました。
「誰かを支えようとする人こそ、誰かの支えが必要です。」
――小澤竹俊医師(ユニバーサルホスピスマインド提唱者)
支える人もまた、誰かに支えられていい。そう思えることで、やさしい空気がめぐり、穏やかな時間が生まれていく。そんな循環を、「オハナなおうち」という場でも大切にしていきたいと心から思います。
おわりに
看取りは、「命の終わり」ではなく「その人の物語のしめくくり」にそっと寄り添う時間。それをともに見届け、支え合える関係性を築くことができたとき、訪問看護は本当の意味で「暮らしのケア」になるのだと感じています。これからも私は、「オハナなおうち」という仮想のシェアハウスを通じて、誰かの気づきややすらぎにつながる発信を続けていきます。
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。