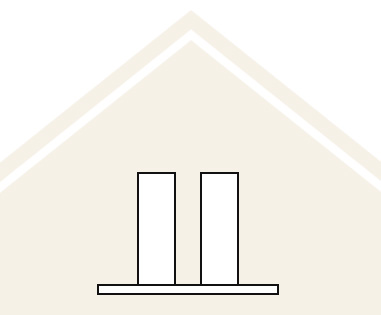おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.5.2〜 5.11】
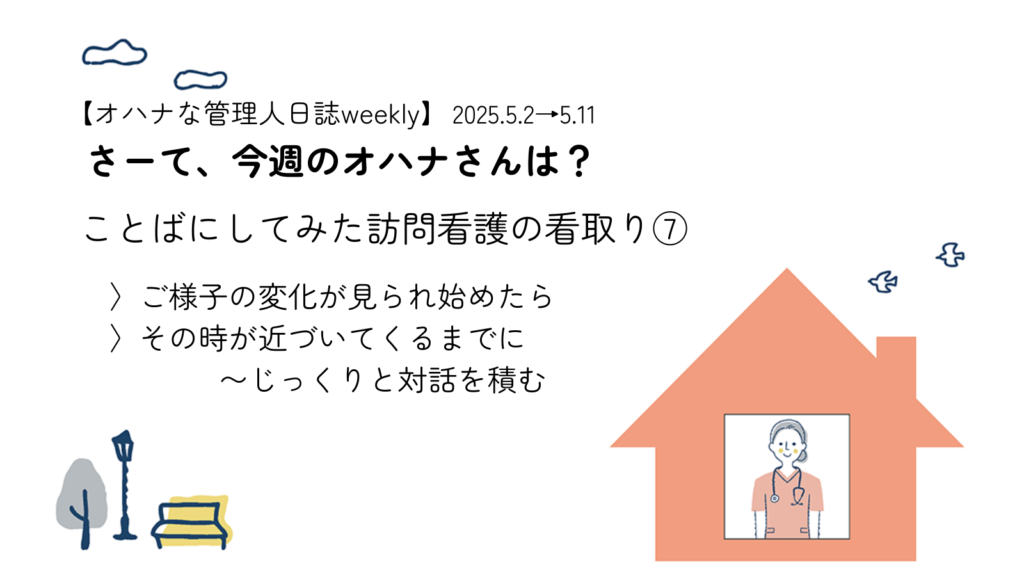
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
ことばにしてみた訪問看護の看取り⑦
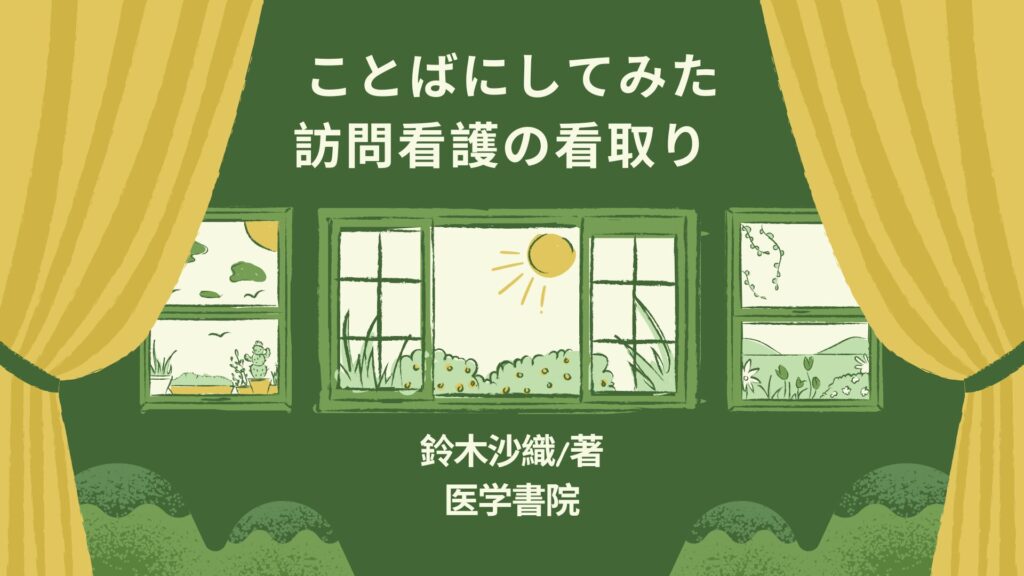
管理人日誌professional Ver. 忙しい妹たちへの解説
【ことばにしてみた訪問看護の看取り】鈴木沙織著 医学書院
ご様子の変化が見られ始めたら
🏠 終末期の輸液について《オハナな管理人日誌 2025.5.2》
体の衰弱が進み、ベッドの上で過ごすことが精一杯になってきました。退院したら好物を食べたいと楽しみにされていましたが、召し上がれたでしょうか?ご家族もあれもこれもと喜んで頂きたい気持ちで一杯です。その気持ちに応えたいのに、体がついていかないんですよね。そして食べられない=体がさらに弱ってくる、死への不安が大きくなります。食べられないことをご家族は心配され、心配されていることが支えに思う反面食べられないことへのプレッシャーにもなりうるのです。
実際には胃瘻のようにお腹に穴を開ける治療はして欲しくないけど、点滴ぐらいはと考えている方が多いです。生理学的には消化管から栄養が吸収する方が自然ではあるのですが、点滴すると元気になるとメンタル的な作用が大きい印象を受けます。「体の働きが弱ってきているので、点滴をすることがかえって体の負担になって苦痛が増えることがあるんですよ」と説明させて頂くとびっくりされます。しかし『せめて点滴ぐらい』という言葉の根底には、なんとか元気になる手立てがないのかという切実な想いがヒシヒシと感じます。その方が感じている点滴の意味に寄り添い、結論よりも折り合いをつけることや別の価値に気づけるアプローチができるかどうかで、後の後悔を少なくできるのかもしれません。
ちなみに主治医より 「輸液が余命延長に寄与しない」ことを説明した上で、希望があれば200~500ml程度の少ない輸液量を皮下点滴で実施することがあります。毎回ではなくても点滴針を刺すことでの苦痛も伴いますし、体に苦痛が出る徴候があれば減量または中止を判断します。点滴をしないと決めた家族が、現状の理解に乏しい親戚からの心無い言葉に傷つけられることもありました。日本では近年ようやく「平穏死」や「自然な最期」を重視する考え方が広まりつつありますが、依然として点滴への期待が根強い背景には、医療への信頼や「何かしてあげたい」という家族心理が影響していることを専門職が理解した上で、意思決定支援するべきですね。
『せめて点滴ぐらい…。』と思われるお気持ちをしっかりと受け止めたいと思います。
🏠 ご家族とともに安楽を支えるケア《オハナな管理人日誌 2025.5.4》
ベッドの上で過ごされ、食事も摂れず、話ができずに寝ている時間が長くなると、徐々に衰弱が進んでいることを日々感じ、予期悲嘆に苛まれながら、ご家族は不安に感じることでしょう。そういう経過になりますよと話されていても、進んで欲しくない現実ですから。まるで大きなベルトコンベアーに乗せられて、自分は行きたくない方向なのに進んでいくような感覚ですと表現されるご家族がいらっしゃいました。とても心情がわかりやすい表現です。
緩和ケアの姿勢として有名な言葉「Not doing, but being」はこの場面の魔法の言葉です。「何かをしてあげる(doing)」のではなく、「ただそこにいる(being)」ことの大切さを表す言葉です。病気が進行し、治療や処置など「何かをする」ことが難しくなったとき、本人やご家族にとっては「そばにいてくれる人がいる」という安心感や心の支えがとても大切になりますが、せめて〇〇したいと願うご家族にはdoingできないことに失望することで頭が一杯になります。まずは専門職がしっかりとそんな心情を理解することが大切です。
そして、安楽なケアを看護師と一緒に行うことを提案します。ご本人の体調によっては体の向きを変えることですら、体力の消耗や苦痛に値する時期もあるため、保清ケアも部分的に日々分割や負担がかからない方法をお勧めします。ホットタオルを顔に当てるのは、その温かさに多くの人が心地よく感じるでしょう。優しく丁寧に声をかけながらのケアはご本人はともかく、そばにいるご家族も嬉しく感じます。顔を拭く手浴をすることは、安楽体位のままでケアができるのでおすすめです。いつも使っている保湿剤でマッサージするようにスキンケアをします。ケアをしながら、ご本人のエピソードや他愛のないおしゃべりで空気まで温かくなる気持ちがします、好みの音楽をBGMで流すと一緒に音楽鑑賞もできます。歯磨きができないと心地悪いですよね。口腔ケアもケア用グッズがドラッグストア等で手に入りますから、スポンジで口腔内を少し冷たい水で浸して拭ったり、脱水が進むと口腔内の乾燥も目立ちますから、保湿用のジェルなどで保護することもお勧めします。

口腔ケアとは別な観点ですが、水分の吸啜が難しくなれば、きれいなスポンジにお好みの飲み物を浸して味わうことやファスナーつき保存袋に飲み物を入れ凍らせて一口大に割り、小さい氷片を味わってもらうこともできます。同じように経腸栄養剤や栄養補助食品を凍らせて味わうことを喜ばれる方もいらっしゃいます。これは失敗例ですが、日本酒が好きな人で同じようにお酒を凍らせて味わってもらいましたが、風味が強くなりすぎて美味しくなかったと苦い思い出があります。清潔な下着やパジャマは気持ちが良いですよね、寝た状態での更衣は工夫が必要ですので、苦痛にならない方法で支援します。ご自分で体位交換できないのですから、シーツや寝衣のしわが皮膚発赤や褥瘡の原因にもなるので細心の注意を払います。
限られた訪問時間でケアの内容から今日はどんな安楽ケアを支援できるのかを頭の中でマネージメントをします。よく訪問看護界に飛び込まれたナースたちのきっかけが、病棟看護よりひとりひとりにじっくり関わる時間を持ちたいからと志望理由を上げられますが、私は例え訪問時間が60分でも90分であっても、いつも短く感じます。より多くのケアが心地よく提供できるように、段取りや順序、時間配分などにも心を配り、日々のケアが後のご家族の思い出の宝箱に入れていただけるように、私自身もかけがえのない時間として、この時期のケアをそう捉えます。肉体が存在しなければ触れることもできませんから、なでることやマッサージすることも大切に感じます。ご家族が孤独や不安に陥ることも心配ですので、その場にいる私自身も三人称のナースではなく二人称で在るのは自然な流れに感じます。
日々のひとつひとつのケアが、ご家族の思い出の宝箱に入れていただけますように。私自身のかけがえのない時間として、ともに過ごせますように。そんな願いを込めて向き合います。
その時が近づいてくるまでに〜じっくりと対話を積む
🏠 旅立ちの時が近づいてきたら《オハナな管理人日誌 2025.5.8》
いよいよ、昏睡状態となり目が覚めなくなりました。
「看護師さんなら、あとどのくらい時間が残されていると思いますか?」
心の準備や同居していない身内に連絡する関係でしょうか、そう尋ねられます。数ヶ月前と変化があるか?、週単位での変化があるか?、前日との変化があるか?、時間単位での変化があるか?その変化とは、セルフケア、意識状態、血圧や熱、酸素飽和度、脈、呼吸状態、尿量などです。旅立ちが近くなればなるほど、変化の波の間隔が短くなります。その変化のを評価してお伝えします。忘れられないエピソードがあります。新年はおそらく迎えられないだろうと周囲の医療者は感じていました。今まで何度もおうちの不思議な力が生命力を引き上げる奇跡に立ち会ってきたように、その方も無事新しい年をご家族と共に迎えることができました。お正月気分が明けた頃にその方が在宅医に「私の余命はどのくらいですか?」その医師はすでに予測された余命は超えていると率直に答えました。「あら~先生でも外れることがあるのね~」と微笑まれたのです。うれしい誤算で良かったとご本人が安堵される空気が流れました。その経験から余命を尋ねられる質問が怖くなくなりました。神様でないから読めない部分もあるし、外れたらどうしようという悩みがなくなったのです。「そうですね、教科書的にいうと今月を超えることは難しいのではないかと感じますが、今までの経験から言うとおうちの不思議な力で奇跡が起こり私たちの予測を大いに外れることもたくさん見てきました。なので、〇〇さんがご自分で選んで旅立たれると私は考えますので、そんな日は1日でも先であればいいと願っています。ですが、何かされたいことがあれば先延ばしにせずに過ごされることをお勧めします。お話ができる間にたくさんお話ししてください。」そんなふうにお答えしています。
伝えたいことは先延ばしにせずに、お話をしてくださいね。お話できなくなってしまって後悔される方がいらっしゃいます。
🏠 旅立ちの時が近づいてきたら②《オハナな管理人日誌 2025.5.10》
『息を引き取る』という言葉は、仏教の影響を受けた日本の伝統的な考え方では、「亡くなった人の息(命)」を残された者が「引き継ぐ」「引き受ける」という意味が込められているとされます。つまり、単に呼吸が止まるだけでなく、命が次の世代や家族に受け継がれていくというニュアンスが含まれています。そして、これも日本の文化的は背景の考えですが、親や大切な人の最期に立ち会うことが「家族としての務め」「孝行」とされる傾向があり、「死に目に会えない」ことを不幸や親不孝と捉える価値観が根付いています。これは、儒教的な「親孝行」や家族の絆を重視する古来からの思想が影響していますが、近年は「死に目に会えなくても不幸ではない」「自分を責める必要はない」とする考え方も広がりつつあります。社会の変化とともに、死との向き合い方や家族観も多様化しているため、必ずしも「死に目に会えない」ことを悔やむ必要はないという意見も増えています。
その瞬間は来て欲しくないと願いつつも、ちょっと目を離した隙に旅立たれたらと不安に感じる方も多いのです。私の経験を振り返ると人それぞれで、ご家族に見守られながら旅立つ時もあれば、家族がほんの少しベッドサイドでうたた寝している時や席を外したとき、かけつけた家族の到着を待ってのこともありましたね。定期の訪問の最中に呼吸が伸びてきたご様子をキャッチし、ご家族にお声をかけることもありました。
私個人の経験上ですが、その人が旅立つ時を選んでいるんじゃないかってそう感じることが多いです。
どうゆう状態で医療者に連絡するべきか迷われることもあります。一緒に過ごして頂いて、ご本人が苦痛が感じられる時は頓服薬を検討したり相談の連絡は遠慮せずにして欲しいこと、さらに、その時が来たら気が動転しても当然ですので、旅立ちが近い状況での呼吸の変化や息を引き取られた後も慌てることなく、落ち着いてから連絡を頂けるようにお伝えします。
🏠 イキヲヒキトル《オハナな管理人日誌 2025.5.11》
「呼吸が止まってしまいました。」「呼吸が止まってしまったように感じます。」「少し前には息していたのですが、今見たら息をしていないんです。」涙声を振り絞るようにご連絡を頂き、かけつけます。現実を受け止められずに心臓マッサージをされていたり、身体にしがみついたまま悲しみに暮れていたり、この上ない悲しみに打ちひしがれているのが背中をさする私の手にも伝わります。「旅立つ時に家族みんなでそばにかけ寄り感謝の言葉を伝えられたよ」、「とうとう旅立ってしまったけど本当によく頑張ってくれた」、「あんなに辛い闘病生活だったしやっと安らかな顔になったね」と、喪失感や後悔だってたくさん感じながらも本人と最期まで一緒に過ごせたという想いをなんとか支えにしながら、かけつけた私たちに泣き笑いながら想いを伝えて下さることもありました。
どんなに寂しくても、ご縁を頂けたことは大変ありがたいことには変わりありません。こんな境遇にならなければ、決して出会うことはなかったでしょう。そしてグリーフケアとして大切なエッセンスが在宅看取りにはたくさん含まれています。
30年前病棟勤務していた時代の終末期の苦い思い出が、私の在宅看取りの世界に足を踏み入れた大きなきっかけとなりました。たとえ旅立つ時が近い状況だとしても、尽くせるだけの治療をすることが善とされ、いかに生存率を伸ばすという延命が最優先された時代でした。やっとインフェームドコンセントという言葉がさけばれ始めた頃ですが、慣例が覆るにはかなりの時間が必要でした。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。