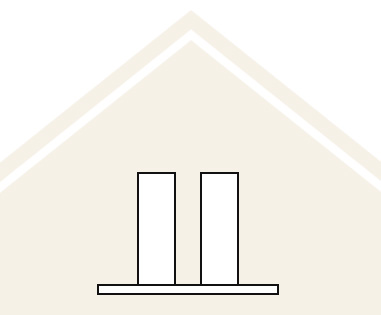おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.3.20〜3.27】
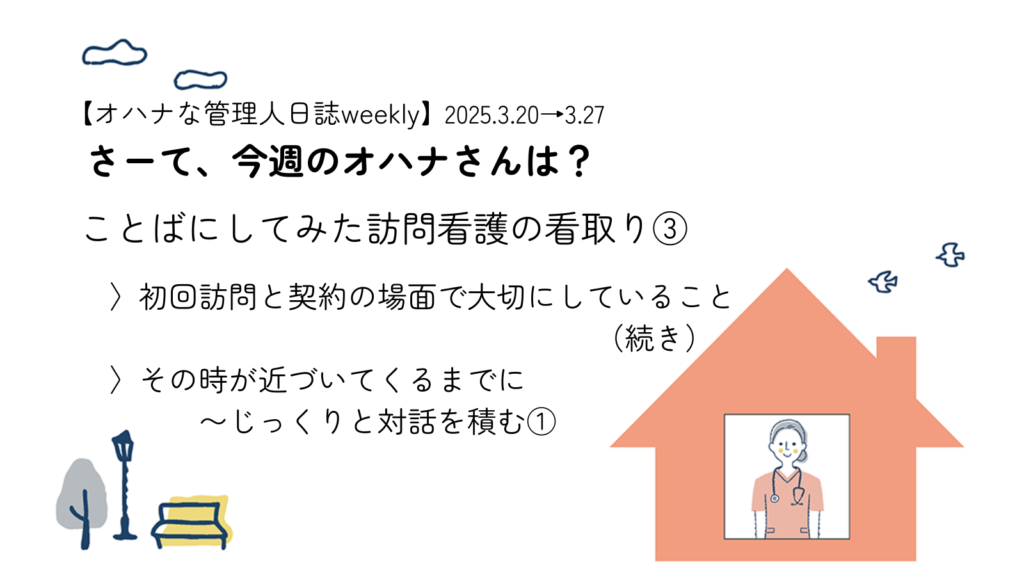
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
ことばにしてみた訪問看護の看取り③
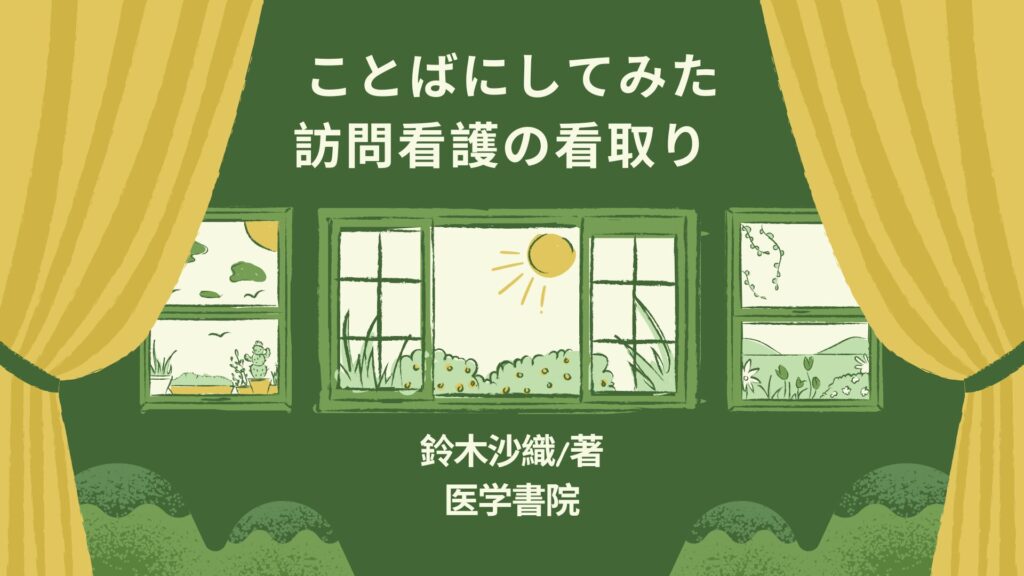
管理人日誌professional Ver. 忙しい妹たちへの解説
【ことばにしてみた訪問看護の看取り】鈴木沙織著 医学書院
初回訪問と契約の場面で大切にしていること(続き)
🏠 願いをこめて《オハナな管理人日誌 2025.3.20》
発病して以来の闘病生活を経て、いよいよ積極的な治療が難しくなり、厳しい余命宣告を受けていらっしゃる方も少なくないです。色々な気持ちに区切りをつけながら在宅療養へとそれなりの覚悟をされている方、受け止めきれずに現実を直視したくないのに限られた時間と選択をせまられている方、心のバランスを一生懸命に整えようとして治る希望が一筋の光に感じている方、電動ベッドを居間にセッティングすることやポータブルトイレの提案、もしかしたら医療者が定期的に訪問することも、自身の中の重症感が増してしまうことで敬遠するのも当然の心理かと思います。
とかく私たちは表面に出てくる言動や行動をこちらの物差しで判断しがちで、あの患者さんは病状の理解が十分でないと思われるので、もう一度ご家族と一緒に主治医から説明してもらうことが必要ではないでしょうかというアプローチになりがちです。目の前の大切な患者さんであることは間違いないですが、心の中まで手に取るようにわかるのでしたら、かえって不気味です。
苦渋の決断で退院することを決めたところで、部屋に訪れる医療者が口を揃えて「よかったですね。」の言葉が重荷になって、退院時期を躊躇された方がいらっしゃいました。医療者の癌末期のかけがえのない時間をご家族と一緒に過ごせる喜びを一緒に喜びたい気持ちもわからないわけでもないですが、角度を変えると、治療が難しい予後が限られていることを伝えられているのですから、病気を治せず自宅に帰ることが「よかった」ことに落とし込めない感情もあるのも当然なのです。
腫れ物をさわるような会話は真のコミュニケーションではないですし、限られた時間での信頼関係構築するためのスキルは経験と鍛錬も必要だと感じます。100人100通りのお互いの個別性があり、これまでの社会的な医療との関係性の影響もないとは言えませんし、当たり前ですが正解はないです。しかし、その時その瞬間の奇跡のような化学反応が起きることもあります。それは、自分の表情や態度・言葉・指の先・毛穴からも(!)気持ちが伝わるくらいに、その方の幸せを『願う』という強いマインドが必要だと感じます。さらに相手の変化を求めるという結果ためではなく、自分がこれ以上ないというくらいの『願い』をこめる目的やプロセスを大切にしたいと思います。それが今まで私が培ってきたコツといえばコツですかね。これは本当に奇跡と思われる瞬間や思いがけない化学反応がおきるリアル体験からの学びのひとつです。
その時が近づいてくるまでに〜じっくりと対話を積む①
🏠 がん治療と緩和ケア《オハナな管理人日誌 2025.3.21》
緩和ケアという概念が日本でも浸透してきてから、50年が過ぎました。医療は日進月歩で進歩していますので、当然50年前の医療からは比較にならないくらいの変化を遂げています。人々の健康と幸福に寄与するのが医療ですから、社会や環境やテクノロジーによって進歩してきた歴史があります。がん治療と緩和ケアもしかりです。現在の末期癌の治療の進歩により、『その時が近づいてくるまで』の期間がかなり限られている方が増えてきました。がんと闘病することだけでもいっぱいいっぱいなのに、先の治療や看取りまで考えましょうなんて無理な話なわけです。まずは今の現状と課題について、私と一緒に考えて見ましょう。
日本の緩和ケアの歴史
初期の取り組み (1970年代)
1973年、大阪市の淀川キリスト教病院で精神科医の柏木哲夫医師が、末期患者を対象としたケアチームを設立しました。これは日本における緩和ケアの始まりとされています。柏木氏は、アメリカ留学時に学んだ「死にゆく患者への組織的ケア」を参考に、医療チームによる包括的なケアを導入しました。
ホスピスの誕生と普及 (1980年代)
1981年、静岡県浜松市の聖隷三方原病院に日本初の独立型ホスピスが設立されました。この時期、いくつかの病院で緩和ケア病棟が開設され、施設ホスピスを中心とした活動が進展しました。
医療制度への統合 (1990年代)
1990年、緩和ケア病棟入院料が診療報酬として新設され、緩和ケアが日本の医療制度に正式に組み込まれました。この制度化により、全国的にホスピス・緩和ケア病棟の設立が進みました。
WHO定義と新たな方向性 (2000年代)
2002年、WHOが緩和ケアの定義を改訂し、「病期を問わず早期から行うべき」という考え方を示しました。これを受け、日本でも予防的対応や治療と並行した緩和ケアが推進されました。2006年には「がん対策基本法」が成立し、緩和ケアが国策として重要視されるようになりました。
現代の状況
緩和ケアは終末期だけでなく、治療初期から取り入れるべきという認識が広まりつつあります。在宅緩和ケアや通院型緩和ケアなど、多様な形態で提供されるようになり、患者のQOL向上を目指した包括的な支援が行われています.日本では当初、終末期医療として発展した緩和ケアですが、現在では治療と並行して患者や家族への身体的・心理的サポートを提供する重要な医療分野として確立されています。
地域の緩和ケアとして、ホスピス型住宅などがんの看取りを特化した施設が急速に拡大しています。基幹病院側からの受け皿となりやすく、「みとりビジネス」として高収入を得ている会社の倫理的な問題や、コンプライアンス違反、医療保険の不正利用、専門性不足の実態が社会的な問題として顕在化しています。ホスピス型住宅は公的に制度化された施設形態ではないため、明確な規定がありません。よって監督体制が不十分である可能性があり、今後のあり方について指摘されています。
🏠 がん治療と緩和ケア②医療倫理《オハナな管理人日誌 2025.3.22》
治療の限界がきて、せめて辛さに寄り添ってほしいという気持ちから、まわりのご家族も手厚い緩和ケアを期待してホスピス〇〇に入所を選択されるのではないでしょうか。前回のお話の「みとりビジネス」のように、その願いを踏みにじられることは、医療者としていや人としての倫理的な問題をはらみます。医療倫理の4原則からも、制度化されているかどうかに関わらず、理念とミッションが泣きます。
医療倫理の四原則
(1979年トム・L・ビーチャムとジェイムズ・F・チルドレスにより提唱)
自律性の尊重(Respect for Autonomy)
患者が自らの意思で決定し行動する権利を尊重する。患者が十分な情報を得た上で治療方針を選択できるよう支援する。
無危害(Non-Maleficence)
患者に危害を与えないこと、または危険を予防する。可能な限り侵襲が少なく、苦痛を引き起こさない治療方法を選択することが求められる。
善行(Beneficence)
患者にとって最善の利益を追求する。この「最善」は医療従事者ではなく患者自身が考える最善であるべきである。
公正(Justice)
患者を公平かつ平等に扱い、限られた医療資源を適切に配分する。
看護倫理原則→ちなみに看護倫理原則は次の2つ追加されて6原則で構成されています。
誠実の原則:真実を告げ、虚偽の報告をしない。患者や家族との信頼関係構築のために重要である。
忠誠の原則:守秘義務を守り、患者の秘密や約束を守る。
うちは介護だから医療者じゃないからなんていうのは情けない弁解です。原則にそって考えていくと、社会制度を利用しているにも関わらず、公正さが歪んでいることがわかりますね。安全で質の高い医療を提供することだけでは倫理的にかなっているとは言えないことがわかります。だからと言って選択肢がたくさんある世界ではないこともわかっています。弱い立場であるから泣き寝入りまでいかなくても、片目をつぶることもあるでしょう。一部の不正で全体が不利益になることも、本当に悔しい限りです。とはいえ自分に嘘をついて生きていきたくない、最後に残るのは強い信念でしょうか。
🏠 がん治療と緩和ケア③緩和ケア≠終末期医療《オハナな管理人日誌 2025.3.23》
緩和ケアとはがん終末期医療だと思っていませんか?緩和ケアの一般的な認知度についてのひとつのアンケート結果は以下のようです。
- 緩和ケアの認知度1:
- 「よく知っている」: 6.0%
- 「やや知っている」: 29.7%
- 「どちらでもない」: 14.4%
- 「あまり知らない」: 35.0%
- 「知らない」: 14.0%
- 緩和ケアのリーフレットの認知度1:
- 「知っており、読んだ」: 10.6%
- 「知っているが、読んだことはない」: 16.4%
- 「知らない」: 70.2%
- がんの早期から緩和ケアが受けられることを知っている人は約38%2。
- がん緩和ケアが早期から受けられることをまったく知らない人が約6割2。
これらの数字から、緩和ケアの認知度はまだ低く、特に早期から受けられることについての認識が不足していることが明白にわかります。「緩和ケア=終末医療」というイメージが依然として強く、この認識を変えていくことが課題となっています。その「緩和ケア=終末医療」というイメージを変えるため、医療機関にも動きは見られます。例えば、がん研有明病院では、「がん治療の柱の一つである」という考えから、2012年に「緩和治療科」と名称を変更しました。他にも、「緩和支持治療科」(聖隷三方原病院)、「緩和支持医療科」(岡山大学病院)、「がんサポートチーム」(大阪医療センター)などの名称で診療を行っている病院もあります。
癌と診断されたときが一番自死される確率が高い現状からも、がん研有明病院の腫瘍精神科のように「こころの専門家」がサポートできる窓口も求められていますが残念ながらリソースが追いついていません。
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspm/16/1/16_35/_html/-char/ja
- https://gan-mag.com/knowledge/2103.html
🏠 がん治療と緩和ケア④つつみ込むように…《オハナな管理人日誌 2025.3.24》
緩和ケアとは、生命を脅かす疾患による問題に直面する患者とその家族に対して、痛みやその他の身体的問題、心理社会的問題、スピリチュアルな問題を早期に発見し、的確なアセスメント対処(治療・処置)を行うことによって、苦しみを予防し、和らげることで、クオリティ・オブ・ライフを改善するアプローチである。
(日本ホスピス緩和ケア協会HPより抜粋)
実は緩和ケアには歴史的な変遷があります。WHOは1990年に緩和ケアを「治癒を目指した治療が有効でなくなった患者に対する」ケアであると定義し、緩和ケアは主に治療終了後に行われるものとされていましたが、2002年にWHOは緩和ケアの定義を修正しています。「生命を脅かす疾患による問題に直面している患者とその家族に対する」ケアであるとしました。この新しい定義により、緩和ケアは終末期に限らず、より早期から提供されるべきものであるという立場が明確になりました。それから20年以上が経過し医学も進歩していますがこの定義は変わらず、現代の日本の緩和ケアの指針も同様です。ですから緩和ケアとは、がんのすべての経過に関わりQOLの向上を目指す包括的なアプローチであり、癌と診断されたときから治療と並行して、つらさを感じる時にケアを受けることができます。
緩和ケア=終末期医療と捉えがちな原因
・前述した歴史的な定義の変遷
・緩和という言葉のイメージ、治療を諦めるというネガティブなイメージを持たれやすいため
・緩和ケア病棟への入院適応は終末期状態や看取り目的な患者さんが対象になるため、緩和ケアのイメージが終末期に限定しやすい
・診断時から終末期までの包括的アプローチではあるが、より終末期の方に注目が集まりやすいため など
前回もお話をした通りに、それぞれのがん拠点病院も全人的なケアを目指した日々努力されているのですが、本当に窓口が小さいです。多くの支援がそうであるように、こちらから一生懸命「助けて」と叫び続けて、やっとやっと声が届けばなんとか窓を開けてもらえるイメージで、「助けて」を言える勇気がでなければ声にならないでしょう。抗がん剤治療を受けながら日常生活を送っているがんサバイバーならなおさら、会社や家族に気兼ねしながらなんとか最低限通院だけは確保と必死な方が多いと思います。しかも、がん拠点病院がある大病院の平均受診時間は半日とかそれ以上で、帰宅して疲労困憊なことが容易に想像できます。がんサバイバーの心の声はSNSに投げられていますが、たくさんの共感を得ることもできる一方で、一般の心ない声に傷つけられるリスクは往々にしてあります。マギーズ東京や少しずつ癌患者さんのオン・オフラインサロンもできつつありますが、公の組織が主催していることも多く、24時間駆け込み寺みたいな場所は、商流を考えても経営が成り立ちませんものね涙。
辛い状況の中で、追い討ちをかけるようにSNSで心ない声に傷つけられないか心配になります。
🏠 ホスピスケア《オハナな管理人日誌 2025.3.27》
ホスピスケアは終末期ケアに似ているのですが、チームでのアプローチであることがしっかりと明記されています。今まではホスピス専門施設や病棟でケア提供されていましたが、在宅ホスピスケアが注目されています。住み慣れた自宅で終末期ケアが受けられることや、癌や難病に限らず全ての終末期ケアが対象であること、公的財源を圧縮できることなどメリットがあげられますが、地域の受け手側もリソース不足といえます。専門性が必要な分野ですが、さらに専門性を高めた多職種チームビルディングが求められています。永遠の課題かもしれません、どこまで行っても多職種連携って。それでもご縁をいただき、支援を重ねていく実践の中で大切なケアとして種まきをし、やがて花開く時を願いながら、また種をまいていく、そんな感じですね。その種まき自体は、決して苦行ではなく、とても豊な気持ちを与えて下さるのです。
ホスピスケアというと、治療できない末期癌状態になってしまった時に手厚く癌の辛さをとってくれることに特化したケアというイメージでしょうか。
ホスピスケアとは
<目的>
・患者さんが人生の最期を穏やかに、そして尊厳を持って過ごせるようサポートすること
・痛みや不快な症状を和らげること
・患者さんと家族の精神的・心理的なサポートを行うこと
<対象>主に末期がんなどの重い病気で、余命が限られている患者さん
<ケアの内容>
・身体的な苦痛を和らげるケア
・不安や恐怖などの精神的なケア
・家族へのサポートや相談対応
<特徴>
・病気の治療や延命ではなく、患者さんの生活の質(QOL)の向上に焦点を当てる
・患者さんの希望や価値観を尊重し、できる限り自然な形で過ごせるようサポート
<提供場所>
・専門のホスピス施設
・病院の緩和ケア病棟
・自宅(在宅ホスピスケア)
ホスピスケアは、人生の最終段階にある患者さんとその家族が、残された時間を大切に、そして可能な限り快適に過ごせるようサポートすることを目指しています。
ケアを受ける場のひとつである緩和ケア病棟では、入院するには条件がある場合も多く、本人が入院を希望している、対象が末期癌や後天性免疫不全症候群(エイズ)に限られる、余命1~3ヶ月以内である、がんであることを本人が認識し治癒を目的とした治療ができないことを理解している、その上入院前の審査や判定に合格することでやっと入院許可がおりるということもあります。費用は一般的に、専門のホスピス施設>病院の緩和ケア病院>在宅ホスピスケア が高額順になります。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。