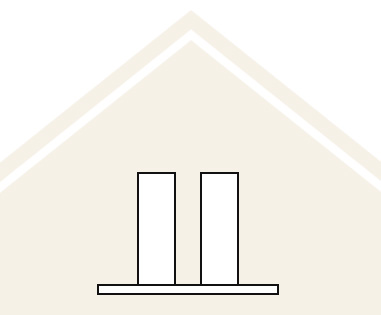緩和ケア医と精神科医が紡ぐ希望の対話:『心の闇を照らす光 – 専門医が語る緩和ケアの真髄』
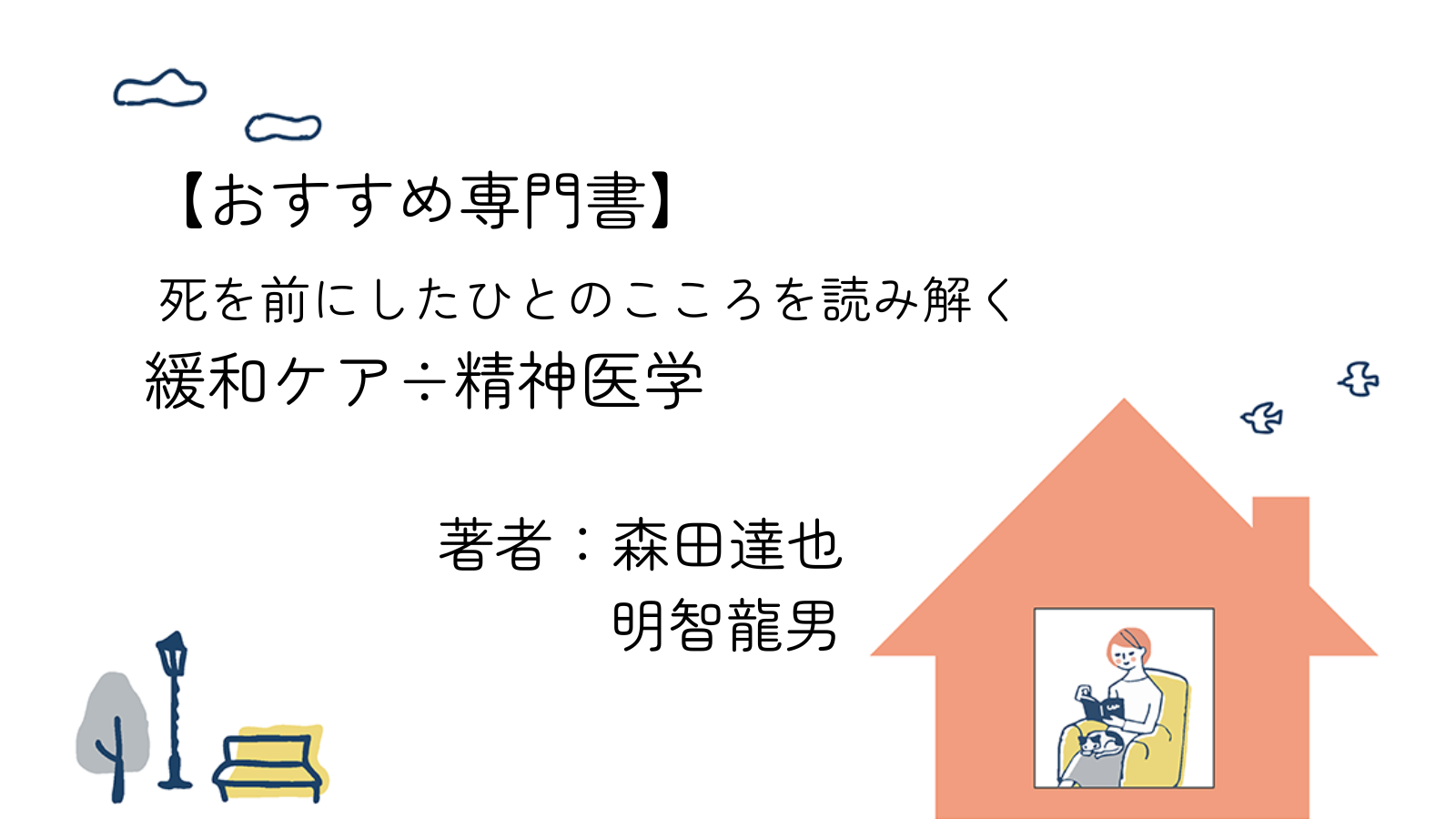
記事内に広告が含まれています。
本好きというわけではないのですが、気になると読みたくなる性質を持っている38ミーです。会社のクローゼットにも、しれっと38ミー図書が並んでいます。蔵書の中にも、森田先生の著書の本も数冊あります。看取りケアとなると私たちの仲間内でも二の足を踏んでしまう高いハードルに感じてしまいがちな分野なのですが、そんな初心者のガチガチの緊張を緩めてくれるように、医師ではない私たちであっても読みやすくわかりやすく書いてくださっている書籍がとても多いので、自然と森田先生の本が増えてきました。ある著書の冒頭に『看護師に育てられた緩和ケア医だと思う。』と自己評価されているのですが、緩和ケアの内容に看護が入っていることに驚きとうれしさですっかりファンになってしまいました。
共著者である聖隷三方原病院副院長緩和支持治療科の森田達也先生と名古屋市立大学病院緩和ケアセンター長などの明智龍男先生は30年来の友人で、「まえがき」と「あとがき」までもダイアローグになっているところも『うふふ』なのです。本書は新人のアサヒ先生が臨床で出会った困った事例に沿って、森田先生が精神医学的な見解について明智先生に質問します。それを受けて明智先生が精神医学の常識を解説し、さらに精神医学を超えて話を展開します。まとめで森田先生がテーマ全体を振り返り、新人のアサヒ先生のエピローグで締めくくる構成になっています。テーマの内容は、緩和ケアの経験をお持ちの方の方がより実感できると思いますし、振り返って何度も読み返しても良いと思います。実は私は在宅医療に携わる知人に本書を激推しして読んでもらい、感銘を受けたことなどお互いの感想を語りあったのですが、とても楽しいひとときでした。このシェアハウスの住人のふたりは、読書より私の解説を楽しみたいなんて虫のいいことを言うのですが、それも私のモチベーションですから、期待に答えましょう❗️
加えてさらに興味深いのは,「わかっていないこと」を掘り下げる中でたびたび顔を出す「医学を超えた問題」の扱い方である。その地点に来ると,二人は専門家の立場を降りて「一人の個人」として語りだす。その記述が本書の味わいをさらに複雑なものにしている(おそらくここを読んで「救われる」読者も少なくないと思う)。もちろん「死を前にしたひとのこころ」をこうした視点から取り上げた本は他にもある。けれどそうした本はしばしば独りよがりで思弁的になってしまうか,結局のところは「こころ」に関するある種の技法を用いて「こうすれば問題解決できます」と安請け合いするマニュアル本になってしまいがちだ。
「わかっていないこと」と向き合う作法
書評者:田代 志門(東北大大学院文学研究科教授・社会学)医学書院書評より抜粋
緩和ケア界の救世主の、悩める緩和ケア医の森田達也先生とためらいの精神科医の明智龍男先生が診療科を超え、ダイアローグを通して、死を前にしたひとのこころの紐解きに挑みます。私も緩和ケアに携わると言葉にできないモヤモヤを感じる場面があります。ひとの気持ちが本当にわかるわけではありません。とはいえ、わかりたいという気持ちを手助けしてくれる、そんな心強い本書でした。私というフィルターを通して終末期の心理について、一緒に考察してみませんか?
目次
Ⅰ・死を前にしたひとのこころ
精神科医が見る不安と抑うつの本質
死を意識したときのこころの動きは、『不安』と『抑うつ』に整理されます。不安と抑うつ(うつ)には、症状や体の変化に明確な違いがあります。
不安は、漠然とした未文化なおそれの感情が続く状態のこと。もともとは生物として生き残るために、脅威に対しての⚠️警告信号。「戦うか、逃げるか」を選択する上で有利な身体状況を作り出すといわれています。ですから強い不安感や恐怖を伴う一時的な感情で、身体症状が顕著です。
不安の例は、大切なプレゼンテーションの直前に、急に心臓がドキドキし(動悸)、手が震え、冷や汗が出るような状態です。そのほか、息苦しい(呼吸困難)、胸が圧迫されたような感じ(胸部圧迫感)、むかむか(胃部不快感)、めまい、肩が凝る(筋緊張)、寝付けない(不眠)など。
一方、抑うつは、(正常範囲を超えた)強い悲しみの感情が続いている状態のこと。より持続的な気分の落ち込みや意欲の低下が特徴です。
抑うつの例は、何週間も続けて朝起きるのが辛く、仕事や趣味に興味が持てず、食欲も落ちているような状態です。だるい、疲れがとれない、おいしくない、頭が重い、すぐ目が覚める、思考・集中力低下など。
恋愛相手に告白しようとしている時は、うまくいくだろうかと当然不安になり、失恋して恋愛対象を失ってしまうと喪失感でうつになってしまうことはわかりやすいね。
これらの症状は併発することもあり、不安障害とうつ病が同時に診断されることも少なくありません。どちらの症状も生活に支障をきたす場合は、専門医への相談が推奨されます。
目の前の感情に「そっと手を当てる」
死を前にすると当然不安や落ち込みがあって当たり前ということを念頭におきながら、折に触れて気持ちの状態を尋ねることは支えになれる可能性があります。
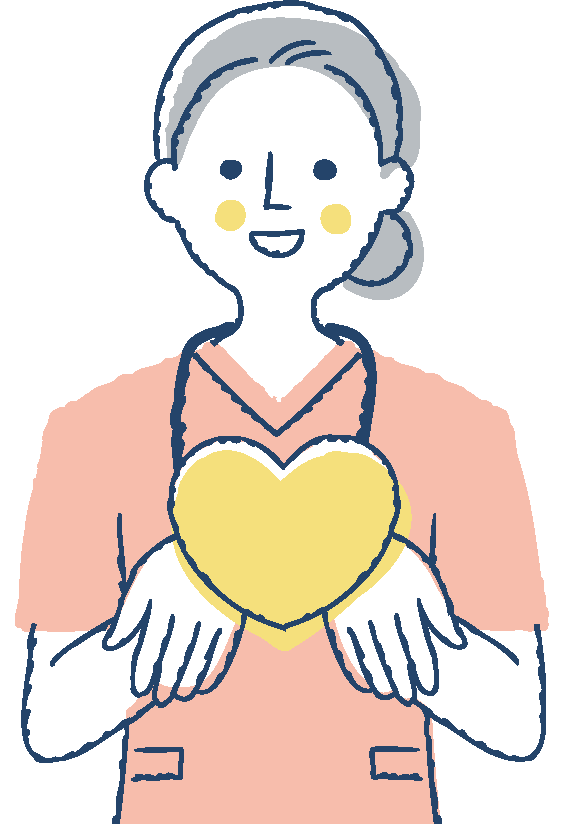
目の前の方の心に手を当てるイメージで。
よくコミュニケーション論で進められるしっくりこない『傾聴』を言語化するとしたら、
明智先生「感情に手当をする」
森田先生「患者さんの後ろ側に色のついた感情の塊のようなものをイメージして、それを一度自分の手の中に入れてから撫でたりさすったりしながら話を続けるというイメージ」
たとえ治療ができなくなってもケアはできます。心に手を当てるように、何か力になりたいという思いを乗せ、つらさを共有し、少しでも和らぐように願いを込めながら。
適度な不安は作業効率を上げる
不安やうつは、とにかくないほうが良いと思われがちですが、実は人の生存の歴史という視点からも必ずしもそうではありません。例えば病気になったとしても全く不安がなかったら、健康に気をつけたり、専門職のアドバイスを守る気持ちは起きないはずです。軽度な不安は、その人を守ってくれている機能となっているので、良い意味で『その不安』を大切にしましょうと言えるのです。2つほどトピックスを。
ヤーキーズとドットソンの法則
1. 緊張感が低すぎると、やる気が出ずに成績が悪くなります。
2. 緊張感が高すぎると、プレッシャーで失敗しやすくなります。
3. ちょうど良い緊張感があると、最高の成果を出せます。
人間の集中力や作業能力に関する面白い法則です。この法則は、「適度な不安・緊張感(ストレス)が最高の成果を生む」という考え方です。
たとえば、テスト勉強を考えてみましょう
1. テストが全然気にならない → 勉強する気が起きない
2.テストのことを考えすぎて不安になる → 頭が真っ白になって勉強できない
3. テストに向けて適度に緊張する → 集中して効果的に勉強できる
適度な緊張感を保つことで、自分の能力を最大限に発揮できるのです。逆を返せば、良いパフォーマンスには、適度な不安が必要だと言えますね。
抑うつのポジティブは面についてです。『抑うつ』と『ポジティブ』が同じテーブルに上がること自体、ほーーーって感じです。まだ仮説ではありますが、新しい切り口として面白く感じます。
抑うつリアリズム理論
この理論は、ローレン・アローイとリン・イボンヌ・エイブラムソンによって提唱されました。この理論は、心理学の中でも実験心理学の分野から生まれてきました。
【実験】ランダムな信号の点滅に対してボタンを押すゲームを行い、参加者の反応を観察しました。
1. 健常者:良い成績を自分の洞察力や実力のおかげだと捉える傾向がありました。
2. うつ病傾向のある人:良い成績を単なる運や偶然の結果だと評価する傾向がありました。
この実験結果から、うつ病傾向のある人の方が現実をより正確に認識していると考えられ、抑うつリアリズム理論が提唱されるに至りました。しかし、この理論には批判もあります。実験の設定が現実世界を適切に反映していない可能性や、抑うつの診断方法に疑問が残ることなどが指摘されています。そのため、理論の妥当性については現在も議論が続いています。
「気分は沈んでいるけど賢いかも?」そのうつ器質により、世の中を正確に見極めることや鋭い感性を持ち合わせ、指導力や創造性や才能で重要な業績を残した歴史的人物は少なくはないのです。リンカーン、チャーチル、ガンティ、ナポレオン、ルーズベルト、トルストイ、ナイチンゲール、ゴッホ、ヘミングウェイ、ベートーベン、徳川家康、夏目漱石、樋口一葉、与謝野晶子、石川啄木…等々、真偽はさておき。病状の程度によっては自死に至ることもあるのでその程度については議論はこれからも重要です。
とても辛いことに直面すると、落ち込み泣き悲しむという一定期間の抑うつ状態を経て、やがて現実を受け入れてスッキリしたという経験は誰しもあるでしょう。視点を変えると、抑うつ状態が生じるということは(=泣き悲しむ)、概ね客観的な現状の認識を受け取った証拠とも言えるということです!
泣いてスッキリすると思い込んでいましたが、泣く感情が生じたということ自体がリアルとして受け取れている証拠とも言えるという説でしたー。面白い👍
終末期の不安と抑うつ
死を前にした人の心としての不安と抑うつの理解
- 不安や抑うつは、がんの進行や再発の時期の30%くらいに見られる
- 「適応障害」が「適応反応症」と言い換えられたように、精神疾患ではなくストレスに対する反応である
- 不安があることで「早く物事が進む」という側面がある
- 抑うつがあることは事実を事実の通りに受け取れている証拠ともいえる
終末期の不安と抑うつに対して臨床家に勧められること
- 適度な不安や抑うつの表出があった場合、つらい感情があってよかったという前提に立ち、「感情にそのもの」について話題にする(不安や抑うつの表出をなくそうとしなくても良い)
- 「感情に手当てをする」イメージを持つ
- 2週間以上継続して気分が落ち込んだままで楽しい時がない症状があれば、薬物療法や精神科医への紹介を考える
不安がないようにと考えがちな私たしのナース脳に、稲妻が走る思いです。よく考えると不安には意味があり、軽いうつには役割があります。不安や抑うつがあって当然だという前提を踏まえて、不安や抑うつをぶった斬って成敗するのではなく、感情に手当をするイメージを持つことが大切。ただ、長引く抑うつは専門家に相談を提案することは注意しましょう。
終末期の「うつ病」
何はすべきで何はすべきでないか?
うつ病による健康損失への影響はがん以上であり、今後も影響が拡大することが予測されています。うつ病は治療できる病気で、積極的に治療を受けるべき疾患だというのは言うまでもありません。前回のお話にありましたが、2週間以上継続して気分が落ち込んでいる症状があれば治療を受けることが重要です。
終末期ではうつに対する積極的な治療が害にしかならないときがある
ただし、うつ症状の薬物療法は即効性に欠けるため、生命予後が週単位であれば効果が期待できないのです。さらに、薬物によってせん妄が強くなり、最期までせん妄状態でその人らしさが失われたまま旅立つことにもなりかねません。終末期のうつ症状に関しては予後や、本人家族が望んできる過ごし方、何を優先するのかをよく相談することが大切です。
たとえ、うつ病に対する治療を行わない場合であっても、ケアができないことではない。
うつ病に伴う苦痛が最小とするために夜間の睡眠の確保や、時にはうつが忘れられる時間を作るための日中でも数時間睡眠の確保をする。また、うつ症状を難治性の苦痛緩和ケアとして捉え、日常のケアとして快につながること(足浴、マッサージなど)を提供する、患者の尊厳を大事にした関わりをすることは常に大切なことである。
日常の心地の良いケアを丁寧な思いやりで優しさを込めて提供することが、どの局面やどの苦痛においても緩和ケア支援として原点回帰するのは、とても意味深く感じます。
ははは、ここでも着地点もやはりこの論点でしたね。それに気がつけることがどんなに重要か伝えていくのも役割でしょうね。緩和ケアに限らずです。
終末期の「死にたい」
Cry for help
妹達の切実なリクエストに応えるべくチャレンジしましょう。とてもセンシティブな論点でSNSでの発信がとても悩ませる、でも大切なこと、緩和ケアにおける希死念慮です。
先日の看護学生さんに向けての講義の中でも、魔法でも使わない限り叶えてあげられない悲痛な希死念慮の願いをあえて取り上げました。現実問題として難しいのがわかりつつも、Beingの大切さを説くと空気が変わりましたね。社会通念上や倫理的な理由という解釈で、本人の悲痛な言葉を淘汰してはいけません。希死念慮が生まれるくらいの苦痛にさいなまれていることを、理解したい気持ちから生まれる化学反応があります。『心をイメージして手当をする』その感覚に近いかもしれません。ボロボロの心を包み込むような優しさで話を受け止めケアを重ね、どんなあなたであっても、ここにいてくれること。縁があって出会えたこと。こうやってかけがえのない時間が過ごせること。ここ、今、この瞬間の私の幸せとあなたの存在への感謝を伝えたいと思うのです。
そして、あなたの切実な願いならば、少しでも早く叶うように祈りたいです。
Suicidal thoughts
森田先生と明智先生にとっても、「希死念慮」を書籍で扱うのは、きっとどんな切り口で話を展開するのか悩まれたのではないでしょうか。まずは読者に問われました、これまで生きてきた中で一度も「死にたい」と思ったことのない人ってどれくらいおられるのでしょうか?と。あまりにも大変な出来事があり心が潰される思いでストレス対処のひとつとして、消えてなくなって楽になれたらと頭の中で考えることは稀なことではないのでは、実際に森田先生も明智先生も割とそういう気分になりがちだと告白されています。ちょっと死にたくなるのはよくあることで、精神医学的に問題として扱わないけれど「持続的に、強く(そのことばかりを具体的に)考えている」となると「精神症状」として扱われます。
Thoughts about dying at the end of life
さらに終末期の「死にたい」背景は、精神医学の一般診療とはまったく異なります。
進行・終末期のがん患者の希死念慮
おおむね10〜20%の患者に希死念慮や死を早めてほしいという希望が存在する。
その背景には痛みをはじめとした身体症状、身体機能の悪化、うつ状態、絶望感、社会的サポートの乏しさ、実存的苦痛など多彩な臨床要因が関連しているとたくさんの研究で明らかにされている。
死を早めてほしいという希望を表明した進行がんの患者を対象とした、その意味することを質的に検討した報告からは、「早い死の希望」は多くの意味を含んでおり、『生きたい』ことに対する逆説的表現、死にゆく過程のつらさ、いま現在の耐え難い苦痛(痛みなど)に対する援助の求め、今後起こりうる耐え難い苦痛から解放される対処法の一つ、一人の個人として関心を抱いてほしいという欲求、愛他性の表現、家族から見捨てられる不安、悲嘆、苦悩などを表現するためのコミュニケーションである可能性が指摘されている。
上記の研究結果をふまえると、終末期の希死念慮の背景は多様である。まずは希死念慮の意味を理解し、「死にたい理由」をひとつひとつ丁寧に考えて、ケアの仕方を改善する努力することで「死にたい気持ちが減らせるか」を考えることが、まず取り組むべきことであると言えます。
「死にたい」という言葉にふたをしてはいけないということですね。つらさがあることへの大切なサインであるかもしれないということを私たちは忘れてはいけないということです。まずは「死にたい」くらい辛い気持ちがあることを受け止め、どうしてそう感じるのかまずはそこからケアをはじめたいと思います。
根本的に緩和されない希死念慮とは
コタール症候群
不死妄想・永延妄想が症状のひとつ。いわゆる死ぬことすらできないという底知れぬ強い苦痛があること。高齢の重症にうつに見られる症状。
サイオンコロジー界において大変示唆に富んでいる概念である。逆説的にいうと想像を絶する苦悩の中では、死が救済になり得るということ。
合理的希死念慮
終末期において、こんな状態であれば誰しも死にたくなるなるよなぁというぐらい辛い状態や状況が存在する。(例えば、難治性の激痛、耐えられない呼吸困難、身の置きどころがない言いようがないだるさ等)安楽死を制度化している国もあるが、日本では許容されていない。
緩和ケアの最終手段として、意識を低下させることで苦痛を感じさせないようにする鎮静のガイドラインがある。適応となる場合に、苦しくてどうにも過ごしようもない時間は、(短時間でも)眠って苦しくない時間を確保する間欠的鎮静(眠ったあとに回復していることを目的とする場合はrespite sedation)といわれる手段などがある。
希死念慮への背景には様々な苦痛が横たわっていますので、まずはそのつらさを知り理解に寄り添います。どうして死にたいのかの理由に対処して、身体的苦痛があればその緩和、楽しみがなければ快の提供、たとえ寝たきりであっても自己決定による自律性の尊重に努めます。とはいえ難治性の苦痛も存在しますので、ガイドラインによる適応があれば鎮静も可能で、辛くて仕方がないときに数時間でも眠ることができ、その間は苦痛から解放される時間を確保できるのです。
医学がどれほど進んでもすべての死を無くすことも、すべての人間の苦しみをなくすことはできません。そんな場面では、そこにとどまること、一緒に苦しさを理解しようとすること、苦しい中にも1日でも一瞬でも生きてきてよかった思える時間を探すこと、いわゆる『幸せ』探しが求められています。
すべての人間としての苦しみを医学が無くすことはできません。それであってもそこに一緒にとどまり、日常の『幸せ』探しが灯台のような明かりになると考えます。
「スピリチュアルペイン」と呼ばれるもの
Why me? なぜなぜ私なの?
Why me?スピリチュアルペインを語る前にちょっとおさらいを。
スピリチュアルペイン(霊的苦痛)
近代ホスピスの創始者である英国の医師シシリー・ソンダース(Cicely Saunders)によって提唱される。終末期患者が経験する苦痛を単に身体的側面からではなく、「トータルペイン」全人的苦痛という概念で説明し、その中に身体的、精神的、社会的、スピリチュアルペイン(霊的苦痛)な側面から構成されているという全人的な視点のひとつ。
『スピリチュアル』の言葉のイメージ的には理解が難しい領域ではありながらも緩和ケアの基盤となる重要な考え方として定着しています。「どうして私が」-why me?の苦悩や死後の苦しみへの不安や「(末期癌で)生きていても意味がない。」等という苦悩の気持ちですよと言われると、あーそうかと納得して頂けるでしょうか。
ではスピリチュアルペインをお二方の先生の分野で割り算していただきましょうか。
精神科領域から「スピリチュアルペイン」を照らすと、多くは既存の精神疾患の診断基準に当てはまらず、いわば正常の反応ととらえられる状況と言えます。たとえば苦悩に加え、興味関心の低下、不眠、食思不振、希死念慮があれば、『うつ病』ですねと診断されます。
スピリチュアルペインの二つの軸
①【宗教的な軸】人間を超えたものに対する感情
→ なんでこんな苦しみを与えるのかという神や先祖への怒り、死後の世界で苦しみを受ける不安など
②【実存的な軸】人間として自分が消滅することに関する苦悩
→ 意味のなさ・価値のなさなど
そんなスピリチュアルペインに似たものを扱った精神療法としては、サイオンコロジー領域から、実存的精神療法、意味に焦点を当てた精神療法、ディグニティーセラピー、そして実存療法として V.E.フランクルのロゴセラピーがあります。
精神医学でも「スピリチュアルペインという概念はない」と言いつつも、実際に患者さんが体験するスピリチュアルペイン(らしきもの)に対するアプローチが試みられていたということがとても興味深いですね。
スピリチュアルペインは解決できません
スピリチュアルペインは、苦悩している人から生まれるものであって、他人がどうこうできる性質の苦痛ではないということは知っています。でも、いつも私の話を真剣に一生懸命に聴いてくださるあなたには打ち明けたいのです。わかってます、解決ができない苦悩だってことも。あなたはとても忙しいはずなのにそんな素振りを見せずに、私の話を聴いてくださり、受け止めてくれることがどんなに嬉しいことか。終末期だから仕方ないと諦めずに、身体の辛さを緩和することを一生懸命に力を惜しまず対峙してくれ、眠れることを一緒に喜んでくれることに、どんなに救われることか。いつもの笑顔のあなたの存在自体が、苦悩で擦り切れた心のエネルギーを満たしてくれるのです。
こんなふうに感じて頂けたら、支援者である私たちもどんなに救われることでしょうか。医療者は問題解決思考でトレーニングされているので、解決できない問題には不慣れなのです。そうだとしても「スピリチュアルペインを無くそう」なんて勢いで来られると、お帰り下さいって言いたくなります。まるでマインドコントロールをすることと同じですから、他人の心を動かすことはできないのです。それを逆手にとると自分の心は自分で決められるでしょう。目の前の苦悩を残念ながら私が無くすことはできませんが、辛さが和らいで欲しいという願いが、私の手のひらから、じわーっと伝わると思います。
亡くなった人にケア評価してもらいたいものですが、残念ながら次の世界で会えるまでのお楽しみになっています。筆者の先生たちが記してあることは、まさにそのまま私のつたない経験の中でも全く同じように感じます。それまた不思議なことですが、自分のケアの軸へのチューニングになりました。
防衛機制と呼ばれるもの
プンプン【防衛機制】置き換え
感情むき出しで患者さんに怒鳴られた経験が、看護師ならひとつやふたつあるのではないでしょうか。ハラスメント的観点は今は置いておいて、どうして火がついたように怒りが湧き上がってくるのでしょう。特に緩和ケアの状況でよく見られる『防衛機制』を一緒に押さえておきましょう。
防衛機制とは、強いストレスや不安を感じたときに、自分の心を無意識に守ろうとする仕組みのことです。これはオーストリアの精神分析学者フロイトが提唱した概念で、人間が困難な状況に直面した際、心のバランスを保つために働きます。
防衛機制の主な種類と例
1. 抑圧: 嫌なことや不安を無意識に心の奥に押し込めること。
例) 怖い夢を見たけど、朝には内容を忘れている。
2. 合理化: 自分の失敗や行動にもっともらしい理由をつけて正当化すること。
例)テストで悪い点を取ったとき、「勉強する時間がなかったから仕方ない」と思う。
3. 同一視 : 他人の良いところを自分と重ねて満足すること。
例)好きなスポーツ選手が活躍しているのを見て、自分も誇らしくなる。
4. 投射: 自分の嫌な気持ちや欠点を他人に押し付けること。
例)自分が苦手な先生が、自分のことを嫌っていると思い込む。
5. 反動形成: 本当は好きなのに、その逆の行動をとること。
例) 好きな人にわざと冷たく接する。
6. 逃避: 現実から目をそらして別の世界に逃げること。
例) 勉強が嫌でゲームばかりする。
7. 退行: 幼い頃の行動に戻ることで安心しようとすること。
例) 怒られた後、泣いて親に甘える。
8. 代償: 本来欲しかったものが得られないとき、別のもので満足すること。 例) 欲しいゲームが買えない代わりにマンガを読む。
9. 昇華: 不満や欲求を社会的に価値ある行動に変えること。
例) ストレス発散のためスポーツや絵を描く。
10.置き換え: 本来の対象ではなく、別の対象に向けること。
例)職場で上司に叱られたストレスを、自分より立場が弱い家族や物にぶつける。
11.投影: 自分の内面にある感情や欲求を他人に押し付けること。
例)自分が職場の同僚を嫌っているのに、その感情を認めたくないため、「あの人は私のことを嫌っている」と思い込む。
病状によって辛い症状への怒りのやり場に困っているところに、つい目の前の人に八つ当たりしてしまうのは、防除規制の中の『置き換え』に当たります。
当たられた方は理不尽に感じますが、実は患者さんがこういった場合に怒りを向ける対象は、多くの場合は、信頼していたり頼りにしている存在であることが多いのです。とはいえ、私たちも人ですから凹みますよ、私だって、ねえ笑。
それって誰の気持ち?【防衛機制】投影
防衛機制のひとつ『投影』のおはなし。自分の気持ちや抱えている問題をまるで他の人が経験しているように感じることです。無意識な心理的防御ですから、目に見えないものであり、投影によって真の問題が誰のものなのか見えにくくします。
緩和ケアで生じやすい投影の例
⚫︎患者ー家族間
患者の不安が強いという家族の訴えは、むしろ家族の不安の方が強かったりすることがある。
⚫︎医療者(自分)ー患者間
特に対象の患者が自分と重なる困難を抱えているとしたら、なおのこと自分の問題を「患者さんが感じている」ように体験することがある。無意識的な認知であるので気がつくことは難しい。
ある、ある、ある、ありまーす!
思い当たるエピソードは結構ありますが、それが投影かも?という深いアセスメントはできていませんでした。そうですね、例えば、がんの痛みが強くて別の薬の変更が必要かどうかっていう場面で、癌性疼痛は悪だという価値観のもとで医療者がアセスメントをすると、「かなり痛そうで辛そうです」と報告を受けた医師が実際に診察にいくと患者本人はそうでもなかったという事例はもしかしてだけど、です。患者さんが痛みを否認しているということもあるので限定はできませんが。そのお医者さん側からすると、え?報告してくれた看護師さんの投影だろうか?なんて逆アセスメントする先生はやや変◯チックですね、怖いです。
とても大事なことは、『置き換えも投影もなくすことはできない』という知識です。
怒鳴られて、ウッと立ち止まった時にメタ認知で俯瞰することができると、「あーもしかしてだけど、置き換えかなあ。私のことを信頼しているから感情的になってたんだなぁ」と、怒鳴られた心のダメージの回復がいくぶん早くなるやもしれません。間違っても、「怒り=病状の受け止めができていないから、もう一度主治医から説明してもらいましょう」なんて、正しい説明の応酬で怒りを増幅させることは避けましょう。
そして、自分が絡む場合の「自分の問題」が患者の問題のように見える投影については、こんな場面によく使うフレーズがあります。「私には〇〇のように感じますが、あなた(患者)はどうですか?」と率直に聞いちゃいますね。そして「それで何か助けが必要でしょうか?」と問題についての相手の捉え方を確認します。その問題について掘り下げて尋ねることで、同じ温度感で情報共有すると誤解が起こりにくい肌感があります。まあ、その話をした時はそうでもあっても、考えはいつでも変わる可能性があることも覚悟しておくと振り回されずに心穏やかに対応しやすくなります。
悲嘆
哀しいかな、哀しいかな、また哀しいかな
『哀しい哉(かな) 哀しい哉(かな)
哀れが中の哀れなり悲しい哉 悲しい哉
悲しみが中の悲しみなり哀しい哉 哀しい哉 復(また)哀しい哉
亡弟子智泉が為の達嚫の文/空海
悲しい哉 悲しい哉 重ねて悲しい哉 』
あの悟りをひらいた空海でさえも、大切な弟子に先立たれた時に詠んだ詩とされています。ライフイベントの中でもパートナーの死が人生の最大のストレスであるという研究結果もあります。誰にでも起こりうることですが、とても辛い出来事のひとつ。大切なひととの終末期を過ごし、ピリオドが打たれて瞬間から、死別の苦しみの中で生きていくことの始まりを意味します。
死別後の悲しみも「病気なのか?」というテーマです。
大切な人との死別後に、悲しい気持ちになり、興味を失い、睡眠や食事がうまくとれず、気力を無くし、興味を失い、睡眠や食事がうまくとれず、気力を無くし、仕事が手につかないーそれは当たり前の反応で、うつ病とまったく同じ症状が出ることは珍しくありません。もちろん死別という人生最大のストレスによって、まともに生活ができないくらいのうつ症状が見られることもあり、それは医療の手助けが必要なケースもあると思います。一方で専門家の中にも<正常>を救えと精神医学的な診断として医学化しすぎているという批判もありました。そのような流れも踏まえながら、現状と課題について、お話を次に続けてみましょう。
悲しみを癒すものは
悲嘆の苦悩について【現状と課題】
⚫︎精神医学診断基準DSM-5からは一時は除外されていたが、死別後でもうつ病の診断基準を満たせばうつ病とみなすことになった。
⚫︎DSM-5-TRでは、特別有効な治療法があるわけではないが「遷延性悲嘆症(長引く悲嘆)」の診断基準が明確化されたので「診断名」としてつくようになった。
⚫︎死別後の悲嘆を精神医学上「疾患」のようにみなすことについて、正常な悲嘆プロセスを医学化するものだという強い懸念がある。悲嘆を医療の対象にすれば、心痛が低俗なものになり、死別を乗り越えていく自然な過程が妨げられ、悲嘆を癒すための伝統的な文化的儀式が頼りにされなくなり、有害の恐れのある不必要な薬物療法を招くことにもなりかねない。
⚫︎死別後の反応の個人差は大きく、日々の生活に大きな支障がない場合には「ちょっと変わった」体験が見られてもそのままで見守るようが良い場合が多い
実は似たような論点が緩和ケアの中でも、自然なものと「医療化」の中で揺れ動いています。たとえば、死前喘鳴を薬物で予防すべきかという論点があります。死前喘鳴が自然な経過ですよと説明したとて、苦しいと捉えて見守る家族にとってはずっと苦しい記憶が残ります。それらは医療側が勝手にしているのではなく、ご遺族の生活がより平穏になることを願ってのことなのです。
ホスピスケアの原点は、延命治療といわれる過度の医療化されたしの過程を、市民の手に取り戻そうというムーブメントから始まりました。しかし皮肉にも、現代においては、医療者が関わるホスピスケアプログラムがなければ平穏な最期を迎えられない高度に医療化された社会として発展してしまいました。
もともと人間社会が持っていた死別後の悲しみを癒すための儀式に医学がとって変わろうとしてはいけない、抗うつ薬よりも悲しみを癒す仕組みを人間社会は持っていることを忘れてはいけない。
緩和ケア÷精神医学 森田達也・明智龍男 医学書院P127
そう森田先生は締めくくっています。とてもズッシリとくる言葉ですが、忘れがちが大切なことを言葉にしてくださいました。
この『医療化』問題は、とても悩ましく感じる場面に何度も何度も遭遇し、いまだにもやもやしたものを抱えています。特にパターナリズムが強くある環境下から在宅に移行する際に、同じ日本であっても文化的違いってこういうことかと面食らいます。『医療化』至上主義では、すべての苦しみを癒すことができないことを知っているからです。
Ⅱ.死を前にしたひとのこころを支えるための方法
支持的精神療法と共感
受容・共感・傾聴
緩和ケアの精神的ケアのスタンダードの『受容・共感・傾聴』とは、医療職ならなおのこと、とても大切な関わりであるのは周知のことでしょう。それぞれふわっとした言葉のイメージは持っていても『言うは易し行うは難し』この言葉がピッタリです。ちょっと回り道になりますが、すべての精神療法や心理的療法の基礎となる支持的精神療法は『ひとのこころを診察するとき基本となるもの』の要素であり、それらに中に受容・共感・傾聴が含まれます。
精神療法(心理療法)とは、一般的には、人との言語的、非言語的なコミュニケーションを通して、苦痛を和らげる治療法のことを指します。話をするだけで気持ちが楽になることってよくありますよね。実は治療においても大きな影響があり、薬物療法に加えて精神療法が併用されています。その精神療法のタイプに問わず、まずは信頼関係や礼節、誠実さ、あたたかさ、思いやり、相手の苦痛をすくいとる感受性などがないと、自分のことを任せられないと心を閉じてしまい精神療法どころではなくなります。
その基本中の基本である、受容・共感・傾聴について考えを深めていきます。
共感は「本当にわかる」ことじゃない
誰しも自分のことさえもわからないのに、相手を「理解できる」ものではないと言う前提条件から始まります。
じゃあ、支持療法とは机上の空論だと言いたいわけではなく、「共感」の本質は、わかることではなく、「理解しようと努力する態度と姿勢」のことなのです。
あなたの気持ちわかるわーと軽々しく言われると、あなたにわかるわけないじゃない!という気持ちが沸々と浮かび上がる経験ありませんか?それよりも、自分のことを理解しようと一生懸命にされる態度や姿勢そのものに、ホッと心が軽くなることあります。それが共感の本質であるのではと明智先生は解説されています。
よく終末期ケアにおいて、何かすること(doing)よりもただそこにいること(being)が重要をいわれますが、この背景にも共感しようとする努力や態度があるからこそ、そこに居るだけでどこにもないつながりが生まれ、あたたかさがじんわりと伝わっていくのかもしれません。
緩和ケア÷精神医学 森田達也 明智龍男 医学書院P137
なんて勇気をもらえる言葉なのでしょう。そして、支援者がよく理解してその努力や態度が当たり前になる日まで、私にはやるべきことがありそうです。
傾聴は聞くではなく、聴くのです。
語る相手の表情や声のトーン、節目がちに、沈黙があったり、今どんな気持ちで言葉を重ねているのだろうか、言い表せないけれどいつもとどことなく違う、そんな風に受け止めながら話を聴いたとしても、やはり完璧に聴けるわけはないことを知ると、「傾聴しました。」とは言えませんね。これも全てに通じること、あなたの話を聞きたいという態度だけが少し傾聴に近づくことができるのかもしれません。
ここでも傾聴の前段階である、非特異的要素が大切だと重ねて解説されています。誰しもそう感じることでしょう、私のことを思って聴いてくださっていると相手の体から醸し出される気遣い(誠意ややさしさと言う言葉が近いでしょうか)があるからこそ、話を打ち明けても良いという安心が伝わります。スキルや技術以前のZEROベースです。私の感覚で言わせてもらうと、『よかったら何か力になりたいと思っています』という願いですね。体から溢れ出し、言霊にも込められるくらいの強い願いは、無意識下であっても相手の心に伝わってしまうものです。
しあわせな距離感
精神科では距離感を保つことが治療となり、緩和ケアでは2人称に近い、ひととひととの関係の誠実な姿勢が苦痛緩和のベースになります。
どちらも目の前の患者さんの幸せのための距離感ですが、真逆な作用であるので、精神科に慣れていない専門職にとっては考えたこともない観点なのです。展開が早い終末期では今の足元から解決する必要がありますが、長いお付き合いとなる精神科では先を見通しながら限界設定(きまりを決めてぶれずに遵守する)することが治療に役立てトータルで見ると幸せに寄与できるということなのです。
すべての支援者に共通していることかと思いますが、はじめが肝心ですよね。ファーストインプレッション、第一印象は本当に心を砕きます。私たちのように終末期ケアの介入は、時間が限られている中でまずは信頼関係、ラポール形成をいかに迅速に構築できるように全集中します。私の経験からは、そこには看護師としてだけでは物足りなく、人としてのマインドが必要に感じています。ですが、それを精神医学的とくにボーダーライン心症に至っては、その距離感は諸刃の剣になってしまう悲しい結末を精神専門家は知っているので、治療としての最初の距離設定がとても重要なのです。
精神訪問看護では、とても腑に落ちる見解で、先生方もそうだといってましたが、私にも苦い経験はあります、そういうことなのかと。
全くスタンスが真逆な距離感ですが、しあわせな距離感として意識的な関わりがとても大切だということですね。それが目に見えず、『心で感じるんだ』と言ってしまうと、まるでスターウォーズの世界で、笑。できるよりもまず心得るから始めていきましょうか。
日々の関わりで、僕たちの言葉や態度でどれだけの「苦痛を和らげる治療(緩和ケア)」の結果が左右されているのかが身に染みます
緩和ケア÷精神医学 森田達也 明智龍男 医学書院 P153
森田先生の言葉…しっかりと心に刻まなきゃ。
ディグニティ遺したい想い
【ディグニティセラピー】終末期患者を想定して、少ない回数で「人生において自分において意味のあると思えたこと」「愛する人に伝えておきたいことや知っておいてほしいこと」をインタビューし、記録を作成して患者さん・ご家族と共有することで、実存的苦痛に対するアプローチのことです。
『太陽と死はずっと見つめることができない』の言葉にあるように、ひとは死にずっと向き合い続けられるものではないのです。このディグニティセラピーは世代継承性が大切なテーマに感じている人には良い効果ありますが、ずっと見つめることができない心情の方には逆効果です。記録を残すことが遺言感が出てしまうので、文章を作らないまでも、本人も家族も、何か残したいなと(何か残してほしいな)という気持ちがちらっと見えたときに、タイミングを逃さず、橋渡しする方が自然な形に感じます。
そういえば娘さんから頼まれたことがありましたね。亡くなった後に大切にしたいから、本人からの手紙が欲しいのだけど、看護師から伝えてもらえないだろうかと。手紙を書ける時間も限られていましたので、早速ご本人に伝えました。書くのをためらっていましたが、娘のためにと思っていたと思います。手紙を書かないといけないと頭ではわかっていても、まだ残されている時間はあるという希望から書くのを先延ばしにしていたのではと今はそう思います。あっという間に起き上がれなくなり、手紙は完成することはありませんでした。
また別の方は退院直後から身体的な苦痛が強く、残された時間もかなり限られている印象を受けました。元々口数の少ない方でしたので、後から後悔される方もいらっしゃったのでと前置きして、ご本人ご家族ともに伝えたいことがあれば先延ばしにしないようにとお伝えしました。想像以上に経過が早かったので、ゆっくりと話ができなかったのではと心配するのは杞憂でした。実はご本人が治療困難と告知された頃に自筆証書遺言書保管制度を利用され、ご家族宛の手紙が遺されていたそうです。特に遺産相続に関して遺言を残したい方には公的なシステムで手数料も安いので実質的なディグニティとして有効です。
緩和ケア医としてがん患者約千人を看取り、自らもがんのため45歳で亡くなった関本剛さん。生前に収録し、自身の葬儀で上映した「別れのあいさつ」の動画は注目を集めました。https://youtu.be/lX0l4vNUhoI
関本医師のように太陽を見つめるために心のサングラスを持ち合わせているひとは少ないでしょうが、これからはこういうディグニティも増えてくるかもしれませんね。このセクションにとっては余談になりますが、関本先生の動画で話される内容のような死後の世界観がとてもしっくりいきます。たくさんのお別れに立ち会う私たちに勇気を与えてくださる言葉ですし、そう思えることは私が生きていく上でも死ぬときでさえも希望になるだろうと感じます。
受け入れるACTというケア
アクセプスタンス&コミットメント・セラピー(ACT)
片仮名にすると難解に感じますよね。認知行動療法のひとつと位置付けられていますが、とてもユニークな理論です。病気や症状の低減を目標にせずに、そのままにしておき(受け入れる=アクセプタンス)、元々大切されていた価値に基づいた行動に気がつき、それに目指して生き直すという治療法だと明智先生は解説されています。それでも治療法なの?と、ただの放置や怠惰なだけじゃないとと勘違いされそうですね。もう少し突っ込んだ解説をすると、病気や症状が解決できないタイプであればあるほど、意識のスポットライトが病気や症状に偏ってしまいがちです。支援者はなんとか問題解決しようと思案しますが、人間が施せない領域の壁にぶち当たり、本人も支援者もお互いに苦しみの螺旋階段をグルグルと回り続けることになります。ACTでは病気や症状はそのままに受け入れ、その意識のスポットライトを目の前の今、ここでの自分にとっての価値(喜びや穏やかさに)に当てられるようにサポートすることだと言えます。
有名なニーバーの祈りをご存知でしょうか。
ニーバーの祈り
変えられるものを変える勇気を、変えられないものを受け容れる冷静さを、そして、変えられるものと変えられないものを区別できる知恵を与えたまえ
緩和ケアの本質が詰まっている深い言葉に感じます。変えられること、つまり緩和できる苦痛は全身全霊でサポートしていく、そして変えられないこと、死がそう遠くない将来に生じることを抗おうとしても現実は厳しいわけです。どうこうしようともできないことは置いておいて、今日、いま、ここでのしあわせ探しを一緒に共有していく。それは「夜と霧」のヴィクトール・フランクルが提唱したような価値を彷彿させられます。
Franklの3つの価値
①創造価値:何かを生み出したり、創造したりすることの価値
②体験価値:自然や芸術、愛情などを経験することの価値
③態度価値:自身の運命に対する態度、姿勢によって生み出される価値
これが慢性疾病や加齢によるもので辛さを抱えながら生きていく方への支援として提唱されている、ストレングスモデルも捉え方が似てますね。ただし時間軸が入ると、より適切なアプローチを選んでいく必要がありそうです。
ACTの概念の中でも同じように出てきましたが、『まず自分自身が医療者として、自分の無力さに自覚的になる』という前提が、どの局面においても支援へと導いてくれるということがとても感慨深いです。無力な自分だと知ることが、誰かのお役に立てられるかもしれないんですから、禅問答のようです。そういえばACT入門の本で『幸福になりたいなら 幸福になろうとしてはいけない』というタイトルがあります。そちらの本は翻訳専門書なので、読み解くには時間が必要ですな。いつか解説してみたいですが。
このACTの章のおかげで、私が支援者として無我夢中にしていたことを解説してもらえたので、ロジカルシンキングとしてスッキリできたことが驚きの発見でした。なるほどって、ガッテンボタンか、へえボタンを押したい気分ですよ。今までつたないながらも終末期に向き合い続け、役に立ちたいと思う一心だったことが結果オーライで、これまでバーンアウトせずに過ごせているのだと、改めて委ねていただける偉大さを感じました。
Ⅲ.患者・医療者関係と意思決定
精神医学からみた意思決定
自律性とパターナリズム
日本ではアドバンスケアプランニングや人生会議として、人権尊重からも自律性が大切だと叫ばれるようになりました。その自律性とパターナリズムについてちょっと脱線してみます。
つい近年までは医療者側が専門職として、与益・無危害の医療倫理的な考えのもと、主治医がベストとして判断された選択が一番良いとされていました。それをパターナリズム(Paternalism)といい、権力や能力を持つ者が、弱い立場にある者の利益や幸福のためとして、その意思を無視して干渉や介入を行うことを指します。日本語では「父権主義」や「温情主義」、とも訳されることがあります。
1970年代初頭に医療社会学者のエリオット・フリードソンによって、「医者と患者の権力関係」がパターナリズムであると指摘されました。著書の『医療と専門家支配』では、医療専門職を専門職のプロトタイプ(型)としており、専門職が社会的支配力をいかに獲得し、患者に影響を及ぼしてきたかなどが言及されています。この医療現場におけるパターナリズムは「医療父権主義」「医療パターナリズム」と呼ばれています。
日本の医療におけるパターナリズムの流れ
1. 戦後から高度経済成長期まで:医師主導のパターナリズム
この時期、日本の医療は「医師中心」の体制が強く、患者は医師の判断に従うことが一般的でした。専門知識への信頼や畏敬が背景にあり、患者の意見が反映されることはほとんどありませんでした。例えば、乳がん治療では医師が再発リスクを重視し、乳房全摘手術を一方的に選択するケースが多く見られました。一方で欧米では、患者の希望に基づき乳房温存手術が普及していました。
2. 1980年代以降:自己決定権の台頭
1980年代から1990年代にかけて、患者の「自己決定権」が注目されるようになりました。これは、インフォームド・コンセント(IC)の普及とともに進展しました。 医師は患者に治療内容を説明し、患者が選択するという形態が徐々に取り入れられました。しかし、この時期でもまだ医師主導の傾向は残っていました。
3. 現代:共同意思決定への移行
現在では、「共同意思決定(Shared Decision Making)」が標準的なアプローチとして広まりつつあります。この手法では、患者本人だけでなく家族や医療従事者も情報を共有しながら最善の治療方針を模索します。特に高齢化社会を背景に、認知症など意思疎通が困難な患者への対応としても重要視されています。
日本でパターナリズムが長く続いた背景には、専門知識への盲目的な信頼や「お任せ文化」がありました。 一方で、自己決定権の尊重が進む中で、患者が意思決定できない場合や情報格差による不平等など、新たな課題も浮上しています。現場の肌感としては、医療の対象が全ての年齢層に対して施される特徴からも、受け手側の準備ができていない方々もいる土壌に、医療のスタンダードを平均して推し進められている印象を受けます。もちろん受け手は混乱したり、それもパターナリズムの一端として変化を丸呑みしている様子もあります。相互理解がなければ、本当の意味の共同意思決定とは言えませんよね。医療が病院から在宅へ移行する際にとても多く感じますが、それぞれの物語の背景があることも十分にわかっているので、全てありのままを受け止めることを繰り返すことで、振り返れば道ができていることを願います。
私ができることは、その覚悟ですね。
意思決定支援:緩和的パターナリズム
『X月X日 主治医より本人家族に病状についてICされておりDNARの了解をとっておりBSCと説明されています。』
医療専門職以外はなんのこっちゃですが、よくご依頼いただくときに良く目にする文言です。
解説すると、『X月X日 主治医より本人家族に病状について説明をされており理解を得ています。(末期癌などの場合)心停止ないし呼吸停止した際に心配蘇生を行わないことに同意しており、今後の治療はがんに対する抗がん剤などの積極的な治療は行わず、症状などを和らげる治療に徹することを説明されています。』という意味です。
文言を読み解くとセンシティブで重い重ーい話です。本人家族にとって、医師の話をストレートに聞けない心情であってもおかしくないですよね。病状が厳しくなってきていることを受けとめられずにいる状況で、心肺停止したらどうしますか?なんて考えたくもないでしょう。今日まで心の支えとして頑張ってきた治療が行えなくなったことを否認したくなるのは、防衛機制として当然です。しかも余命時間もかなり限られてきて、療養や看取りをどこでどう過ごすのか意思決定して下さいなんて、能力があろうとなかろうと、わかりません、わかりたくありませんって心情に医療者はどれだけ自分の心を砕けるでしょうか。ケースワーカは板挟みになるでしょうね、在院日数も限られていて、受け止めきれていないのをわかりつつも話を進めなくてはいけない立場ですから。
終末期の意思決定は医療者でも難しい選択のオンパレードな状況な上に、たった1回しか機会がなくて取り返しがつかないような困難な意識決定をしないといけないのは、自律といっても家族や本人にはあまりにも荷が重すぎるという考えのもと、緩和的パターナリズムという優しさが終末期には必要であるいう論点があります。
本人にも家族にも自律した選択はもちろん大切だという前提のもと、その選択によって責任を背負わせることになることを携わる者は知るべきことです。特に家族が後から後悔が強まらないように「責任を引き受ける」ことを意識していたと森田先生の見解がありました。
4人に1人がガンに罹患するというデータがあるように、ガン治療も日進月歩しています。もちろん治癒することが一番ですが、ステージ4の延命のための治療薬もある時代ですから、選択肢があることは心の支えになります。しかし、いつか治療が難しくなるときがやってきたときに、「ギリギリまで治療できてよかったね」と、坂から転げ落ちるように体調が悪くなることを受け入れることができるでしょうか。「こんなに早く旅立ちのときが来るなんて」最近本当に多く聞く言葉です。
そんな中受け皿である私たちにできることは何でしょうか、問い続けます。
心の恒常性を保とうとする自然なの働きがあることや、それぞれの人生の物語やパーソナリティを学ぶことは、意思決定支援においても自分の中の捉え方が変わるものだと率直に感じます。逆に全く知らずに、目の前の事実だけを鵜呑みにしプロセスありきで良しと横行されてしまうことへの危惧も感じます。
意思決定支援:マイルドカツアゲ
自律の「自分で決める」が「自分で決めなければならない」に置き換わりやすいのも深いです。「悪に病状をデータや論理的に説明して今の病状はあまりにも悪いのだから、抗がん剤を続けると命がむしろ短くなるし、緩和ケアを受ける方が長生きするという研究データもありますがどうしますか?あなたの責任の上で決めてください」という説明は、患者中心と言えるのかはかなり怪しいものです。
そのスタイルについて内科医の名郷直樹医師は次のように提言しています。
この状況は「今ここで俺に千円差し出せば許してやるが、出さなければぶん殴る。どちらに決めるかは、お前の責任において、お前が自分で決めろ。自分で決める以上その責任はお前にある」というカツアゲの場面と本質的にどこが違うのかはっきりしない。
緩和ケア÷精神医学 森田達也 明智龍男 医学書院P212-213
カツアゲですか…的を得すぎてぐうの音も出ません。実はそれに近いことがよしとされていることに気がつかないことが多く感じます。終末期に関わるナースには是非知ってもらいたいです。
【終末期に横行するマイルドカツアゲ】
入院中で治療が難しくなった場面で「今後をどこで過ごしますか?もう治療がないんだったら家で過ごすのがいいよ、是非そうしたら?」
よく耳にする話で、何が問題なの?ってポカンのされる人もいるのでは?
ではそれをカツアゲ風に解釈すると、「このまま入院していても状態が悪化すると思われるので、状態が悪化する前に家に帰った方がよい。家に帰らなくてもいいが、その場合は帰る時期を逸するよ。」という意味が含まれているということです。
治療することができないのなら、せめてもの想いとして、良かれとして、『退院して家族と少しでも時間を過ごした方がいい』という看護師自身の価値観を押し付けているとも言えます。もしかしたら、逃避状況で時間がないことは考えたくない心理かもしれないのです。
私の経験からも、退院の目処がつき、在宅療養の準備が始まったところ、病棟で病室に来るナース、来るナースが家に帰れてよかったねを連発されたことで、予後がないことを押し付けられているように感じてしまい気持ちが落ち込み、退院が延期になってしまった方がいらっしゃいました。少し気持ちが落ち着いてからの退院となりましたが、残念ながら数日で旅立たれてしました。かけがえのない時間ですから、やり直しもききません。きっとマイルドカツアゲにさえも気がついていないでしょうね。
【家族に対するマイルドカツアゲ】
食べられなくなった時の点滴をどうするか?興奮性のせん妄や身の置き所がないくらいの倦怠感の際のセデーションをどうするのか?など選択を求められることは、正解がわからず決めかねてしまうのは当然のことですね。選択したことや、しなかったことで、家族が責任を背負うには負担が多すぎます。それこそ、その人にとっての軸を家族と専門職で一緒に考えながらの緩和的パターナリズムが必要かもしれません。
心に余裕がないのがわかっていながらも意思決定していかないといけない局面はあります。結果よりもプロセスが大事だと思っていますが、パニックになっている相手に冷静に決めてくださいなんて、無理難題を押し付けているだけで尊厳とは程遠いものです。行き先を決めてもらって線路をひくことだけに支援者の心がとらわれてしまわないように、望んでいない行き先に向かわされる本人・家族が日々のかけがのない生活を歩んでいくことで、たどり着くまでの想い出の日常を大切にできたらと願いながら、関わり続けることだけは、私にもできることかなあと思います。
誰のための意思決定支援なのか、今まで学んできた心理的防衛機制が潜んでいないか、自分自身が投影してしまっていないか、メタ認知していくには知識も経験も必要なのかもしれませんね。
精神医学からみた病状理解とACP
うまく伝わらない理由
病状を伝えているのにうまく伝わらないのはどうしてなのかしら?
それぞれの角度で解釈すると、一般的な臨床では『理解が悪い』、精神医学では『否認』、緩和ケアでは『希望』となります。きっと思い当たる経験があるのではないでしょうか。主治医から病状説明され、在宅でかけがえのない日々をどう過ごしましょうかという文脈に『なれない』理由があります。研究論文からも進行肺がんの患者さんの21%が、がんが治癒困難であることを理解していなかったと報告されています。21%って想像よりも上の数字です、5人にひとりですから。
どんな心理的な作用か明智先生の解説が続きます。『否認』は以前の解説した心理的防衛機制のひとつですが、現在は疾患な概念というよりも意識的にも無意識的にも日常生活において観察されるストレスへの一種の対処様式(コーピング)として用いられることが多いようです。
否認の3段階
ここでの否認の定義は、苦痛を伴う現実状況から自分自身の精神的な安定を守ろうとする働きとして、現状を直視することを避ける対処のことを言います。
レベル3:疾患の存在そのものを認めない(まれ)ー真の否認
例)診断名をがんと説明されてもそれを認めない
レベル2:症状と疾患の関連を認めない(比較的多い)
例)痛みがあっても受診しない
レベル1:疾患の致死性を認めない(多い)
例)奇跡を望む
死にゆく患者の心理過程としてよく知られているものの一つに、キューブラー・ロスの5段階モデルはご存知でしょう。否認ー怒りー取引ー抑うつー受容という5ステップをたどっていくと提唱されていますが、ここにも否認が現れます。
よく出会う臨床では「麻薬を使うほど自分の状態は悪くないとオピオイド服用を拒否する」「奇跡が起こることを望み続ける」など表現されることが多いです。ですから何も特別な病的な心理状態ではなく、無意識でされている対処法でもあり、むしろ健康的で人の心理としては自然なものです。まさに否認というよりは「希望」と表現される方がしっくりきます。
積極的な待ちの姿勢
自然なものだからといって見守ることで大丈夫な否認とそうでない否認(明かに不都合と思われる状況)があることがとても難しいのです。まずは否認そのものよりも、否認の後ろに隠れている心情(心理的防衛機制がないか)について理解し、いや理解しようと努力し、です😅
否認か希望かもと気づくと同時に、きっとつらいんだろうなと思いながら、過敏に反応することよりも、少し見守ることが大切かもしれません。
もう一方の方が難しい局面かといえる、『そうでない否認、非適応な場合』はというのは、否認されることで、たとえば効果的な治療を受けれらなかったり、逆に害をもたらす不適切な治療につながることや、生活の質を保つ上で著しい妨げになっている場合のことをそう表現されています。『穏やかで注意深い直面化など治療介入が考慮されることもある』それには、「Hope for the best,perpare for the worst」現状に対して最も良い転帰がもたらせられることを望むことに理解を示しつつ、一方では万が一に備えておきませんかという介入で、少しずつ現状の直面化を促す方法のコミュニケーション技術が有効と言われています。
まるでアレルギー疾患の感化療法のようですね、以前の太陽と死の名言から拝借すると、少しずつ太陽の光に慣れさせていくようなそんな感覚でしょうか。
いわゆるACP(アドバンス・ケア・プランニング)には賛否両論があります。終末期医療においては、患者さんの生活の質(QOL)を最大限に維持することに加え、いわば患者さんにとっての「望ましい死(QODクオリティオブデス)」というべきものの体現へと目標が移行することが多いです。これにはそれぞれの個別的な価値観の理解ぬきでは治療目標の設定とは言えません。特に文化的な背景から望ましい最期の要素は個人差が大きいのは当然で、「残された時間を知り準備をする」のも「死を意識しない」のもそれぞれの個別性の価値観があります。おしなべてすべからく、じゃあ人生会議でとテーブルに座わらされても、一体誰のための会議となっちゃいませんかね。
そして人間は加齢とともに楽観的になっていく性質があります。そういう特質が醸成されながら進化してきました。その自然な流れをせき止めて、そろそろ人生の終わりに近づいてきたからといって突然「現実をしっかりみなさい」という方向転換は難しいだろうなというのはすごく納得できます。
臨床的には、否認(希望)そのものは、それによって「自分が死ぬという恐怖」や「大切な人を失う哀しみ」からこころを守っているわけですから、本来は適応的で自然なものです。今は鉄壁の否認をしていても、現実と向き合わないといけない時期もあります。例えば衰弱が進んでトイレに行けなくなるなど、いやおうもなく刻々と身体の変化を実感することで、「もしもう時間がないのなら…」と気持ちがポロッと湧き出ることがあります。そういう機会を逃さないように『積極的な待ちの姿勢』が必要と森田先生は提案されています。
このポロッとや積極的な待ちの姿勢の話は思い当たることがあります。その時を逃さない準備は、私も意図的ではなくても持ち続けているスタンスで、反射的に発動してしまっているかもしれませんね。
名著を読み終えて
私は個人的に緩和ケアの森田先生のファンで、今までもバイブル的な著書に助けられてきました。先生のお人柄なのでしょうか、くすぐられるんですよ。特にタイトルがやばい。今回だって、速攻ポチりました。森田先生の著書は痒いところに手が届く本なのです。
私が看護師の若葉マークが外れた頃もう30年前になりますが、やっとインフォームドコンセントという言葉があちこちで聞かれるようになった頃です。私の配属先の血液内科は不治の病が多く、パターナリズムが患者さんへの最大の優しさだとされていた時代です。全力を尽くす治療が患者さんの益とされていましたので、危篤状態であっても亡くなる日の朝だって抗がん剤の点滴がベッドサイドにぶら下がっているのは当たり前で、それこそ『全力の治療を尽くしましたが、残念ですが力及ばずご逝去されました。』主治医のそんなお悔やみの言葉をよく耳にしていましたが、私にとっては違和感でした。患者さんの口から『家に帰りたい』という言葉を聞いていたからです。そこから私の出産子育てを経て、社会復帰の際に、『お家』側の世界で生きてみたくなり、これまで違和感を別の角度で見られるようになりました。
ご縁と出会いから、たくさんの学びと幸せをいただいているのは、今も進行形です。その学びは意識的にも無意識的にも私の中に確実に積み重なっているですが、推し量ることは難しいものです。私の中に宝物として持っている自覚はありつつも、突然輝きだす時に宝物としての姿が見えることがあります。この著書がまさに私の中に光を当ててくれ、宝物の存在を教えてくれました。改めて、これまでの出会いに感謝し、これからの出会いに貢献できたらとワクワクします。
本著を推し活のようにポチり、期待以上の内容にのけぞり萌えまくり、妹たちにおやすみ前の絵本のように語りたくなった訳です。それでも満足できずに衝動にかられ、末の妹に一読するように指令を出し、巻き込み巻き込み、笑。読み終わって気がつきましたが、きっとこの森田先生と明智先生とのダイヤローグが羨ましかったのでしょう、この本を肴にして、立場の違う四女と対話を楽しみたかったんだと。四女も答えるべく本に付箋を貼りまくりで読んでくれました。今回のシリーズは四女との対話へのまとめとして私的なフィルター加工での仕上がりとなっております。テーマが深いので、一度に語り尽くせないものですが、実際の姉妹での対話は楽しいひとときでした。世界は広がります。奇跡のような幸せです。
なお、今回は専門分野の深掘りになってしまい、professional Ver.とさせていただきました。全く話が見えない方は大変申し訳ありませんでした、どうぞ読み飛ばしてください。中身はともかく、普段の私たちの裏側の顔や心の中を垣間見て下さると幸いです。表向きは平然を装っているはずですが、心の中では必死にバネを巻きつつ(笑)、満身創痍で何かお役に立てないかと考える日々であることをお伝えできたのなら何も言うことはありません。
「理」の字は宝石の模様の筋目という意味があるので、「心理」とは心の筋目と解釈できるでしょう。心の筋目に愛でるように手をあて、生まれる科学反応を期待していけたらと思います。出会いをいただけること自体が私にとって何よりのことです。それは日常のあちこちにきらめいている宝石のようなもので、私が留めておくだけではもったいないです。心動かされる日々はこれからも誰かの支えや癒し、そして人生の彩りの種として、いろんな形でお届けできたらと願うばかりです。
あー、学ぶことは楽しいですね。
著者紹介:森田達也・明智龍男
森田達也
聖隷三方原病院 副院長/緩和支持治療科
1992年京都大学医学部卒業。1994年聖隷三方原病院ホスピス科、2005年緩和支持治療科部長、2014年副院長。緩和治療の専門医として、「時期を問わない」緩和ケアに携わる。困っている人がいるのに誰もやっていない領域、何をどうしたらいいのかさっぱりわからない領域が好き。人間のどうしようもなさが愛おしい。
主な著書に『臨床現場のもやもやを解きほぐす 緩和ケア×生命倫理×社会学』『死亡直前と看取りのエビデンス 第2版』『エビデンスからわかる 患者と家族に届く緩和ケア』『緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス ああいうこととこういうはなぜ違うのか?』(全て共著、医学書院)、『緩和ケアで鍵となる研究 先を見通す背景読みスキル』(青海社)『緩和治療薬の考え方、使い方ver.3』(共著、中外医学社)、他
明智龍男
名古屋市立大学大学院医学研究科精神・認知・行動医学分野 教授
名古屋市立大学病院こころの医療センター センター長
名古屋市立大学病院緩和ケアセンター センター長
1991年広島大学医学部卒業。国立呉病院・中国地方がんセンター、広島市民病院精神科等を経て、1995年から国立がんセンター東病院・中央病院精神科および精神腫瘍学研究部。
2004年名古屋市立大学大学院医学研究科 精神・認知・行動医学分野助教授、2009年名古屋市立大学病院緩和ケア部部長(併任)を経て、2011年より現職。
迷いながらも緩和医療に従事し続けている。文学も音楽も映画も医療も人生も「悲しみ」に本質があると思ってしまう、ちょっとペシミスティックな精神医。
主な著書に『がんとこころのケア』(NHK出版)、『こころとからだにチームでのぞむ慢性疼痛ケースブック』(共編・共著、医学書院)、『死にゆく患者と、どう話すか』(監修、医学書院)、『「こころ」や「精神」を医学する精神医学とは何か?ー精神科医になることを迷っている人、なったばかりの人、興味がある人のために』(編・共著、中外医学社)、他。
緩和ケア÷精神医学 共著:森田達也 明智龍男 医学書院 書籍内プロフィール抜粋
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。