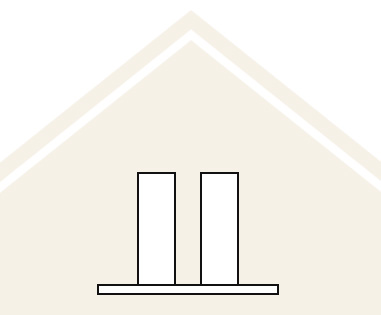おうちナースな7DAYS【オハナな管理人日誌weekly】2025.1.8〜1.14
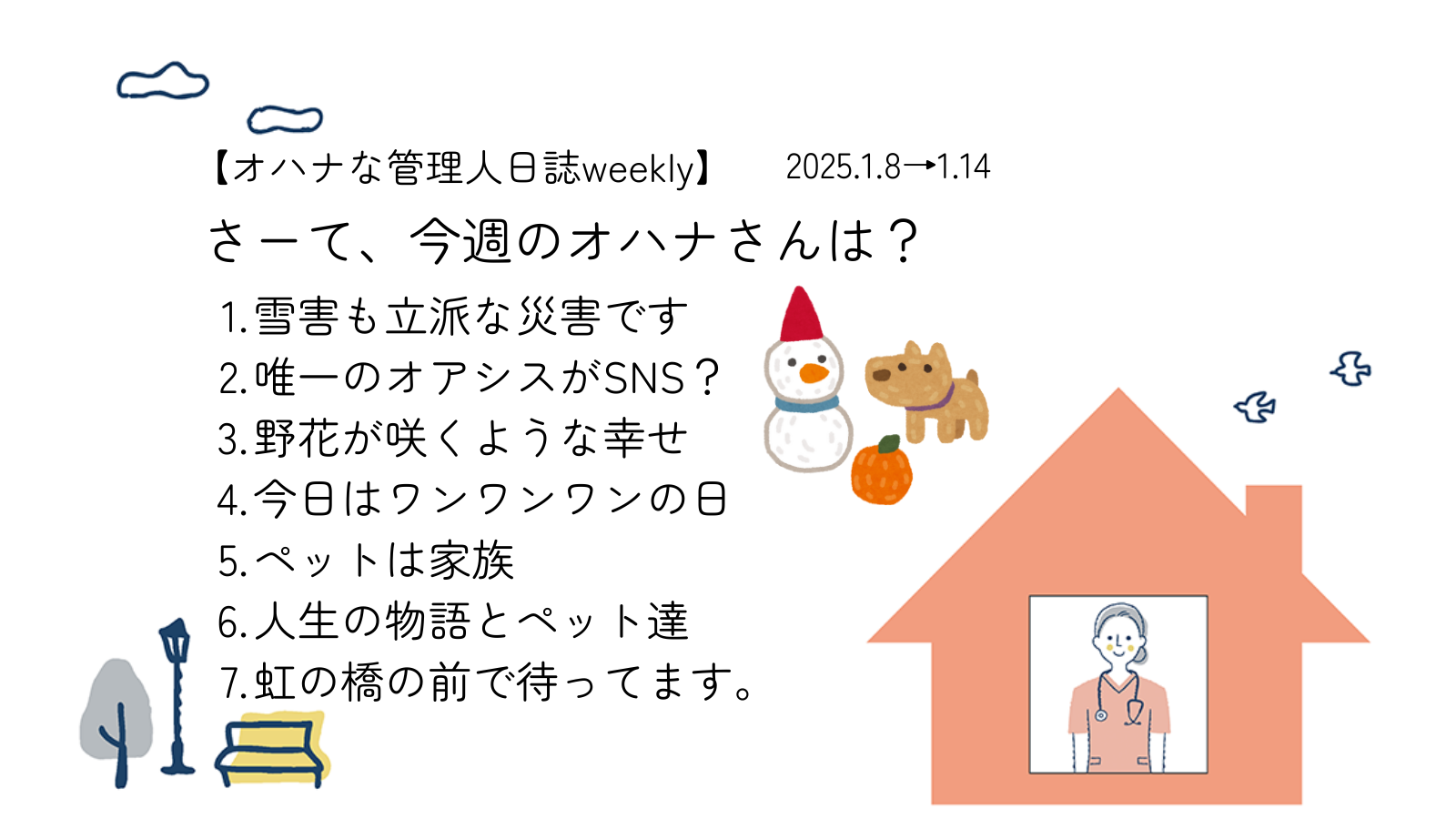
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
雪害も立派な災害です
《オハナな管理人日誌 2025.1.8》
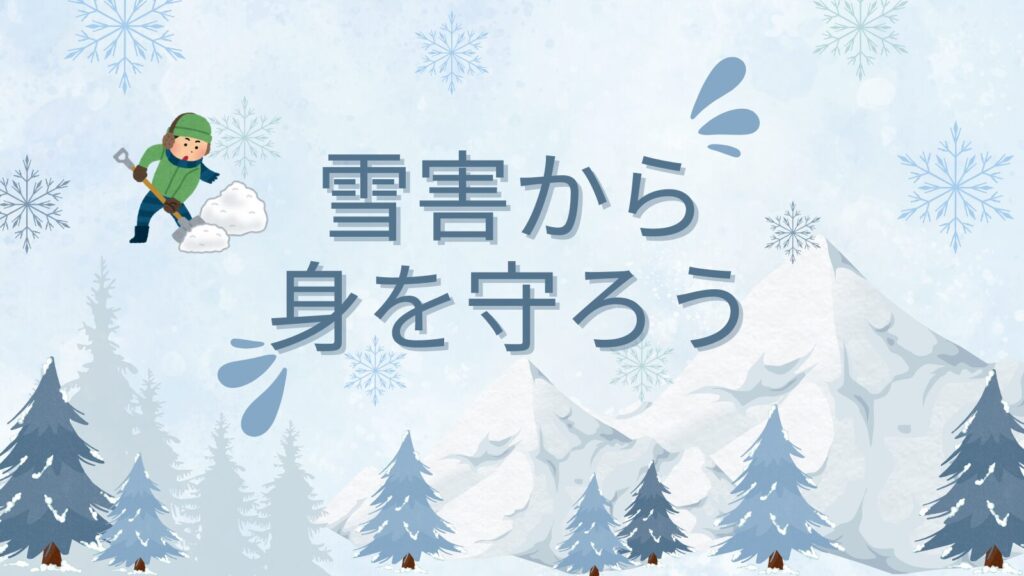
「今季一番の寒波」が襲来。寒気のピークは9日~10日。西日本では1月としては過去トップ3に入るくらいの強いレベル。北陸など日本海側では、10日までの3日間に新たに2メートル近い雪が降り、立往生のリスク大。普段、雪の降らない東海や西日本の太平洋側でも積雪の可能性があるため、路面の凍結などに注意が必要です!
2024年4月より訪問看護事業所において、BCP(業務継続計画)策定が義務づけとなりました。オールハザードアプローチBCPと横文字が並ぶと言葉を覚えるだけでも一苦労なお年頃でありますが、要はあらゆる災害や感染症が発生しても迅速に対応できる準備をしておきなさいね。ということです。去年はその準備で様々なセミナーでの勉強会がありました。私たちの拠点である旭川周辺のお年寄りは、昔から地盤が低いところの水害がある程度で大きな地震もないし、旭川はいいところだなぁ。ただ雪だけは降るのは仕方ないよなぁと口々に言います。
そうそう、忘れもしない2013年1月3日仕事始めの勤務の朝、深夜から朝方にかけて暴風雪が吹き荒れ、旭川市内全域で交通麻痺が起きました。除雪が間に合わずに車が動かせない人々が多数、バスも運休、幹線道路の真ん中を人が歩いて職場に向かっている姿もありました。平常な訪問看護どころではありません。玄関の扉も雪で覆われて開かないとSOSがあり、スコップを担ぎながら歩いて救助に行った経験がありました。雪には割と強い都市ですので、さすがに夕方までには大通りは車が通れるくらいに回復できたのと、1月3日のことだったので一般的な会社や学校もお正月休みだったのも良かったのかもしれませんね。大変でしたが、深刻な?被害はなかったように記憶してます。
この度の警報に伴って、久しぶりに耳にした言葉ですね、不要不急の外出は避けるようにと。過去にもホワイトアウトやスタックで、雪が降り積もる中、車が立ち往生してしまって、何日も渋滞が続いたり、排気ガスの一酸化中毒で悲しい結末もありましたね。万が一立ち往生してしまった時には、命を守る行動も大切です。
🚗車が立ち往生した場合、命を守るために以下の対策を取ることがとても重要です👍
1. 安全確保:ハザードランプを点灯し、可能であれば三角停止板を設置して後続車に注意を促します。後続車が視界が悪く、多重事故となりやすいので本当に気をつけて!可能な場合は、近くの安全な施設へ移動します。
2. 車内環境の管理:避難できる場所がない場合は、なるべくエンジンを切り、防寒具を着用します。マフラー周りの雪を定期的に除雪し、排気ガスによる一酸化炭素中毒を防ぎます。防寒具がなく暖がないことでの低体温症も重篤な不調です。
3. 体調管理: エコノミークラス症候群を予防するため、定期的に体を動かし、足の指を動かしたり、足首を回したり、ストレッチをしましょう。水分補給を心がけたいところですが、トイレ問題も待ったなしです。
4. 救助要請:ロードサービスに連絡し、救助を求めます。 体調が悪化した場合は、迷わず救助を要請します。道路が塞がってしまうと長時間になる場合も想定されますね。
5. 備えの重要性:燃料は常に満タンを心がけます。
非常用品(防寒具、スコップ、水、食料、簡易トイレなど)を車に積んでおきます。長時間の待機に備えて、毛布やカイロ、キャンプ用の寝袋、紙おむつなど代替できるものなど、備えあればです。
やっぱり出かけなければ良かったと後悔しないように避けれることは避ける選択も大切に思います。
嵐が何事もなかったように過ぎ去ることを願いつつ、被災した時の鉄則のひとつに『自分の命は自分で守る』そこから次の命の救助につながります。こんな海の藻屑のような記事ですが、イメトレだけであっても、万が一のお役に立てたらと長々と綴ってしまいました。
唯一のオアシスがSNS?
《オハナな管理人日誌 2025.1.9》
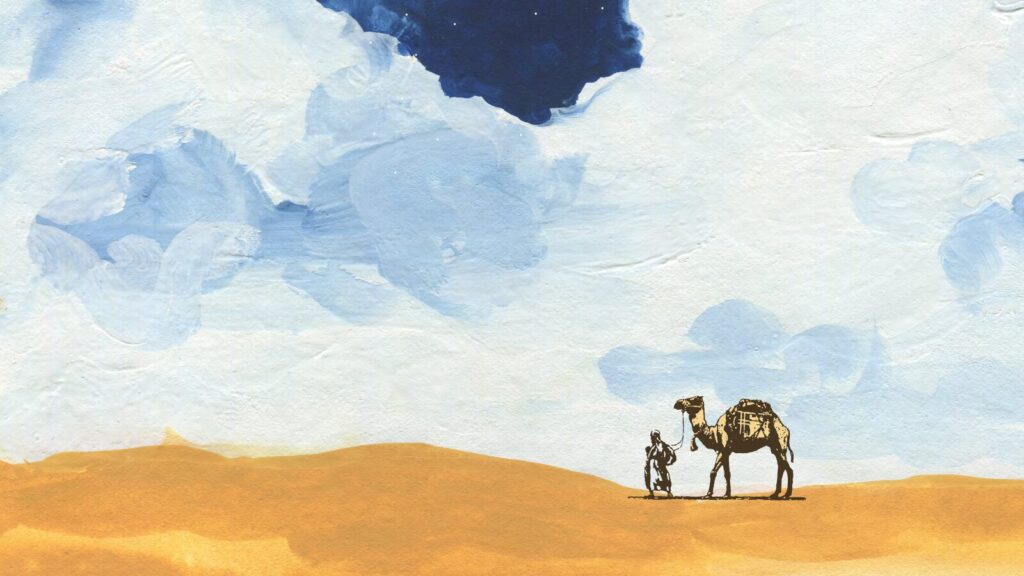
閉塞感ばかりの世の中の唯一のオアシスがSNS?
メディアに出ているイエールの大学の成田教授が年末にポストされた言葉が気になりました。
これからの日本人は結婚もせず子供も持たず、一人で金もなく中高年に突入する。そうすれば鬱になる。そこで現れるオアシスがX。陰謀論を叫び、政治に吠え、炎上した人を叩いていいねというお薬をもらう。Xはもう心療内科 2024/12/25
5万人以上がいいねしているポスト。SNSネイティブでない私の世代は、SNSはLINE程度で他は距離を置いている(もしくは利便性がない?)という方も少なくないはずなので、成田教授の言わんとしていることも理解できなくても当たり前です。こうやって私が少しSNSを覗くようになって常に感じることは、鬱積した気持ちを抱えている方が世の中にはたくさんいらっしゃるのだなあと驚きました。
職業病的な視点で、癌の闘病に関するリアルな思いが吐露されているのをたくさん目にします。ちょっと的外れな話をしてしまうと、リアルな相談窓口もあるんですよ。
がんの心のケアを提供する窓口
【 がん相談支援センター】全国のがん診療連携拠点病院などに設置されており、がんについて詳しい看護師やソーシャルワーカーが無料・匿名で相談に応じています。
【腫瘍精神科】がん研有明病院などの医療機関では、腫瘍精神科医と公認心理師が患者さんやご家族の心のケアを行っています。
【 がんサポートコミュニティー】臨床心理士や社会福祉士、看護師などの専門家による心理社会的なサポートを提供しています。
【 マギーズ東京】がん患者と支援者のために開設された施設で、心理的サポートを提供しています。
【がん相談ホットライン】日本対がん協会が運営する電話相談窓口で、看護師や社会福祉士などの資格を持つ相談員が対応しています。
電話番号:03-3541-7830
相談受付:毎日(年末年始を除く) 10~13時、15~18時
(※時間は変更になるあり、ホームページにて確認要)
●匿名で構いません
●秘密は厳守いたします
●相談時間は概ね20分
●相談料は無料(通話料は相談者のご負担になります)
わかってますよ。リアルな相談口を求めていない方もいるでしょうね。無機質に吐露することに価値があるんだなあと、流れてくるポストを眺めているとそう思います。たくさんのいいねが支えになっても、心ないコメントを浴びせられていることも見かけますから、そのリスクを背負うには辛すぎませんかね。SNSの距離感を錯覚して追い詰められ悲しい結末…、著名人でもありましたよね。
辛さはバーチャルではなく、リアルな次元に存在するもの。投影された影をいくら整えても、本体が癒されなければ何も得られないでしょう。わざと薄っぺらな関係に目を瞑り、癒されていると思い込みたいそんな心持ちかしら…。
野花が咲くような幸せ
《オハナな管理人日誌 2025.1.10》
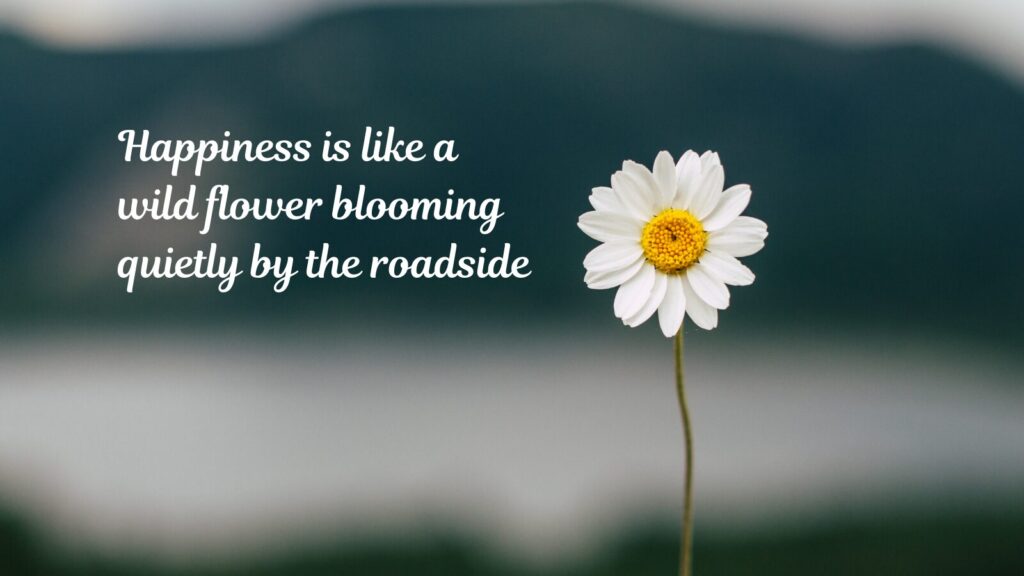
しあわせは道端にひっそりと咲いている野花のようなもの
回ご縁をいただいた看護学生さんに余命1年と宣告されたらどんな気持ちが浮かぶか?と質問を投げかけてみました。私が学生の時は、死や人生の最期が自分にやってくることなんて他人事だったなあと思い返しながら…。
それぞれがその方なりに余命に向き合って回答してくださいました。絶望や不信や不安、悲しみ…いわゆるショック状態ですね、当然ですよね。そして予期悲嘆との取り引きとして、後悔ない1年にするための行動、『やりたいことを全部やりたい』これが一番多かった回答でした。家族や友人や大切な人への関わりも目立ちましたので、温かい育みの中で育った方も多いのだなあと、これは単純にホッとしました。まあ母数がかなり限局してますから、そんなケースだったというレベルです。
余命が限られた方々に教えられたことは、例え時間が限られていても豊に生きることは可能で、肉体的に難しくなっても心は豊かさを保てる鍵があるということです。その教えは余命が遠いところに感じている者たちにおいても、人生を豊にする幸せを感じながら過ごせるエッセンスと含んでいます。その幸せは道端にひっそりと咲いている野花のようなもので、時間に追われ乗り物で移動し前だけ向いていると足元の幸せに気がつきにくいのです。だからこそ、「もしあと1年で人生が終わるとしたら?」の著者小澤先生は、自分とって本当に大切なことに気がつくことであり、苦しみや困難に向き合う力、人と支え合い助け合う力、苦しんでいる人を笑顔にする技術を育むことにもつながると結んでいます。
今日はワンワンワンの日
《オハナな管理人日誌 2025.1.11》
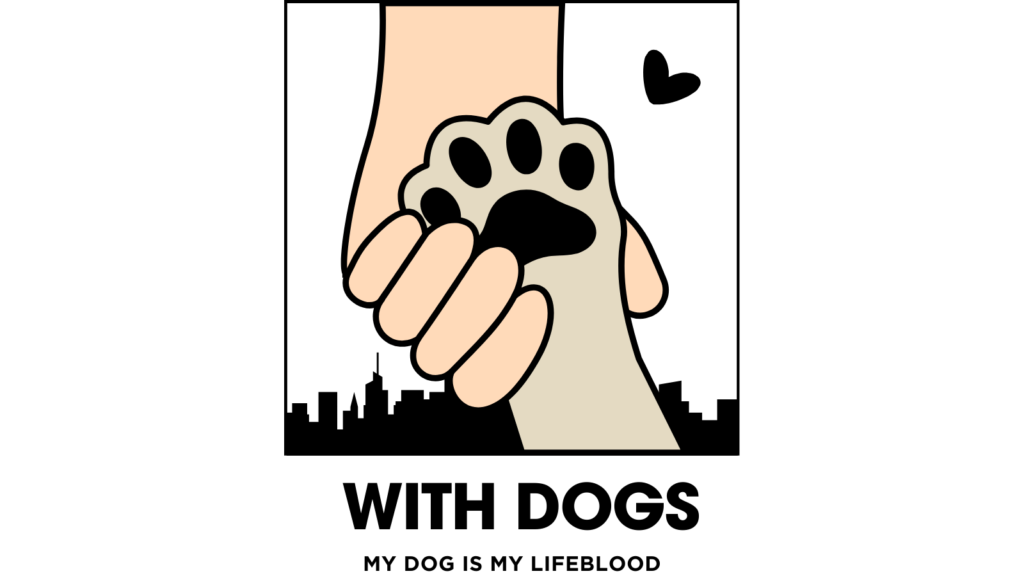
愛犬の存在が生きる糧
愛犬家、愛猫家、愛鳥家、愛魚家、愛亀家、愛鼠家、愛兎家、愛蛇家、愛豚家、愛羊家…etc、愛玩動物やペットという言葉では表現しきれませんね、訪問先でも家族として歓迎して動物たち。
好き嫌いが分かれる分野ですが、家族ケア支援として、まるごと捉える方が私は好きです。愛犬の存在が在宅療養生活で大きな役割を果たすことが往々としてあります。
私が子供の頃は(昭和の終わりの頃ですね)田舎の祖父の家の前には犬小屋があり鎖に繋がれて外で暮らしているのは珍しくありませんでした。エサも食卓の残り物といえば聞こえがいいですが、味噌汁ぶっかけご飯、ネコマンマでしたね。社会や生活様式が変化してしまうと物事の捉えが変わり、ペットとの関係性が現代社会とかけ離れてしまっていることに気づきます。もちろんその時代においても、ペットを可愛がっていなかったわけではありませんが、ペットとの距離感が変化しています。その距離感の近さが私たちの人生においてのメリットとなり、デメリットにもなるわけです。少し掘り下げてみましょうね。
ペットは家族
《オハナな管理人日誌 2025.1.12》

健やかなる時も病める時もペットは家族
昔は『子はかすがい』と言われました。かすがいは材木と材木とをつなぎとめるために打ち込む、 両端の曲がった大きな釘のことで、子供に対する両親の愛情が仲の悪い夫婦のあいだをつなぎ止めると言う意味です。少し前から子供→ペットに代わっていることも多いでしょう。ペットがいるから自然と家族の会話が増えると言うのはわかりますよね、逆にいざこざの火種になることもあるでしょうね。
ペットとの暮らしメリット・デメリット
【メリット】
1. オキシトシンの分泌:ペットとの触れ合いや視線を合わせることで、脳内で幸せホルモンと呼ばれている「オキシトシン」という物質が分泌される。
▶︎ 精神の安定とリラックス効果
▶︎ストレスの緩和
▶︎他者への信頼感の増加
▶︎心拍数と血圧の安定
2. 身体活動の増加:特に犬の場合、散歩などの日常的な運動が習慣化する。
▶︎運動不足の解消→血圧や中性脂肪の改善、心臓病リスクの低下
3. 社会的交流の促進:ペットを介して他の人々とコミュニケーションを取る機会が増える。
▶︎孤独感の軽減
▶︎社会性の向上
▶︎発語量の増加によるストレス発散
4. 生活リズムの安定化:ペットの世話を通じて規則正しい生活習慣が形成され、これがストレス軽減につながる。
5. 自尊心と責任感の向上:ペットの世話をすることで、自発的な行動が促され、自尊心が高まる。これにより精神的な安定が得られ、ストレス耐性が向上する。
【デメリット】
1. 経済的負担が増加。餌代、日用品、医療費など、年間で犬は約36万円、猫は約16万円のコストがかかる。
2. 長期間家を空けられなくなる。
3. 掃除やお世話などペットのお世話に時間が必要となる。
4. 鳴き声が騒音問題になる可能性がある。
5. 睡眠や作業効率など、ペットがかまってくることでの生活スタイルの影響。
飼い主が健康で元気で責任を持って暮らせることが前提なのですが、長く過ごしているうちに困難になることも在宅療養での悩みになることがあります。
人生の物語とペット達
《オハナな管理人日誌 2025.1.13》
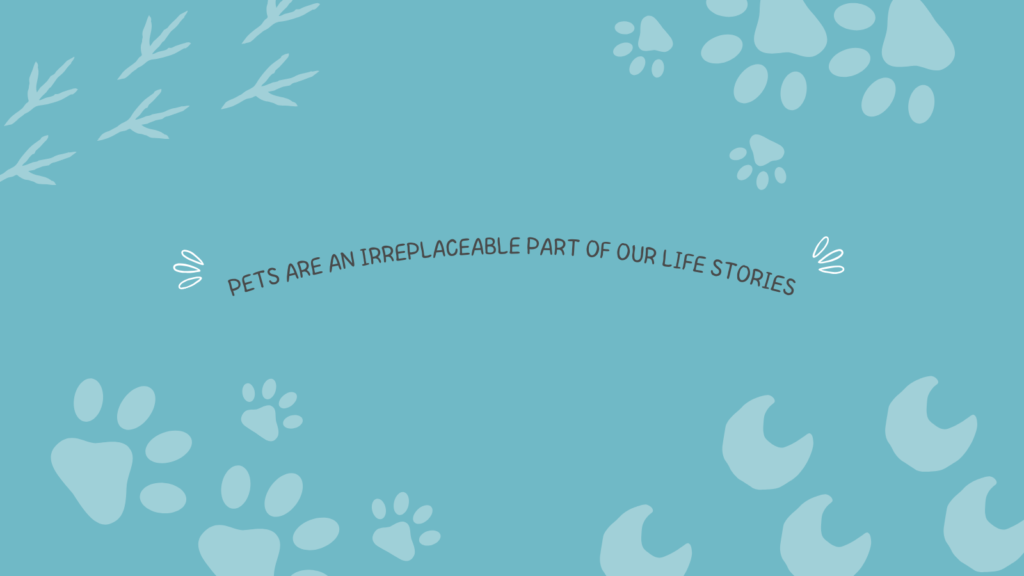
人生の物語にもかけがえのないペット達
訪問看護先で忘れられない存在のペットたちがいます。
訪問時間には正確に玄関先で到着を待ってくれる。どこにそんな正確な時計があるのかしら?気が済むまで歓迎してくれ、ケア中は大人しく居眠りタイム、でもそろそろ終わりの時間が近づくと知らせに来てくれるお利口犬。今でも遊びに行っても歓迎してくれるのはうれしいのだけれど、ご家族とお話しできないくらいのわちゃわちゃ。しまいにはずっしりと重さを感じながら抱っこしないと、話が進まないの。
要介護になってしまうと愛猫のお世話も大変な様子。それでもおひとりさまの支えになります。お世話は飼い主の身体が痛いだるいは考慮してくれません、愛猫のお世話が自然とリハビリに。玄関の引き戸をくり抜いて、自由な猫ちゃんたちが時には自慢げに見せびらかしにくわえてきた獲物にびっくり。
可愛い存在であっても、アレルギー持ちのスタッフはペットに癒されながらも症状との戦いは裏話ね。
おひとりさま末期癌の方は、以前飼っていた愛犬の存在がつらい療養生活の支えに。不安や辛さや愚痴をすべて心の中の愛犬に吐露され、病状が進行すると近く存在を感じていました。おそらくお迎えだったのでしょう。亡くなったペットがそばに来てくれるお迎え現象のような、せん妄はよく経験します。
老犬を看取ったあとのペットロス。喪失感を抱えながら日々過ごしているうちに、ご高齢の飼い主さんの老衰に拍車が。大切なペットとのお別れは辛さが長引くと、うつ状態の悪化やセルフネグレクトの原因に。おひとりさま生活では心配な状況を発見しにくいことも深刻な悩みのひとつです。
寝たきりの妻と小型犬そして夫。夫は脳梗塞で左半身が麻痺してしまったにも関わらず、懸命に愛妻と愛犬のお世話を。妻のケアの時はベッドに上がり見守り隊。しんどい夫の愚痴の聞き役。妻と間違って愛犬の名前で呼んだ夫のいい間違いの笑い話。夫と愛犬で妻を見送った後も、やはりお互いの存在が支えになりました。
今の愛犬が4代目。歴代の愛犬の位牌と写真を眺めながら暮らしています。夫と娘それぞれが先に旅立ってしまい、喪失した辛さで自暴自棄になりそうな心を4代目の愛犬がつなぎとめてくれています。愛犬のために、それが今の生ききる理由。
若いペットたちはイタズラ好き。バリケードを破ってぴょんぴょんジャンプして、うれしさ100%で向かってきます。好奇心の多い子は、訪問バックに頭を突っ込んで、面白いもの探し。血圧計のゴム球だけは勘弁して、商売上がったりよ。
好きな人もいれば、苦手もいますね。昔、野犬に噛まれたとか嫌いとか、私の弟も追っかけられたトラウマから苦手意識がありますね。その時は姉の私も一緒に公園の滑り台の上まで一旦逃げたあと、さっさと置き去りにして逃げ帰った…、まずい、そんな記憶が出てきちゃった。ごめん、弟。
虹の橋の前で待ってます。
《オハナな管理人日誌 2025.1.14》
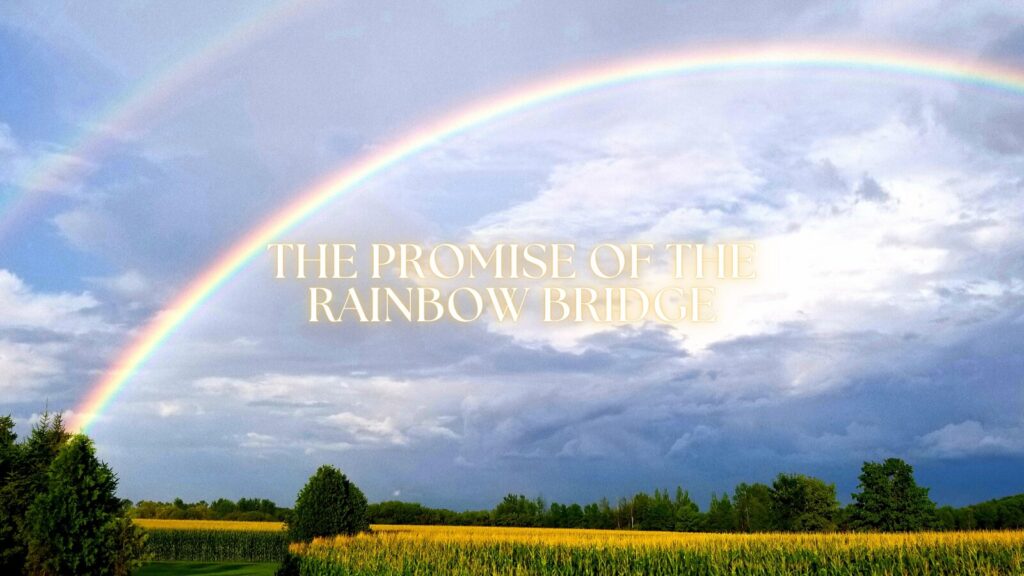
虹の橋というスコットランド10代の女の子の詩を聞いたことがあるでしょう。世界中のペットロスで苦しんでいる方への癒しの詩として広まりました。亡くなったペットは虹の橋を渡っていく。愛犬家を亡くした知人がそう話をしていました。実はお話が広がっていくうちに原作とは違う捉え方になっています。原作は、『虹の橋の前で飼い主と再会して、一緒に虹の橋を渡って天国に行く』というストーリーです。
虹の橋の物語の原作者は1959年エドナ・クライン・レキー、愛犬メジャーの死を悼み彼女は友人たちに自作の詩をタイプして配布しました。友人たちが感動し、コピーを拡散しましたが、作者の名前が記されていなかったため、匿名の作品として広まりました。1994年、アメリカの人気コラムで全文を無記名で掲載し、多くの読者に紹介されました。その後、インターネットの普及とともに世界中に広まりました。様々な言語に翻訳され、書籍やSNSなどの媒体で、絵や文字、歌などの形式で広く普及しています。原作の第1部に加え、第2部、第3部が別の作者によって創作され、三部作としても知られています。
「虹の橋」
天国のすぐこちら側に、虹の橋と呼ばれる場所があります。ここで誰かと特別に親しかった動物が亡くなると、そのペットは虹の橋へと向かいます。そこには、私たちの特別な友達のための牧場や丘があり、みんな一緒に走り回って遊ぶことができます。たくさんの食べ物や水、そして陽の光があり、私たちの友達は暖かく快適に過ごしています。
病気だった動物や年老いた動物たちは、健康で元気を取り戻し、怪我をしたり不自由だった動物たちは、再び完全で強くなります。それはまるで、過ぎ去った日々の夢の中で私たちが覚えているような姿です。動物たちは幸せで満足していますが、ただ一つ小さなことを除いては。それぞれが、とても特別な誰か、置いていかれた誰かを恋しく思っているのです。
みんな一緒に走り回って遊んでいますが、ある日、一匹が突然立ち止まり、遠くを見つめます。その輝く目は真剣で、興奮した体が震え始めます。突然、群れから飛び出し、緑の草原を越えて、どんどん速く走っていきます。あなたが見つけられたのです。そして、あなたと特別な友が遂に出会うと、二度と離れることのない喜びの再会で、しっかりと抱き合います。幸せなキスがあなたの顔に降り注ぎ、あなたの手は再び愛する頭を撫でます。そして、あなたは再びその信頼に満ちた目を見つめます。その目は長い間あなたの人生から離れていましたが、決して心から離れることはありませんでした。
そして、あなたたちは一緒に虹の橋を渡っていくのです…
虹の橋の物語は、特定の宗教観にとらわれない内容であったことが、世界中に広まった要因の一つと考えられています。この物語は60年以上ペットロスに苦しむ多くの人々の心を癒し、希望を与える役割を果たしています。ペットロスだけではなく、人生の大きな喪失感とグリーフ(悲嘆)との対峙として、この物語に大切なヒントが含まれています。この創造性が未来への希望と変わり、その希望が生きる支えになるからです。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。