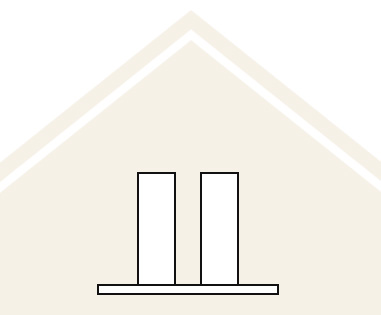しあわせ増配中!おうちナースな7DAYS【オハナな管理人日誌weekly】2024.12.25〜12.31
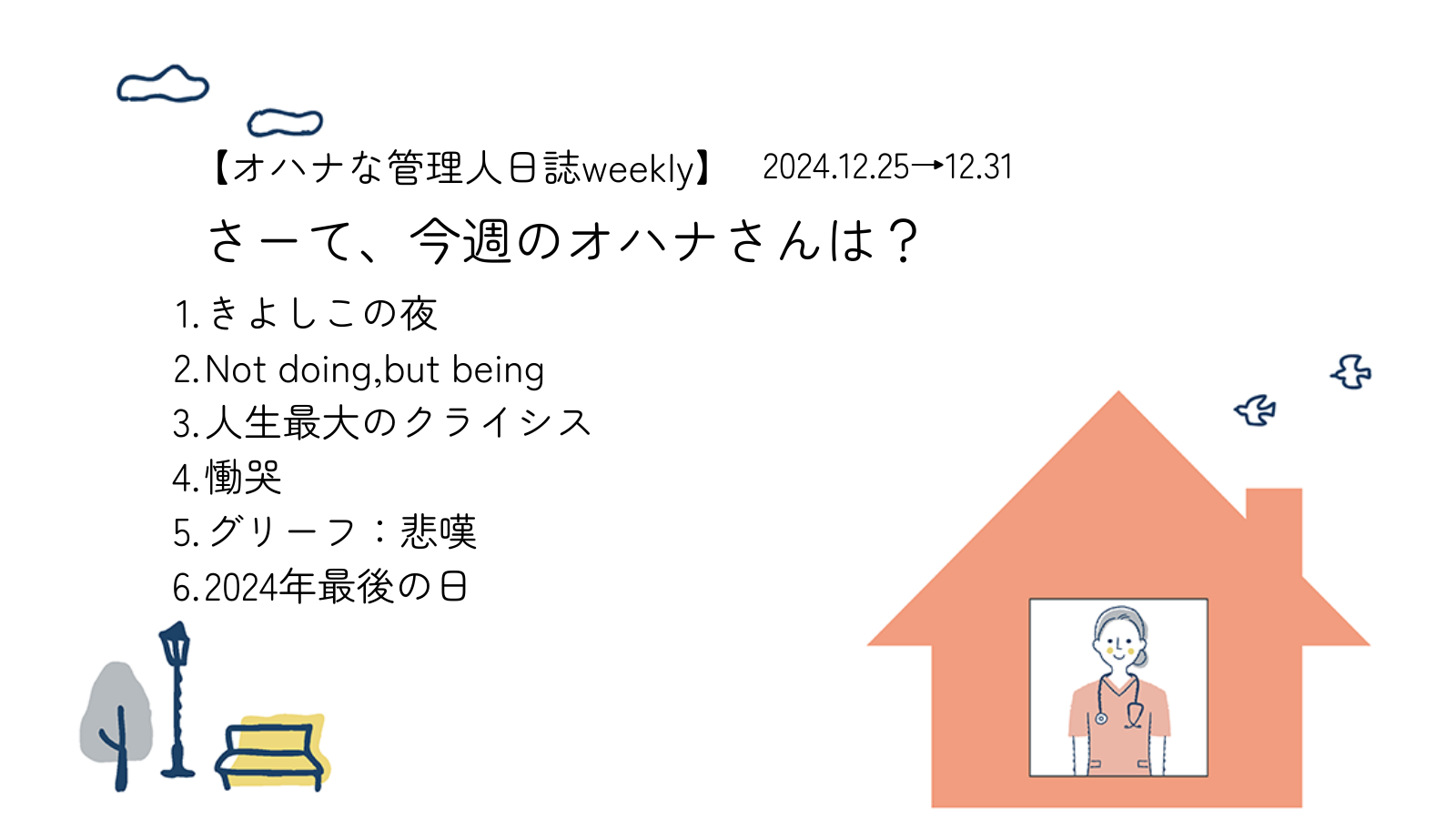
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
きよしこの夜
《オハナな管理人日誌 2024.12.25》
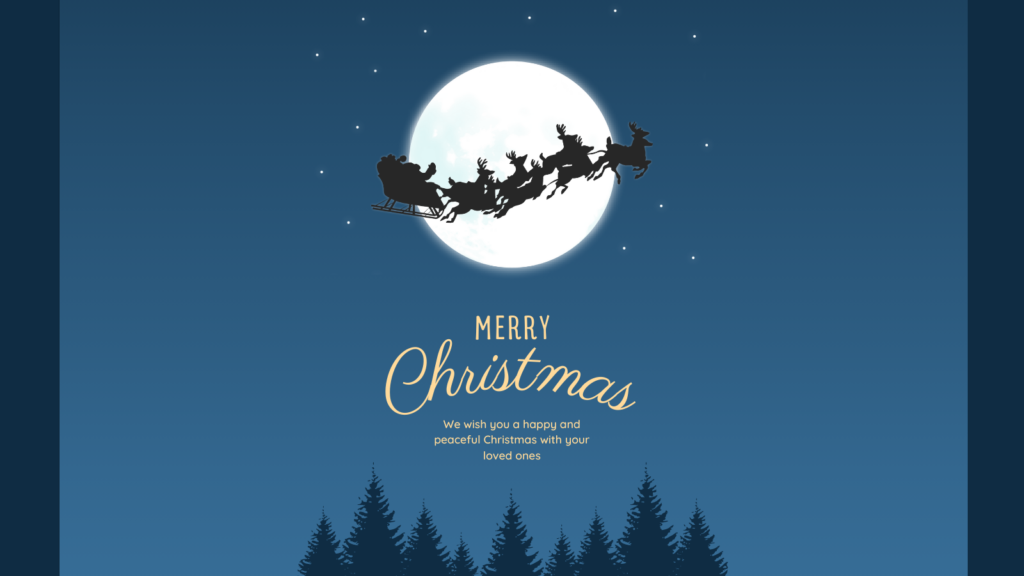
クリスマスイブの夜に、辛いお別れでした。
残される者にとっては、その日はできるだけ遠くあって欲しい。
旅立つタイミングは人それぞれで
残されるものの思いが叶わないこともあって
一層悲しみが増します。
行きどころのない辛さが口からあふれ、涙がたくさん流れました。
今はどんな言葉がけよりも、思う存分感情を出せることを大切に感じ
悲しみの心に手を当てるように、ご家族の背中をさすっていました。
きっと来年も、再来年もクリスマスが来るたびに思い出すでしょう。
それが彼からのプレゼントなのかもしれません。
かけがえのない大切なことを教えて下さいました。
Not doing, but being
《オハナな管理人日誌 2024.12.26》
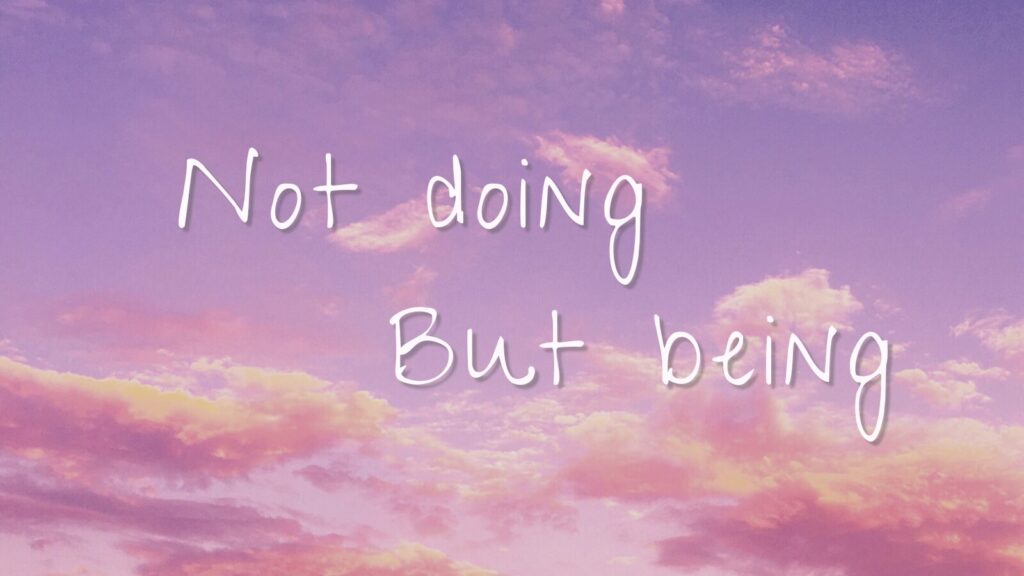
“Not doing, but being” は近代ホスピスの母と呼ばれるDame Cicely Saunders(シシリー・ソンダース)先生の言葉で、ホスピス緩和ケアの真髄を表現しています。
【存在の重要性】何かを「する」ことよりも、そこに「いる」ことの大切さ
【受動的姿勢】医療者が患者のそばに寄り添い、存在することの重要性
【患者中心】医療者が主体となる「doing」から患者が主体となる「being」へ
【スピリチュアルケア】 ただそばにいることで患者と家族にスピリチュアルな救いへの価値感
看護師の職業的な特性として、お世話好きモードが働きやすく、終末期においても善意の「doing」で支援すればするほど空回りして、さらに必死に「doing」支援してしまうと、ますます関係性が気まずくなることがあります。自分のなかの「doing」は心の中で願い、自分には何ができるのかと自問自答しながら「being」の姿勢で向き合う、私はそう解釈しています。
人生最大のクライシス
《オハナな管理人日誌 2024.12.27〜28》

パートナーの死
パートナーとの死別は人生のクライシスのひとつです。日本において、配偶者との死別は寿命に大きな影響を与えることが明らかになっています。特に男性において、その影響が顕著です。
【寿命の短縮】
配偶者を亡くした男性は、配偶者がいる男性と比較して寿命が大幅に短くなります。40歳時点での平均余命を見ると、有配偶男性が39.06歳であるのに対し、死別した男性は34.95歳と、約4年も短くなっています。興味深いことに、女性の場合、配偶者との死別が必ずしも寿命を縮めるわけではありません。40歳時点での平均余命を見ると、有配偶女性が45.28歳であるのに対し、死別した女性は43.32歳と、わずかな差にとどまっています。
【死亡リスクの上昇】
パートナーを亡くした男性は、死別後半年間で死亡リスクが41%も上昇します。その後リスクは若干低下するものの、それでもパートナーがいる人と比べて14%高い状態が続きます。むしろ、夫を看取った女性は総じて長寿である傾向が見られます。死亡年齢の中央値を見ると、死別した女性が最も高くなっています。
クライシスを乗り越えるために
パートナーとの死別における男女差から、その後の生活がどんな変化が生じているかを紐を解くと、どんな助けが役立てる可能性があるのかという学びになります。
男女差の要因
- 社会的つながり:男性は配偶者に依存する傾向が強く、死別後に社会的孤立に陥りやすい。
- 家事能力:多くの男性は家事を妻に依存しており、死別後の生活維持が困難になる。
- 精神面:男性は感情表現が苦手な傾向があり悲嘆のプロセスを適切に処理できない可能性がある。
男女差というと主語が大きい気がするので個人的には好みではありませんが、男性であっても女性であっても、夫婦であってもなくても、人生のクライシスには変わりはありません。相互作用や役割の関係性が実質的にも精神的にも深い繋がりがあればあるほど、喪失感を強く感じ、後の生活に影響が大きくなります。
慟哭
《オハナな管理人日誌 2024.12.29》

「慟」は身体を上下に動かして悲しむということ、「哭」は大声で泣くということ。
慟哭という言葉では表現が足りない悲しみは何と表現したらいいのだろう。
やり場のない悲しみで心が壊れてしまわなだろうか。
どんな言葉も届かない背中をみつめながら
少しであっても
溢れ続ける悲しみが放電できたのなら
この背中に触れる指先が
悲しみを振り払うことはできたのなら
「1分でも1秒でも生きてさえいてくれたらよかったのに。」
胸がつぶれるようなさみしさ
全身を切り裂かれたような悲しみ
無力な私たち
それを実感できることも大切なこと
グリーフ:悲嘆
《オハナな管理人日誌 2024.12.30》
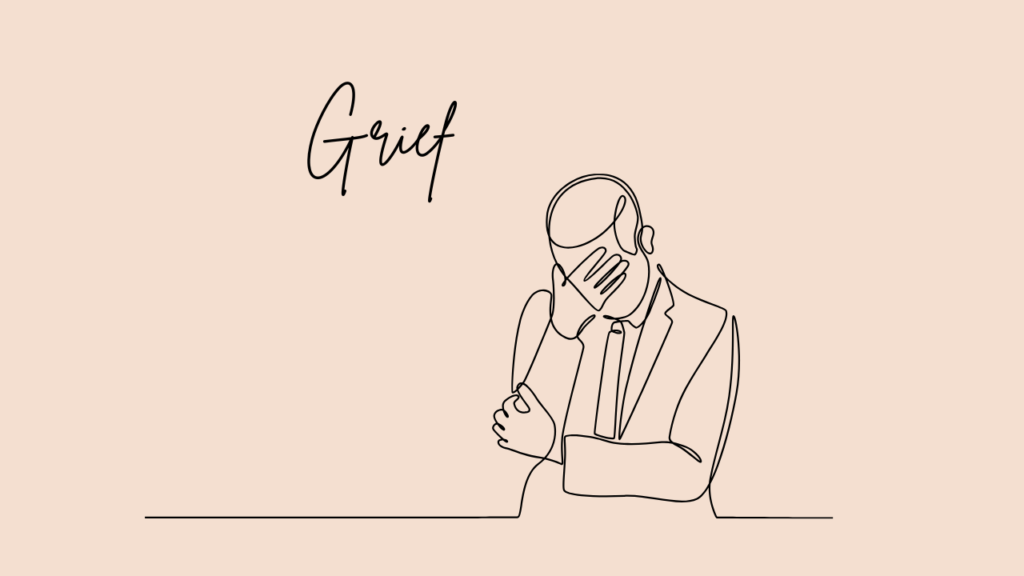
グリーフとは、直訳すれば「深い悲しみ」や「悲嘆」を意味する言葉で、大切な人や物を失ったときに起こる身体的・精神的な変化を指します。
グリーフの特徴
グリーフは単なる悲しみではなく、より複雑な感情状態です。死別だけでなく、離婚、引越し、仕事の喪失など、さまざまな喪失体験で生じます。孤独感、絶望感、不安を引き起こす可能性があります。睡眠障害、食欲喪失、体力低下などの身体的症状を伴うことがあります。
喪失体験でグリーフが生じる可能性があるのは、家族や友人との死別、ペットとの死別、死産や流産の経験、災害による住居の消失、 重要な人間関係の終了などです。グリーフに陥ることは正常な反応で個人によってその過程や期間は異なりますが、2週間以上だいたいの日で気分が落ち込んでいる、または2週間以上何も興味がわかない状況がある場合は専門家に相談することをお勧めします。
2024年最後の日
《オハナな管理人日誌 2024.12.31》

2024年最後の日、いかがお過ごしですか?
昨日が私の仕事納めでした。いつものケアの中でも自然と今年を振り返る話題を振ってしまいます。介護や療養を続けていると、そのことに精一杯になってしまって周りを見渡す余裕がないことが多いです。こんな時期も私は外からの心地よい風でありたいなぁと思います。切れ間がない平凡な介護や療養の日常を、伴走し続けている私たちが違う目線で軌跡をなぞり、対話という光をあててみます。一年どうだったかって私も考えあぐねますが、細かい出来事であっても、全体的な雰囲気であっても、今の直感的な気持ちを口に出せることが大切かと思います。春の桜がきれいだった、去年できないことができるようになった、変わらず過ごせたことが何より、今ここで一緒に過ごせることが一番…。その気持ちに手をあてるように、介護される方と介護する方それぞれに言葉にならないお互いへの気持ちをアイメッセージで添えながら、幸せのお裾分けの時間を過ごさせていただきました。
今年もたくさんの幸せをありがとうございました。
新年も一緒に過ごせることを楽しみしています。
良いお年をお迎えください
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。