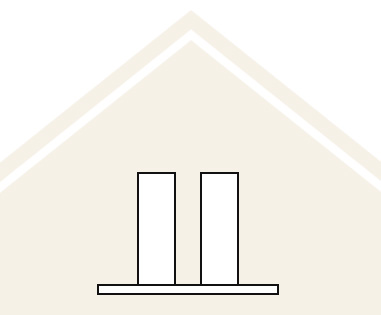おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.2.12〜2.18】
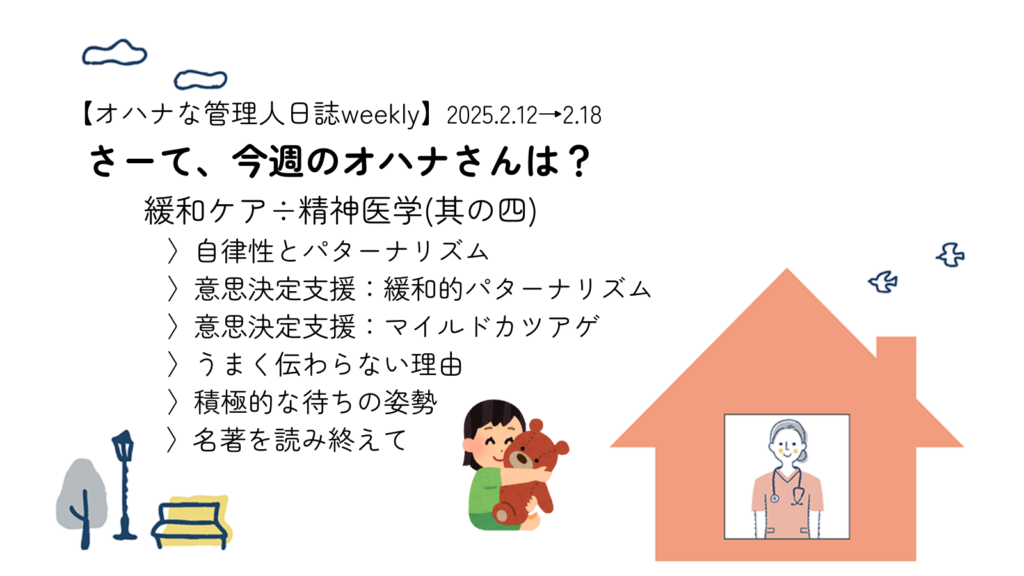
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
緩和ケア÷精神医学(其の参)
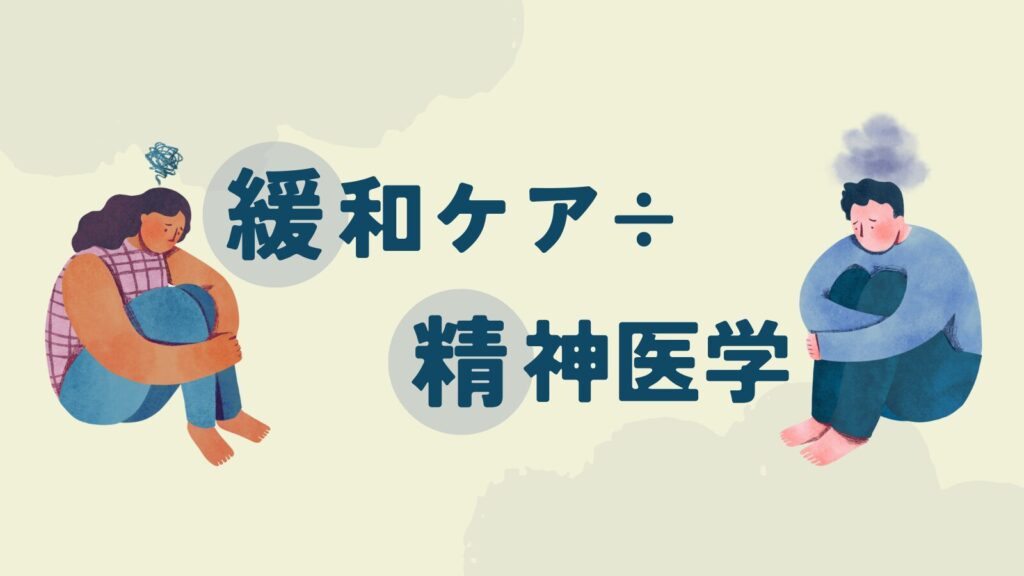
参考引用文献:緩和ケア÷精神医学から 森田達也・明智龍男著 【医学書院】
自律性とパターナリズム
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.12》
日本ではアドバンスケアプランニングや人生会議として、人権尊重からも自律性が大切だと叫ばれるようになりました。その自律性とパターナリズムについてちょっと脱線してみます。
つい近年までは医療者側が専門職として、与益・無危害の医療倫理的な考えのもと、主治医がベストとして判断された選択が一番良いとされていました。それをパターナリズム(Paternalism)といい、権力や能力を持つ者が、弱い立場にある者の利益や幸福のためとして、その意思を無視して干渉や介入を行うことを指します。日本語では「父権主義」や「温情主義」、とも訳されることがあります。
1970年代初頭に医療社会学者のエリオット・フリードソンによって、「医者と患者の権力関係」がパターナリズムであると指摘されました。著書の『医療と専門家支配』では、医療専門職を専門職のプロトタイプ(型)としており、専門職が社会的支配力をいかに獲得し、患者に影響を及ぼしてきたかなどが言及されています。この医療現場におけるパターナリズムは「医療父権主義」「医療パターナリズム」と呼ばれています。
日本の医療におけるパターナリズムの流れ
1. 戦後から高度経済成長期まで:医師主導のパターナリズム
この時期、日本の医療は「医師中心」の体制が強く、患者は医師の判断に従うことが一般的でした。専門知識への信頼や畏敬が背景にあり、患者の意見が反映されることはほとんどありませんでした。例えば、乳がん治療では医師が再発リスクを重視し、乳房全摘手術を一方的に選択するケースが多く見られました。一方で欧米では、患者の希望に基づき乳房温存手術が普及していました。
2. 1980年代以降:自己決定権の台頭
1980年代から1990年代にかけて、患者の「自己決定権」が注目されるようになりました。これは、インフォームド・コンセント(IC)の普及とともに進展しました。 医師は患者に治療内容を説明し、患者が選択するという形態が徐々に取り入れられました。しかし、この時期でもまだ医師主導の傾向は残っていました。
3. 現代:共同意思決定への移行
現在では、「共同意思決定(Shared Decision Making)」が標準的なアプローチとして広まりつつあります。この手法では、患者本人だけでなく家族や医療従事者も情報を共有しながら最善の治療方針を模索します。特に高齢化社会を背景に、認知症など意思疎通が困難な患者への対応としても重要視されています。
日本でパターナリズムが長く続いた背景には、専門知識への盲目的な信頼や「お任せ文化」がありました。 一方で、自己決定権の尊重が進む中で、患者が意思決定できない場合や情報格差による不平等など、新たな課題も浮上しています。現場の肌感としては、医療の対象が全ての年齢層に対して施される特徴からも、受け手側の準備ができていない方々もいる土壌に、医療のスタンダードを平均して推し進められている印象を受けます。もちろん受け手は混乱したり、それもパターナリズムの一端として変化を丸呑みしている様子もあります。相互理解がなければ、本当の意味の共同意思決定とは言えませんよね。医療が病院から在宅へ移行する際にとても多く感じますが、それぞれの物語の背景があることも十分にわかっているので、全てありのままを受け止めることを繰り返すことで、振り返れば道ができていることを願います。
私ができることは、その覚悟ですね。
意思決定支援:緩和的パターナリズム
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.13》
『X月X日 主治医より本人家族に病状についてICされておりDNARの了解をとっておりBSCと説明されています。』
医療専門職以外はなんのこっちゃですが、よくご依頼いただくときに良く目にする文言です。
解説すると、『X月X日 主治医より本人家族に病状について説明をされており理解を得ています。(末期癌などの場合)心停止ないし呼吸停止した際に心配蘇生を行わないことに同意しており、今後の治療はがんに対する抗がん剤などの積極的な治療は行わず、症状などを和らげる治療に徹することを説明されています。』という意味です。
文言を読み解くとセンシティブで重い重ーい話です。本人家族にとって、医師の話をストレートに聞けない心情であってもおかしくないですよね。病状が厳しくなってきていることを受けとめられずにいる状況で、心肺停止したらどうしますか?なんて考えたくもないでしょう。今日まで心の支えとして頑張ってきた治療が行えなくなったことを否認したくなるのは、防衛機制として当然です。しかも余命時間もかなり限られてきて、療養や看取りをどこでどう過ごすのか意思決定して下さいなんて、能力があろうとなかろうと、わかりません、わかりたくありませんって心情に医療者はどれだけ自分の心を砕けるでしょうか。ケースワーカは板挟みになるでしょうね、在院日数も限られていて、受け止めきれていないのをわかりつつも話を進めなくてはいけない立場ですから。
終末期の意思決定は医療者でも難しい選択のオンパレードな状況な上に、たった1回しか機会がなくて取り返しがつかないような困難な意識決定をしないといけないのは、自律といっても家族や本人にはあまりにも荷が重すぎるという考えのもと、緩和的パターナリズムという優しさが終末期には必要であるいう論点があります。
本人にも家族にも自律した選択はもちろん大切だという前提のもと、その選択によって責任を背負わせることになることを携わる者は知るべきことです。特に家族が後から後悔が強まらないように「責任を引き受ける」ことを意識していたと森田先生の見解がありました。
4人に1人がガンに罹患するというデータがあるように、ガン治療も日進月歩しています。もちろん治癒することが一番ですが、ステージ4の延命のための治療薬もある時代ですから、選択肢があることは心の支えになります。しかし、いつか治療が難しくなるときがやってきたときに、「ギリギリまで治療できてよかったね」と、坂から転げ落ちるように体調が悪くなることを受け入れることができるでしょうか。「こんなに早く旅立ちのときが来るなんて」最近本当に多く聞く言葉です。
そんな中受け皿である私たちにできることは何でしょうか、問い続けます。
心の恒常性を保とうとする自然なの働きがあることや、それぞれの人生の物語やパーソナリティを学ぶことは、意思決定支援においても自分の中の捉え方が変わるものだと率直に感じます。逆に全く知らずに、目の前の事実だけを鵜呑みにしプロセスありきで良しと横行されてしまうことへの危惧も感じます。
意思決定支援:マイルドカツアゲ
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.14》
自律の「自分で決める」が「自分で決めなければならない」に置き換わりやすいのも深いです。「悪に病状をデータや論理的に説明して今の病状はあまりにも悪いのだから、抗がん剤を続けると命がむしろ短くなるし、緩和ケアを受ける方が長生きするという研究データもありますがどうしますか?あなたの責任の上で決めてください」という説明は、患者中心と言えるのかはかなり怪しいものです。
そのスタイルについて内科医の名郷直樹医師は次のように提言しています。
『この状況は「今ここで俺に千円差し出せば許してやるが、出さなければぶん殴る。どちらに決めるかは、お前の責任において、お前が自分で決めろ。自分で決める以上その責任はお前にある」というカツアゲの場面と本質的にどこが違うのかはっきりしない。』
カツアゲですか…的を得すぎてぐうの音も出ません。実はそれに近いことがよしとされていることに気がつかないことが多く感じます。終末期に関わるナースには是非知ってもらいたいです。
【終末期に横行するマイルドカツアゲ】
入院中で治療が難しくなった場面で「今後をどこで過ごしますか?もう治療がないんだったら家で過ごすのがいいよ、是非そうしたら?」
よく耳にする話で、何が問題なの?ってポカンのされる人もいるのでは?
ではそれをカツアゲ風に解釈すると、「このまま入院していても状態が悪化すると思われるので、状態が悪化する前に家に帰った方がよい。家に帰らなくてもいいが、その場合は帰る時期を逸するよ。」という意味が含まれているということです。
治療することができないのなら、せめてもの想いとして、良かれとして、『退院して家族と少しでも時間を過ごした方がいい』という看護師自身の価値観を押し付けているとも言えます。もしかしたら、逃避状況で時間がないことは考えたくない心理かもしれないのです。
私の経験からも、退院の目処がつき、在宅療養の準備が始まったところ、病棟で病室に来るナース、来るナースが家に帰れてよかったねを連発されたことで、予後がないことを押し付けられているように感じてしまい気持ちが落ち込み、退院が延期になってしまった方がいらっしゃいました。少し気持ちが落ち着いてからの退院となりましたが、残念ながら数日で旅立たれてしました。かけがえのない時間ですから、やり直しもききません。きっとマイルドカツアゲにさえも気がついていないでしょうね。
【家族に対するマイルドカツアゲ】
食べられなくなった時の点滴をどうするか?興奮性のせん妄や身の置き所がないくらいの倦怠感の際のセデーションをどうするのか?など選択を求められることは、正解がわからず決めかねてしまうのは当然のことですね。選択したことや、しなかったことで、家族が責任を背負うには負担が多すぎます。それこそ、その人にとっての軸を家族と専門職で一緒に考えながらの緩和的パターナリズムが必要かもしれません。
心に余裕がないのがわかっていながらも意思決定していかないといけない局面はあります。結果よりもプロセスが大事だと思っていますが、パニックになっている相手に冷静に決めてくださいなんて、無理難題を押し付けているだけで尊厳とは程遠いものです。行き先を決めてもらって線路をひくことだけに支援者の心がとらわれてしまわないように、望んでいない行き先に向かわされる本人・家族が日々のかけがのない生活を歩んでいくことで、たどり着くまでの想い出の日常を大切にできたらと願いながら、関わり続けることだけは、私にもできることかなあと思います。
誰のための意思決定支援なのか、今まで学んできた心理的防衛機制が潜んでいないか、自分自身が投影してしまっていないか、メタ認知していくには知識も経験も必要なのかもしれませんね。
うまく伝わらない理由
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.15》
病状を伝えているのにうまく伝わらないのはどうしてなのかしら?
それぞれの角度で解釈すると、一般的な臨床では『理解が悪い』、精神医学では『否認』、緩和ケアでは『希望』となります。きっと思い当たる経験があるのではないでしょうか。主治医から病状説明され、在宅でかけがえのない日々をどう過ごしましょうかという文脈に『なれない』理由があります。研究論文からも進行肺がんの患者さんの21%が、がんが治癒困難であることを理解していなかったと報告されています。21%って想像よりも上の数字です、5人にひとりですから。
どんな心理的な作用か明智先生の解説が続きます。『否認』は以前の解説した心理的防衛機制のひとつですが、現在は疾患な概念というよりも意識的にも無意識的にも日常生活において観察されるストレスへの一種の対処様式(コーピング)として用いられることが多いようです。
否認の3段階
ここでの否認の定義は、苦痛を伴う現実状況から自分自身の精神的な安定を守ろうとする働きとして、現状を直視することを避ける対処のことを言います。
レベル3:疾患の存在そのものを認めない(まれ)ー真の否認
例)診断名をがんと説明されてもそれを認めない
レベル2:症状と疾患の関連を認めない(比較的多い)
例)痛みがあっても受診しない
レベル1:疾患の致4性を認めない(多い)
例)奇跡を望む
4にゆく患者の心理過程としてよく知られているものの一つに、キューブラー・ロスの5段階モデルはご存知でしょう。否認ー怒りー取引ー抑うつー受容という5ステップをたどっていくと提唱されていますが、ここにも否認が現れます。
よく出会う臨床では「麻薬を使うほど自分の状態は悪くないとオピオイド服用を拒否する」「奇跡が起こることを望み続ける」など表現されることが多いです。ですから何も特別な病的な心理状態ではなく、無意識でされている対処法でもあり、むしろ健康的で人の心理としては自然なものです。まさに否認というよりは「希望」と表現される方がしっくりきます。
積極的な待ちの姿勢
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.16》
自然なものだからといって見守ることで大丈夫な否認とそうでない否認(明かに不都合と思われる状況)があることがとても難しいのです。まずは否認そのものよりも、否認の後ろに隠れている心情(心理的防衛機制がないか)について理解し、いや理解しようと努力し、です😅。
否認か希望かもと気づくと同時に、きっとつらいんだろうなと思いながら、過敏に反応することよりも、少し見守ることが大切かもしれません。
もう一方の方が難しい局面かといえる、『そうでない否認、非適応な場合』はというのは、否認されることで、たとえば効果的な治療を受けれらなかったり、逆に害をもたらす不適切な治療につながることや、生活の質を保つ上で著しい妨げになっている場合のことをそう表現されています。『穏やかで注意深い直面化など治療介入が考慮されることもある』それには、「Hope for the best,perpare for the worst」現状に対して最も良い転帰がもたらせられることを望むことに理解を示しつつ、一方では万が一に備えておきませんかという介入で、少しずつ現状の直面化を促す方法のコミュニケーション技術が有効と言われています。
まるでアレルギー疾患の感化療法のようですね、以前の太陽と4の名言から拝借すると、少しずつ太陽の光に慣れさせていくようなそんな感覚でしょうか。
いわゆるACP(アドバンス・ケア・プランニング)には賛否両論があります。終末期医療においては、患者さんの生活の質(QOL)を最大限に維持することに加え、いわば患者さんにとっての「望ましい死(QODクオリティオブデス)」というべきものの体現へと目標が移行することが多いです。これにはそれぞれの個別的な価値観の理解ぬきでは治療目標の設定とは言えません。特に文化的な背景から望ましい最期の要素は個人差が大きいのは当然で、「残された時間を知り準備をする」のも「4を意識しない」のもそれぞれの個別性の価値観があります。おしなべてすべからく、じゃあ人生会議でとテーブルに座わらされても、一体誰のための会議となっちゃいませんかね。
そして人間は加齢とともに楽観的になっていく性質があります。そういう特質が醸成されながら進化してきました。その自然な流れをせき止めて、そろそろ人生の終わりに近づいてきたからといって突然「現実をしっかりみなさい」という方向転換は難しいだろうなというのはすごく納得できます。
臨床的には、否認(希望)そのものは、それによって「自分が4ぬという恐怖」や「大切な人を失う哀しみ」からこころを守っているわけですから、本来は適応的で自然なものです。今は鉄壁の否認をしていても、現実と向き合わないといけない時期もあります。例えば衰弱が進んでトイレに行けなくなるなど、いやおうもなく刻々と身体の変化を実感することで、「もしもう時間がないのなら…」と気持ちがポロッと湧き出ることがあります。そういう機会を逃さないように『積極的な待ちの姿勢』が必要と森田先生は提案されています。
このポロッとや積極的な待ちの姿勢の話は思い当たることがあります。その時を逃さない準備は、私も意図的ではなくても持ち続けているスタンスで、反射的に発動してしまっているかもしれませんね。
名著を読み終えて
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.18》
私は個人的に緩和ケアの森田先生のファンで、今までもバイブル的な著書に助けられてきました。先生のお人柄なのでしょうか、くすぐられるんですよ。特にタイトルがやばい。今回だって、速攻ポチりました。森田先生の著書は痒いところに手が届く本なのです。
私が看護師の若葉マークが外れた頃もう30年前になりますが、やっとインフォームドコンセントという言葉があちこちで聞かれるようになった頃です。私の配属先の血液内科は不治の病が多く、パターナリズムが患者さんへの最大の優しさだとされていた時代です。全力を尽くす治療が患者さんの益とされていましたので、危篤状態であっても亡くなる日の朝だって抗がん剤の点滴がベッドサイドにぶら下がっているのは当たり前で、それこそ『全力の治療を尽くしましたが、残念ですが力及ばずご逝去されました。』主治医のそんなお悔やみの言葉をよく耳にしていましたが、私にとっては違和感でした。患者さんの口から『家に帰りたい』という言葉を聞いていたからです。そこから私の出産子育てを経て、社会復帰の際に、『お家』側の世界で生きてみたくなり、これまで違和感を別の角度で見られるようになりました。
ご縁と出会いから、たくさんの学びと幸せをいただいているのは、今も進行形です。その学びは意識的にも無意識的にも私の中に確実に積み重なっているですが、推し量ることは難しいものです。私の中に宝物として持っている自覚はありつつも、突然輝きだす時に宝物としての姿が見えることがあります。この著書がまさに私の中に光を当ててくれ、宝物の存在を教えてくれました。改めて、これまでの出会いに感謝し、これからの出会いに貢献できたらとワクワクします。
本著を推し活のようにポチり、期待以上の内容にのけぞり萌えまくり、妹たちにおやすみ前の絵本のように語りたくなった訳です。それでも満足できずに衝動にかられ、末の妹に一読するように指令を出し、巻き込み巻き込み、笑。読み終わって気がつきましたが、きっとこの森田先生と明智先生とのダイヤローグが羨ましかったのでしょう、この本を肴にして、立場の違う四女と対話を楽しみたかったんだと。四女も答えるべく本に付箋を貼りまくりで読んでくれました。今回のシリーズは四女との対話へのまとめとして私的なフィルター加工での仕上がりとなっております。テーマが深いので、一度に語り尽くせないものですが、実際の姉妹での対話は楽しいひとときでした。世界は広がります。奇跡のような幸せです。
なお、今回は専門分野の深掘りになってしまい、professional Ver.とさせていただきました。全く話が見えない方は大変申し訳ありませんでした、どうぞ読み飛ばしてください。中身はともかく、普段の私たちの裏側の顔や心の中を垣間見て下さると幸いです。表向きは平然を装っているはずですが、心の中では必死にバネを巻きつつ(笑)、満身創痍で何かお役に立てないかと考える日々であることをお伝えできたのなら何も言うことはありません。
「理」の字は宝石の模様の筋目という意味があるので、「心理」とは心の筋目と解釈できるでしょう。心の筋目に愛でるように手をあて、生まれる科学反応を期待していけたらと思います。出会いをいただけること自体が私にとって何よりのことです。それは日常のあちこちにきらめいている宝石のようなもので、私が留めておくだけではもったいないです。心動かされる日々はこれからも誰かの支えや癒し、そして人生の彩りの種として、いろんな形でお届けできたらと願うばかりです。
あー、楽しかった。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。