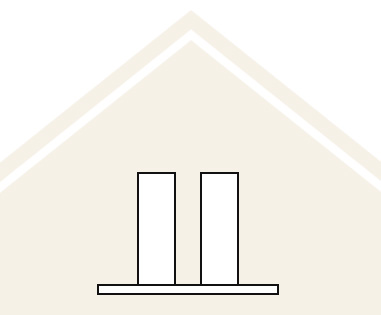おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.2.5〜2.11】
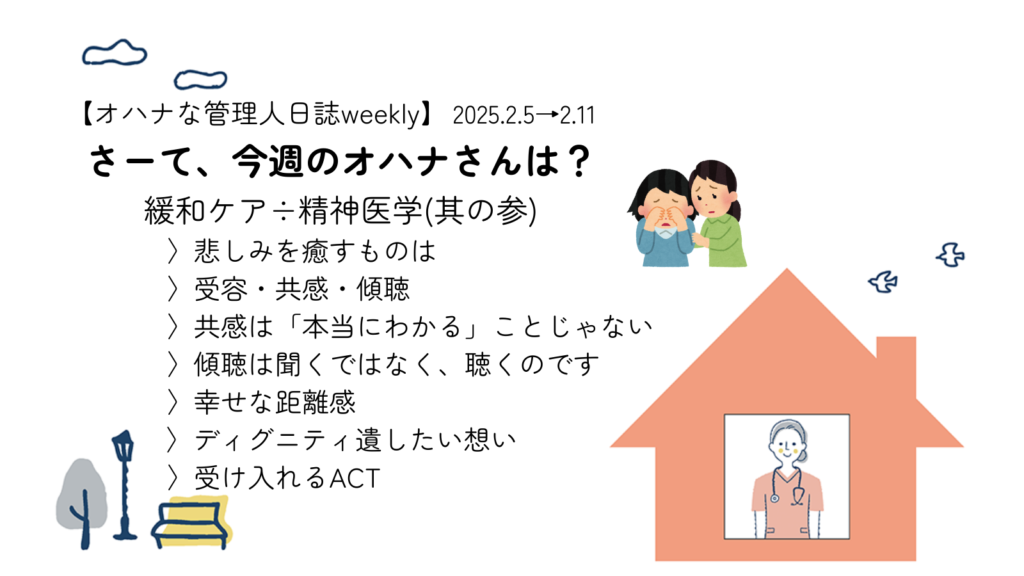
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
緩和ケア÷精神医学(其の参)
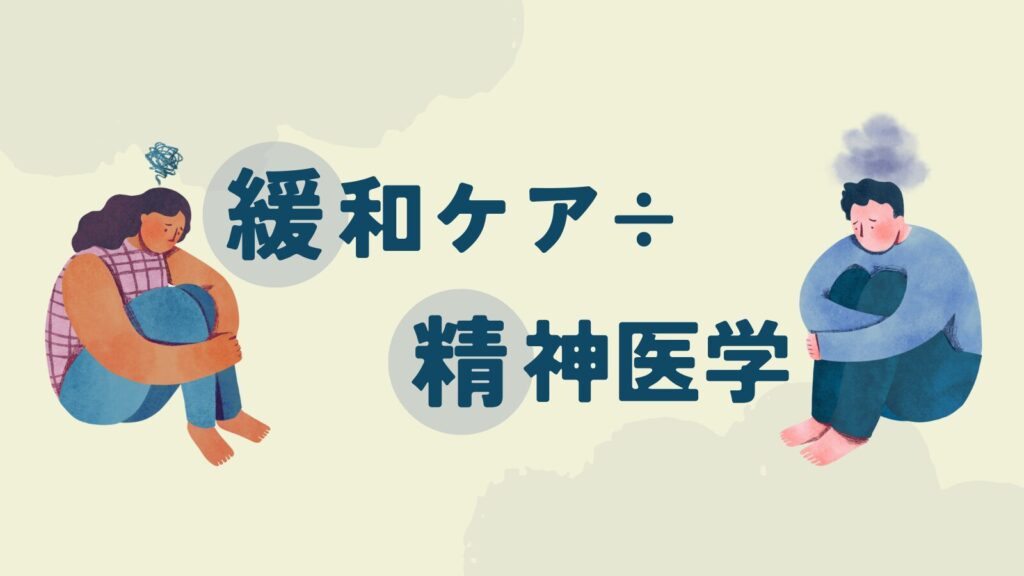
参考引用文献:緩和ケア÷精神医学から 森田達也・明智龍男著 【医学書院】
悲しみを癒すものは
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.5》
悲嘆の苦悩について【現状と課題】
⚫︎精神医学診断基準DSM-5からは一時は除外されていたが、4別後でもうつ病の診断基準を満たせばうつ病とみなすことになった。
⚫︎DSM-5-TRでは、特別有効な治療法があるわけではないが「遷延性悲嘆症(長引く悲嘆)」の診断基準が明確化されたので「診断名」としてつくようになった。
⚫︎4別後の悲嘆を精神医学上「疾患」のようにみなすことについて、正常な悲嘆プロセスを医学化するものだという強い懸念がある。悲嘆を医療の対象にすれば、心痛が低俗なものになり、4別を乗り越えていく自然な過程が妨げられ、悲嘆を癒すための伝統的な文化的儀式が頼りにされなくなり、有害の恐れのある不必要な薬物療法を招くことにもなりかねない。
⚫︎4別後の反応の個人差は大きく、日々の生活に大きな支障がない場合には「ちょっと変わった」体験が見られてもそのままで見守るようが良い場合が多い
実は似たような論点が緩和ケアの中でも、自然なものと「医療化」の中で揺れ動いています。たとえば、4前喘鳴を薬物で予防すべきかという論点があります。4前喘鳴が自然な経過ですよと説明したとて、苦しいと捉えて見守る家族にとってはずっと苦しい記憶が残ります。それらは医療側が勝手にしているのではなく、ご遺族の生活がより平穏になることを願ってのことなのです。
ホスピスケアの原点は、延命治療といわれる過度の医療化されたしの過程を、市民の手に取り戻そうというムーブメントから始まりました。しかし皮肉にも、現代においては、医療者が関わるホスピスケアプログラムがなければ平穏な最期を迎えられない高度に医療化された社会として発展してしまいました。
もともと人間社会が持っていた死別後の悲しみを癒すための儀式に医学がとって変わろうとしてはいけない、抗うつ薬よりも悲しみを癒す仕組みを人間社会は持っていることを忘れてはいけない。
そう森田先生は締めくくっています。とてもズッシリとくる言葉ですが、忘れがちが大切なことを言葉にしてくださいました。
この『医療化』問題は、とても悩ましく感じる場面に何度も何度も遭遇し、いまだにもやもやしたものを抱えています。特にパターナリズムが強くある環境下から在宅に移行する際に、同じ日本であっても文化的違いってこういうことかと面食らいます。『医療化』至上主義では、すべての苦しみを癒すことができないことを知っているからです。
受容・共感・傾聴
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.6》
Part2 4を前にしたひとのこころを支えるための方法
緩和ケアの精神的ケアのスタンダードの『受容・共感・傾聴』とは、医療職ならなおのこと、とても大切な関わりであるのは周知のことでしょう。それぞれふわっとした言葉のイメージは持っていても『言うは易し行うは難し』この言葉がピッタリです。
ちょっと回り道になりますが、すべての精神療法や心理的療法の基礎となる支持的精神療法は『ひとのこころを診察するとき基本となるもの』の要素であり、それらに中に受容・共感・傾聴が含まれます。
精神療法(心理療法)とは、一般的には、人との言語的、非言語的なコミュニケーションを通して、苦痛を和らげる治療法のことを指します。話をするだけで気持ちが楽になることってよくありますよね。実は治療においても大きな影響があり、薬物療法に加えて精神療法が併用されています。その精神療法のタイプに問わず、まずは信頼関係や礼節、誠実さ、あたたかさ、思いやり、相手の苦痛をすくいとる感受性などがないと、自分のことを任せられないと心を閉じてしまい精神療法どころではなくなります。
その基本中の基本である、受容・共感・傾聴について考えを深めていきます。
共感は「本当にわかる」ことじゃない
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.7》
誰しも自分のことさえもわからないのに、相手を「理解できる」ものではないと言う前提条件から始まります
じゃあ、支持療法とは机上の空論だと言いたいわけではなく、「共感」の本質は、わかることではなく、「理解しようと努力する態度と姿勢」のことなのです。
あなたの気持ちわかるわーと軽々しく言われると、あなたにわかるわけないじゃない!という気持ちが沸々と浮かび上がる経験ありませんか?それよりも、自分のことを理解しようと一生懸命にされる態度や姿勢そのものに、ホッと心が軽くなることあります。それが共感の本質であるのではと明智先生は解説されています。
よく終末期ケアにおいて、何かすること(doing)よりもただそこにいること(being)が重要をいわれますが、この背景にも共感しようとする努力や態度があるからこそ、そこに居るだけでどこにもないつながりが生まれ、あたたかさがじんわりと伝わっていくのかもしれません。
なんて勇気をもらえる言葉なのでしょう。そして、支援者がよく理解してその努力や態度が当たり前になる日まで、私にはやるべきことがありそうです。
傾聴は聞くではなく、聴くのです。
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.8》
語る相手の表情や声のトーン、節目がちに、沈黙があったり、今どんな気持ちで言葉を重ねているのだろうか、言い表せないけれどいつもとどことなく違う
そんな風に受け止めながら話を聴いたとしても、やはり完璧に聴けるわけはないことを知ると、「傾聴しました。」とは言えませんね。これも全てに通じること、あなたの話を聞きたいという態度だけが少し傾聴に近づくことができるのかもしれません。
ここでも傾聴の前段階である、非特異的要素が大切だと重ねて解説されています。誰しもそう感じることでしょう、私のことを思って聴いてくださっていると相手の体から醸し出される気遣い(誠意ややさしさと言う言葉が近いでしょうか)があるからこそ、話を打ち明けても良いという安心が伝わります。スキルや技術以前のZEROベースです。私の感覚で言わせてもらうと、『よかったら何か力になりたいと思っています』という願いですね。体から溢れ出し、言霊にも込められるくらいの強い願いは、無意識下であっても相手の心に伝わってしまうものです。
しあわせな距離感
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.9》
精神科では距離感を保つことが治療となり、緩和ケアでは2人称に近い、ひととひととの関係の誠実な姿勢が苦痛緩和のベースになります。
どちらも目の前の患者さんの幸せのための距離感ですが、真逆な作用であるので、精神科に慣れていない専門職にとっては考えたこともない観点なのです。
展開が早い終末期では今の足元から解決する必要がありますが、長いお付き合いとなる精神科では先を見通しながら限界設定(きまりを決めてぶれずに遵守する)することが治療に役立てトータルで見ると幸せに寄与できるということなのです。
すべての支援者に共通していることかと思いますが、はじめが肝心ですよね。ファーストインプレッション、第一印象は本当に心を砕きます。私たちのように終末期ケアの介入は、時間が限られている中でまずは信頼関係、ラポール形成をいかに迅速に構築できるように全集中します。私の経験からは、そこには看護師としてだけでは物足りなく、人としてのマインドが必要に感じています。ですが、それを精神医学的とくにボーダーライン心症に至っては、その距離感は諸刃の剣になってしまう悲しい結末を精神専門家は知っているので、治療としての最初の距離設定がとても重要なのです。
精神訪問看護では、とても腑に落ちる見解で、先生方もそうだといってましたが、私にも苦い経験はあります、そういうことなのかと。
全くスタンスが真逆な距離感ですが、しあわせな距離感として意識的な関わりがとても大切だということですね。それが目に見えず、『心で感じるんだ』と言ってしまうと、まるでスターウォーズの世界で、笑。できるよりもまず心得るから始めていきましょうか。
日々の関わりで、僕たちの言葉や態度でどれだけの「苦痛を和らげる治療(緩和ケア)」の結果が左右されているのかが身に染みます
森田先生の言葉…しっかりと心に刻まなきゃ。
ディグニティ遺したい想い
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.10》
ディグニティセラピー:終末期患者を想定して、少ない回数で「人生において自分において意味のあると思えたこと」「愛する人に伝えておきたいことや知っておいてほしいこと」をインタビューし、記録を作成して患者さん・ご家族と共有することで、実存的苦痛に対するアプローチのことです。
『太陽と4はずっと見つめることができない』の言葉にあるように、ひとは4にずっと向き合い続けられるものではないのです。このディグニティセラピーは世代継承性が大切なテーマに感じている人には良い効果ありますが、ずっと見つめることができない心情の方には逆効果です。記録を残すことが遺言感が出てしまうので、文章を作らないまでも、本人も家族も、何か残したいなと(何か残してほしいな)という気持ちがちらっと見えたときに、タイミングを逃さず、橋渡しする方が自然な形に感じます。
そういえば娘さんから頼まれたことがありましたね。亡くなった後に大切にしたいから、本人からの手紙が欲しいのだけど、看護師から伝えてもらえないだろうかと。手紙を書ける時間も限られていましたので、早速ご本人に伝えました。書くのをためらっていましたが、娘のためにと思っていたと思います。手紙を書かないといけないと頭ではわかっていても、まだ残されている時間はあるという希望から書くのを先延ばしにしていたのではと今はそう思います。あっという間に起き上がれなくなり、手紙は完成することはありませんでした。
また別の方は退院直後から身体的な苦痛が強く、残された時間もかなり限られている印象を受けました。元々口数の少ない方でしたので、後から後悔される方もいらっしゃったのでと前置きして、ご本人ご家族ともに伝えたいことがあれば先延ばしにしないようにとお伝えしました。想像以上に経過が早かったので、ゆっくりと話ができなかったのではと心配するのは杞憂でした。実はご本人が治療困難と告知された頃に自筆証書遺言書保管制度を利用され、ご家族宛の手紙が遺されていたそうです。特に遺産相続に関して遺言を残したい方には公的なシステムで手数料も安いので実質的なディグニティとして有効です。
緩和ケア医としてがん患者約千人を看取り、自らもがんのため45歳で亡くなった関本剛さん。生前に収録し、自身の葬儀で上映した「別れのあいさつ」の動画は注目を集めました。https://youtu.be/lX0l4vNUhoI
関本医師のように太陽を見つめるために心のサングラスを持ち合わせているひとは少ないでしょうが、これからはこういうディグニティも増えてくるかもしれませんね。このセクションにとっては余談になりますが、関本先生の動画で話される内容のような死後の世界観がとてもしっくりいきます。たくさんのお別れに立ち会う私たちに勇気を与えてくださる言葉ですし、そう思えることは私が生きていく上でも4ぬときでさえも希望になるだろうと感じます。
受け入れるACT
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.11》
アクセプスタンス&コミットメント・セラピー(ACT)
片仮名にすると難解に感じますよね。認知行動療法のひとつと位置付けられていますが、とてもユニークな理論です。病気や症状の低減を目標にせずに、そのままにしておき(受け入れる=アクセプタンス)、元々大切されていた価値に基づいた行動に気がつき、それに目指して生き直すという治療法だと明智先生は解説されています。それでも治療法なの?と、ただの放置や怠惰なだけじゃないとと勘違いされそうですね。もう少し突っ込んだ解説をすると、病気や症状が解決できないタイプであればあるほど、意識のスポットライトが病気や症状に偏ってしまいがちです。支援者はなんとか問題解決しようと思案しますが、人間が施せない領域の壁にぶち当たり、本人も支援者もお互いに苦しみの螺旋階段をグルグルと回り続けることになります。ACTでは病気や症状はそのままに受け入れ、その意識のスポットライトを目の前の今、ここでの自分にとっての価値(喜びや穏やかさに)に当てられるようにサポートすることだと言えます。
有名なニーバーの祈りをご存知でしょうか。
【ニーバーの祈り】
変えられるものを変える勇気を、
変えられないものを受け容れる冷静さを、
そして、変えられるものと変えられないものを区別できる知恵を与えたまえ
緩和ケアの本質が詰まっている深い言葉に感じます。変えられること、つまり緩和できる苦痛は全身全霊でサポートしていく、そして変えられないこと、4がそう遠くない将来に生じることを抗おうとしても現実は厳しいわけです。どうこうしようともできないことは置いておいて、今日、いま、ここでのしあわせ探しを一緒に共有していく。それは「夜と霧」のヴィクトール・フランクルが提唱したような価値を彷彿させられます。
【Franklの3つの価値】
①創造価値:何かを生み出したり、創造したりすることの価値
②体験価値:自然や芸術、愛情などを経験することの価値
③態度価値:自身の運命に対する態度、姿勢によって生み出される価値
これが慢性疾病や加齢によるもので辛さを抱えながら生きていく方への支援として提唱されている、ストレングスモデルも捉え方が似てますね。ただし時間軸が入ると、より適切なアプローチを選んでいく必要がありそうです。
ACTの概念の中でも同じように出てきましたが、『まず自分自身が医療者として、自分の無力さに自覚的になる』という前提が、どの局面においても支援へと導いてくれるということがとても感慨深いです。無力な自分だと知ることが、誰かのお役に立てられるかもしれないんですから、禅問答のようです。そういえばACT入門の本で『幸福になりたいなら 幸福になろうとしてはいけない』というタイトルがあります。そちらの本は翻訳専門書なので、読み解くには時間が必要ですな。いつか解説してみたいですが。
このACTの章のおかげで、私が支援者として無我夢中にしていたことを解説してもらえたので、ロジカルシンキングとしてスッキリできたことが驚きの発見でした。なるほどって、ガッテンボタンか、へえボタンを押したい気分ですよ。今までつたないながらも終末期に向き合い続け、役に立ちたいと思う一心だったことが結果オーライで、これまでバーンアウトせずに過ごせているのだと、改めて委ねていただける偉大さを感じました。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。