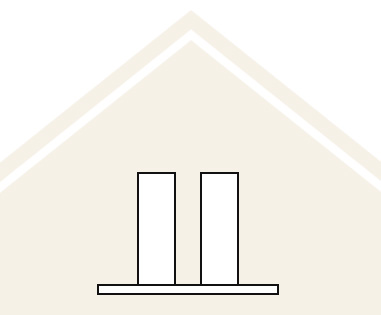おうちナースな7DAYS|オハナな管理人日誌weekly【2025.1.29〜2.4】
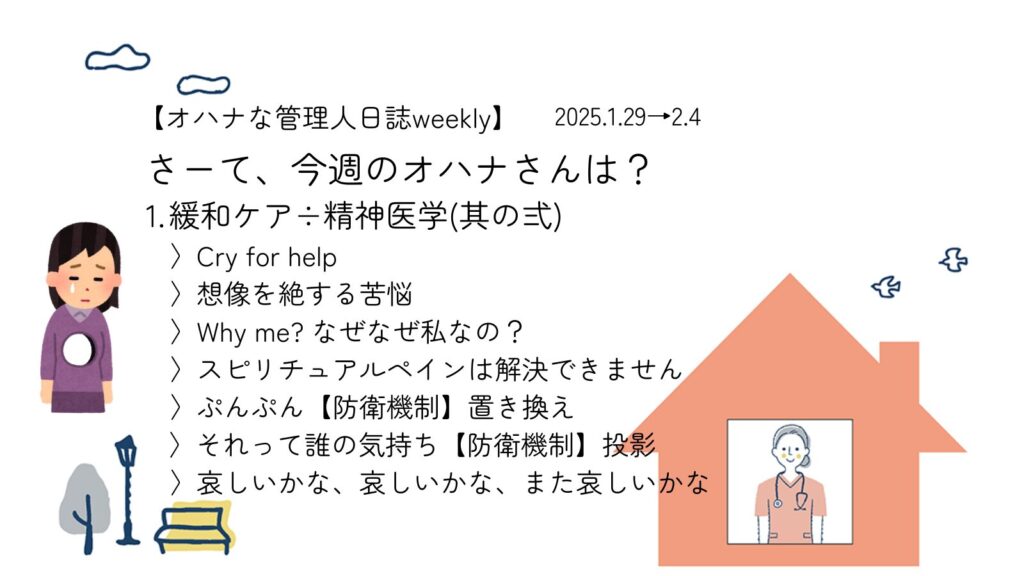
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
目次
緩和ケア÷精神医学(其の弍)
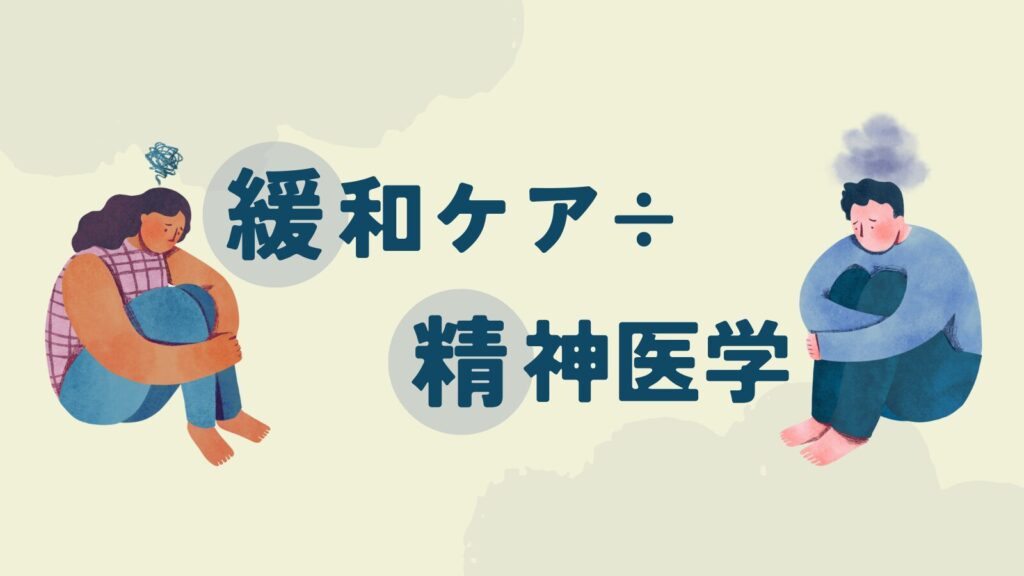
参考引用文献:緩和ケア÷精神医学から 森田達也・明智龍男著 【医学書院】
Cry for help
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.1.29》
妹達の切実なリクエストに応えるべくチャレンジしましょう。とてもセンシティブな論点でSNSでの発信がとても悩ませる、でも大切なこと、緩和ケアにおける希4念慮です。
先日の授業の中でも、魔法でも使わない限り叶えてあげられない悲痛な希4念慮の願いをあえて取り上げました。現実問題として難しいのがわかりつつも、Beingの大切さを説くと空気が変わりましたね。社会通念上や倫理的な理由という解釈で、本人の悲痛な言葉を淘汰してはいけません。希4念慮が生まれるくらいの苦痛にさいなまれていることを、理解したい気持ちから生まれる化学反応があります。『心をイメージして手当をする』その感覚に近いかもしれません。ボロボロの心を包み込むような優しさで話を受け止めケアを重ね、どんなあなたであっても、ここにいてくれること。縁があって出会えたこと。こうやってかけがえのない時間が過ごせること。ここ、今、この瞬間の私の幸せとあなたの存在への感謝を伝えたいと思うのです。
そして、あなたの切実な願いならば、少しでも早く叶うように祈りたいです。
想像を絶する苦悩
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.1.30》
コタール症候群
不死妄想・永延妄想が症状のひとつです。いわゆる4ぬことすらできないという底知れぬ強い苦痛があります。高齢の重症にうつに見られる症状なのですが、サイオンコロジー界において大変示唆に富んでいる概念に感じます。逆説的にいうと想像を絶する苦悩の中では、4が救済になり得るということです。
合理的希4念慮
こんな状態であれば誰しも4にたくなるなるよなぁというぐらい辛い状態や状況が存在します。(例えば、難治性の激痛、耐えられない呼吸困難、身の置きどころがない言いようがないだるさ等)安楽死を制度化している国もありますが、日本では許容されていません。
希4念慮への背景には様々な苦痛が横たわっていますので、まずはそのつらさを知り理解に寄り添います。どうして4にたいのかの理由に対処して、身体的苦痛があればその緩和、楽しみがなければ快の提供、たとえ寝たきりであっても自己決定による自律性の尊重に努めます。とはいえ難治性の苦痛も存在しますので、ガイドラインによる適応があれば鎮静も可能で、辛くて仕方がないときに数時間でも眠ることができ、その間は苦痛から解放される時間を確保できるのです。
医学がどれほど進んでもすべての4を無くすことも、すべての人間の苦しみをなくすことはできません。そんな場面では、そこにとどまること、一緒に苦しさを理解しようとすること、苦しい中にも1日でも一瞬でも生きてきてよかった思える時間を探すこと、いわゆる『幸せ』探しが求められています。
すべての人間としての苦しみを医学が無くすことはできません。それであってもそこに一緒にとどまり、日常の『幸せ』探しが灯台のような明かりになると考えます。
Why me? なぜなぜ私なの?
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.1.31》
Why me?スピリチュアルペインを語る前にちょっとおさらいを。
スピリチュアルペイン(霊的苦痛)は、近代ホスピスの創始者である英国の医師シシリー・ソンダース(Cicely Saunders)によって提唱されました。終末期患者が経験する苦痛を単に身体的側面からではなく、「トータルペイン」全人的苦痛という概念で説明し、その中に身体的、精神的、社会的、スピリチュアルペイン(霊的苦痛)な側面から構成されているという全人的な視点のひとつです。
『スピリチュアル』の言葉のイメージ的には理解が難しい領域ではありながらも緩和ケアの基盤となる重要な考え方として定着しています。「どうして私が」-why me?の苦悩や死後の苦しみへの不安や「(末期癌で)生きていても意味がない。」等という苦悩の気持ちですよと言われると、あーそうかと納得して頂けるでしょうか。
ではスピリチュアルペインをお二方の先生の分野で割り算していただきましょうか。
精神科領域から「スピリチュアルペイン」を照らすと、多くは既存の精神疾患の診断基準に当てはまらず、いわば正常の反応ととらえられる状況と言えます。たとえば苦悩に加え、興味関心の低下、不眠、食思不振、希4念慮があれば、『うつ病』ですねと診断されます。
スピリチュアルペインの二つの軸
①【宗教的な軸】人間を超えたものに対する感情 → なんでこんな苦しみを与えるのかという神や先祖への怒り、4後の世界で苦しみを受ける不安など
②【実存的な軸】人間として自分が消滅することに関する苦悩 → 意味のなさ・価値のなさなど
そんなスピリチュアルペインに似たものを扱った精神療法としては、サイオンコロジー領域から、実存的精神療法、意味に焦点を当てた精神療法、ディグニティーセラピー、そして実存療法として V.E.フランクルのロゴセラピーがあります。
精神医学でも「スピリチュアルペインという概念はない」と言いつつも、実際に患者さんが体験するスピリチュアルペイン(らしきもの)に対するアプローチが試みられていたということがとても興味深いですね。
スピリチュアルペインは解決できません
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.1》
『スピリチュアルペインは、苦悩している人から生まれるものであって、他人がどうこうできる性質の苦痛ではないということは知っています。でも、いつも私の話を真剣に一生懸命に聴いてくださるあなたには打ち明けたいのです。わかってます、解決ができない苦悩だってことも。あなたはとても忙しいはずなのにそんな素振りを見せずに、私の話を聴いてくださり、受け止めてくれることがどんなに嬉しいことか。終末期だから仕方ないと諦めずに、身体の辛さを緩和することを一生懸命に力を惜しまず対峙してくれ、眠れることを一緒に喜んでくれることに、どんなに救われることか。いつもの笑顔のあなたの存在自体が、苦悩で擦り切れた心のエネルギーを満たしてくれるのです。』
こんなふうに感じて頂けたら、支援者である私たちもどんなに救われることでしょうか。医療者は問題解決思考でトレーニングされているので、解決できない問題には不慣れなのです。そうだとしても「スピリチュアルペインを無くそう」なんて勢いで来られると、お帰り下さいって言いたくなります。まるでマインドコントロールをすることと同じですから、他人の心を動かすことはできないのです。それを逆手にとると自分の心は自分で決められるでしょう。目の前の苦悩を残念ながら私が無くすことはできませんが、辛さが和らいで欲しいという願いが、私の手のひらから、じわーっと伝わると思います。
亡くなった人にケア評価してもらいたいものですが、残念ながら次の世界で会えるまでのお楽しみになっています。筆者の先生たちが記してあることは、まさにそのまま私のつたない経験の中でも全く同じように感じます。それまた不思議なことですが、自分のケアの軸へのチューニングになりました。
ぷんぷん【防衛機制】置き換え
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.2》
感情むき出しで患者さんに怒鳴られた経験が、看護師ならひとつやふたつあるのではないでしょうか。ハラスメント的観点は今は置いておいて、どうして火がついたように怒りが湧き上がってくるのでしょう。特に緩和ケアの状況でよく見られる『防衛機制』を一緒に押さえておきましょう。
防衛機制とは、強いストレスや不安を感じたときに、自分の心を無意識に守ろうとする仕組みのことです。これはオーストリアの精神分析学者フロイトが提唱した概念で、人間が困難な状況に直面した際、心のバランスを保つために働きます。
防衛機制の主な種類と例
1. 抑圧: 嫌なことや不安を無意識に心の奥に押し込めること。
例) 怖い夢を見たけど、朝には内容を忘れている。
2. 合理化:自分の失敗や行動にもっともらしい理由をつけて正当化すること。
例)テストで悪い点を取ったとき、「勉強する時間がなかったから仕方ない」と思う。
3. 同一視 :他人の良いところを自分と重ねて満足すること。
例)好きなスポーツ選手が活躍しているのを見て、自分も誇らしくなる。
4. 投射:自分の嫌な気持ちや欠点を他人に押し付けること。
例)自分が苦手な先生が、自分のことを嫌っていると思い込む。
5. 反動形成: 本当は好きなのに、その逆の行動をとること。
例) 好きな人にわざと冷たく接する。
6. 逃避: 現実から目をそらして別の世界に逃げること。
例) 勉強が嫌でゲームばかりする。
7. 退行: 幼い頃の行動に戻ることで安心しようとすること。
例) 怒られた後、泣いて親に甘える。
8. 代償:本来欲しかったものが得られないとき、別のもので満足すること。 例) 欲しいゲームが買えない代わりにマンガを読む。
9. 昇華:不満や欲求を社会的に価値ある行動に変えること。
例) ストレス発散のためスポーツや絵を描く。
10.置き換え:本来の対象ではなく、別の対象に向けること。
例)職場で上司に叱られたストレスを、自分より立場が弱い家族や物にぶつける。
11.投影:自分の内面にある感情や欲求を他人に押し付けること。
例)自分が職場の同僚を嫌っているのに、その感情を認めたくないため、「あの人は私のことを嫌っている」と思い込む。
病状によって辛い症状への怒りのやり場に困っているところに、つい目の前の人に八つ当たりしてしまうのは、防除規制の中の『置き換え』に当たります。
当たられた方は理不尽に感じますが、実は患者さんがこういった場合に怒りを向ける対象は、多くの場合は、信頼していたり頼りにしている存在であることが多いのです。
とはいえ、私たちも人ですから凹みますよ、
私だって、ねえ笑。
それって誰の気持ち?【防衛機制】投影
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.3》
防衛機制のひとつ『投影』のおはなし。自分の気持ちや抱えている問題をまるで他の人が経験しているように感じることです。無意識な心理的防御ですから、目に見えないものであり、投影によって真の問題が誰のものなのか見えにくくします。
緩和ケアで生じやすい投影の例
⚫︎患者ー家族間
患者の不安が強いという家族の訴えは、むしろ家族の不安の方が強かったりすることがある。
⚫︎医療者(自分)ー患者間
特に対象の患者が自分と重なる困難を抱えているとしたら、なおのこと自分の問題を「患者さんが感じている」ように体験することがある。無意識的な認知であるので気がつくことは難しい。
ある、ある、ある、ありまーす!
思い当たるエピソードは結構ありますが、それが投影かも?という深いアセスメントはできていませんでした。そうですね、例えば、がんの痛みが強くて別の薬の変更が必要かどうかっていう場面で、癌性疼痛は悪だという価値観のもとで医療者がアセスメントをすると、「かなり痛そうで辛そうです」と報告を受けた医師が実際に診察にいくと患者本人はそうでもなかったという事例はもしかしてだけど、です。患者さんが痛みを否認しているということもあるので限定はできませんが。そのお医者さん側からすると、え?報告してくれた看護師さんの投影だろうか?なんて逆アセスメントする先生はやや変◯チックですね、怖いです。
とても大事なことは、『置き換えも投影もなくすことはできない』という知識です。
怒鳴られて、ウッと立ち止まった時にメタ認知で俯瞰することができると、「あーもしかしてだけど、置き換えかなあ。私のことを信頼しているから感情的になってたんだなぁ」と、怒鳴られた心のダメージの回復がいくぶん早くなるやもしれません。間違っても、「怒り=病状の受け止めができていないから、もう一度主治医から説明してもらいましょう」なんて、正しい説明の応酬で怒りを増幅させることは避けましょう。
そして、自分が絡む場合の「自分の問題」が患者の問題のように見える投影については、こんな場面によく使うフレーズがあります。「私には〇〇のように感じますが、あなた(患者)はどうですか?」と率直に聞いちゃいますね。そして「それで何か助けが必要でしょうか?」と問題についての相手の捉え方を確認します。その問題について掘り下げて尋ねることで、同じ温度感で情報共有すると誤解が起こりにくい肌感があります。まあ、その話をした時はそうでもあっても、考えはいつでも変わる可能性があることも覚悟しておくと振り回されずに心穏やかに対応しやすくなります。
哀しいかな、哀しいかな、また哀しいかな
《オハナな管理人日誌 professional Ver.2025.2.4》
『哀しい哉(かな) 哀しい哉(かな)
哀れが中の哀れなり悲しい哉 悲しい哉
悲しみが中の悲しみなり哀しい哉 哀しい哉 復(また)哀しい哉
亡弟子智泉が為の達嚫の文/空海
悲しい哉 悲しい哉 重ねて悲しい哉 』
あの悟りをひらいた空海でさえも、大切な弟子に先立たれた時に詠んだ詩とされています。ライフイベントの中でもパートナーの4が人生の最大のストレスであるという研究結果もあります。誰にでも起こりうることですが、とても辛い出来事のひとつ。大切なひととの終末期を過ごし、ピリオドが打たれて瞬間から、4別の苦しみの中で生きていくことの始まりを意味します。
4別後の悲しみも「病気なのか?」というテーマです。
大切な人との4別後に、悲しい気持ちになり、興味を失い、睡眠や食事がうまくとれず、気力を無くし、興味を失い、睡眠や食事がうまくとれず、気力を無くし、仕事が手につかないーそれは当たり前の反応で、うつ病とまったく同じ症状が出ることは珍しくありません。もちろん4別という人生最大のストレスによって、まともに生活ができないくらいのうつ症状が見られることもあり、それは医療の手助けが必要なケースもあると思います。一方で専門家の中にも<正常>を救えと精神医学的な診断として医学化しすぎているという批判もありました。そのような流れも踏まえながら、現状と課題について、お話を次に続けてみましょう。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。