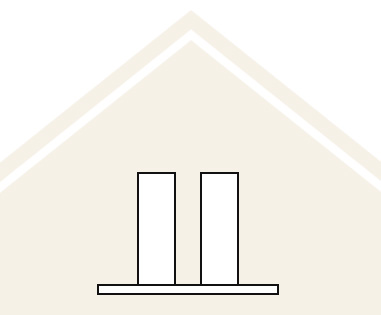おうちナースな7DAYS【オハナな管理人日誌weekly】2025.1.22〜1.28
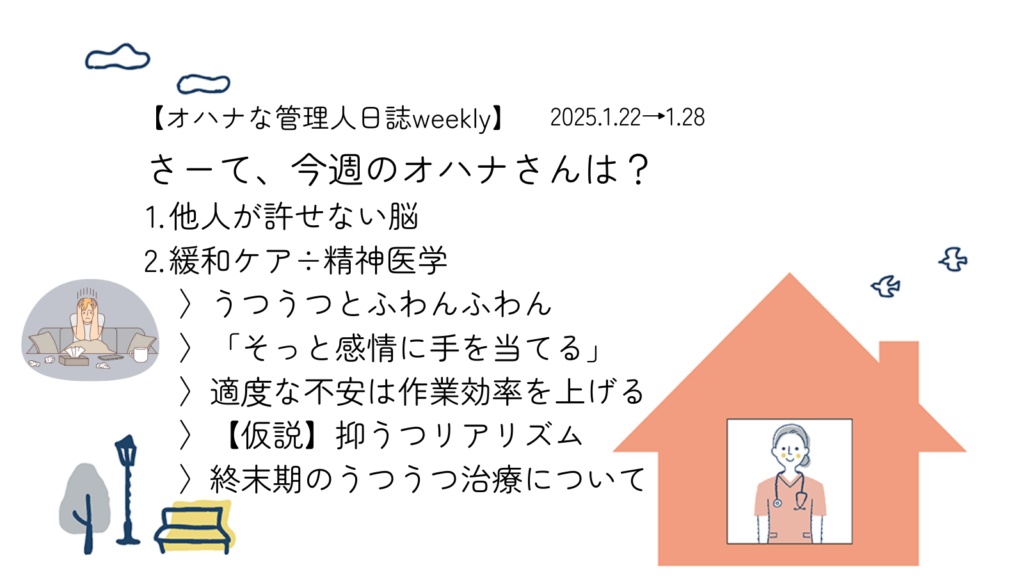
Instagramで投稿中のオハナなおうちの『オハナな管理日誌』のweeklyバージョンです。ダイジェストというより、リライトや加筆をしていることが多いかもです笑。管理人のバイアスが100%かかっておりますが、在宅看護の枝葉としての読みものとして楽しんで頂けたら幸いです。
記事内に広告が含まれています。
目次
他人が許せない脳
《オハナな管理人日誌 2025.1.22》

メディアに抗議が殺到、SNSが大炎上、人が他人を許せないとディスり、正義中毒に酔いしれる。それは脳の特性がなせる技。
正義中毒とは
1. 脳の快楽反応:人間の脳は、裏切り者や社会のルールから外れた人などの攻撃対象を見つけ、罰することに快感を覚えるように設計されています。この快楽反応が、人々を「正義中毒」と呼ばれる状態に陥らせる可能性があります。
2. 対立を好む脳の傾向:人間の脳は本質的に対立するように作られています。この傾向が、他者との違いを強調し、許容することを困難にします。
3. 確証バイアスの増長:ネット社会は人々の確証バイアスを強化する傾向があります。これにより、自分の信念や価値観と異なる意見や行動を受け入れにくくなります。
4. 集団思考の影響:特に日本社会では、個人の意思よりも集団の目的が優先される傾向があります。これにより、集団のルールに逆らう行為に対して厳しい態度をとりやすくなります。
5. 社会的ストレスの影響:現代社会のストレスや不安が、他者を批判したり許せなくなったりする傾向を助長している可能性があります。
これらの要因が複合的に作用し、人々は他人を許すことが困難になっています。この状態から抜け出すには、自己認識を高め、メタ認知能力を鍛えることが重要。
多様性を受け入れ、他者への理解と共感を深めることで、より穏やかな心で生きることができるのです。難しいですね…。
気づいてます?それって正義中毒というのですよ。今夜も脳の快楽から抜けられない子羊たちが量産されています。
緩和ケア÷精神医学
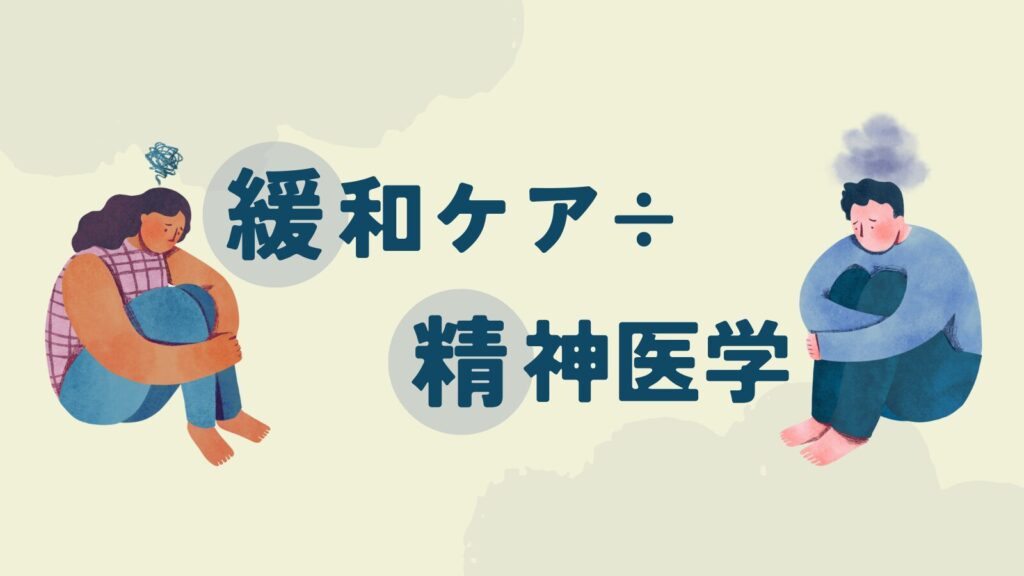
参考引用文献:緩和ケア÷精神医学から 森田達也・明智龍男著 【医学書院】
うつうつとふわんふわん
《オハナな管理人日誌 2025.1.23》
4を意識したときのこころの動きは、『不安』と『抑うつ』に整理されます。不安と抑うつ(うつ)には、症状や体の変化に明確な違いがあります。
不安は、漠然とした未文化なおそれの感情が続く状態のこと。もともとは生物として生き残るために、脅威に対しての⚠️警告信号。「戦うか、逃げるか」を選択する上で有利な身体状況を作り出すといわれています。ですから強い不安感や恐怖を伴う一時的な感情で、身体症状が顕著です。
不安の例は、大切なプレゼンテーションの直前に、急に心臓がドキドキし(動悸)、手が震え、冷や汗が出るような状態です。そのほか、息苦しい(呼吸困難)、胸が圧迫されたような感じ(胸部圧迫感)、むかむか(胃部不快感)、めまい、肩が凝る(筋緊張)、寝付けない(不眠)など。
一方、抑うつは、(正常範囲を超えた)強い悲しみの感情が続いている状態のこと。より持続的な気分の落ち込みや意欲の低下が特徴です。
抑うつの例は、何週間も続けて朝起きるのが辛く、仕事や趣味に興味が持てず、食欲も落ちているような状態です。だるい、疲れがとれない、おいしくない、頭が重い、すぐ目が覚める、思考・集中力低下など。
恋愛相手に告白しようとしている時は、うまくいくだろうかと当然不安になり、失恋して恋愛対象を失ってしまうと喪失感でうつになってしまうことはわかりやすいね。
これらの症状は併発することもあり、不安障害とうつ病が同時に診断されることも少なくありません。どちらの症状も生活に支障をきたす場合は、専門医への相談が推奨されます。
目の前の感情に「そっと手を当てる」
《オハナな管理人日誌 2025.1.24》
4を前にすると当然不安や落ち込みがあって当たり前ということを念頭におきながら、折に触れて気持ちの状態を尋ねることは支えになれる可能性があります。
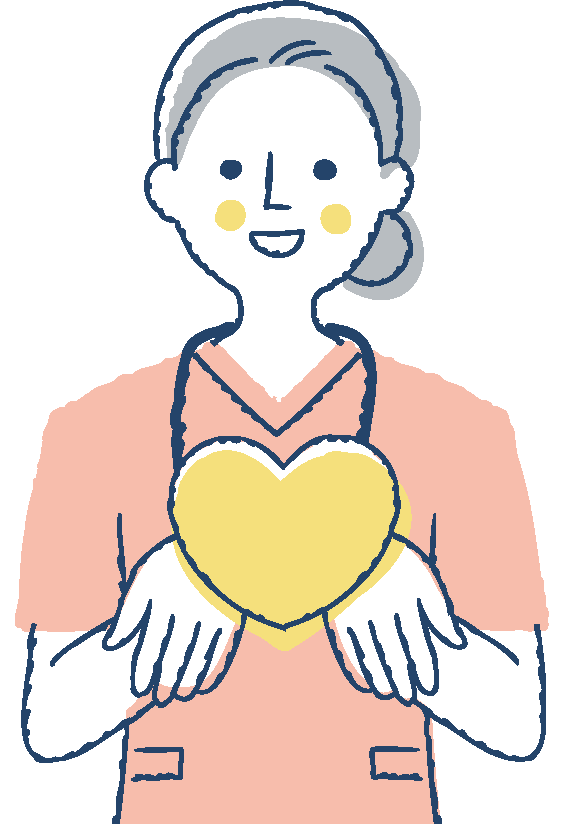
目の前の方の心に手を当てるイメージで。
よくコミュニケーション論で進められるしっくりこない『傾聴』を言語化
明智先生「感情に手当をする」
森田先生「患者さんの後ろ側に色のついた感情の塊のようなものをイメージして、それを一度自分の手の中に入れてから撫でたりさすったりしながら話を続けるというイメージ」
たとえ治療ができなくなってもケアはできます。心に手を当てるように、何か力になりたいという思いを乗せ、つらさを共有し、少しでも和らぐように願いを込めながら。
適度な不安は作業効率を上げるのだ。
《オハナな管理人日誌 2025.1.25》
不安やうつは、とにかくないほうが良いと思われがちですが、実は人の生存の歴史という視点からも必ずしもそうではありません。例えば病気になったとしても全く不安がなかったら、健康に気をつけたり、専門職のアドバイスを守る気持ちは起きないはずです。軽度な不安は、その人を守ってくれている機能となっているので、良い意味で『その不安』を大切にしましょうと言えるのです。2つほどトピックスを。
【ヤーキーズとドットソンの法則】
1. 緊張感が低すぎると、やる気が出ずに成績が悪くなります。
2. 緊張感が高すぎると、プレッシャーで失敗しやすくなります。
3. ちょうど良い緊張感があると、最高の成果を出せます。
人間の集中力や作業能力に関する面白い法則です。この法則は、「適度な不安・緊張感(ストレス)が最高の成果を生む」という考え方です。
たとえば、テスト勉強を考えてみましょう
1. テストが全然気にならない → 勉強する気が起きない
2.テストのことを考えすぎて不安になる → 頭が真っ白になって勉強できない
3. テストに向けて適度に緊張する → 集中して効果的に勉強できる
適度な緊張感を保つことで、自分の能力を最大限に発揮できるのです。逆を返せば、良いパフォーマンスには、適度な不安が必要だと言えますね。
【仮説】抑うつリアリズム
《オハナな管理人日誌 2025.1.26》
前回の不安の大切な役割に続いて、お次は抑うつのポジティブは面についてです。『抑うつ』と『ポジティブ』が同じテーブルに上がること自体、ほーーーって感じです。まだ仮説ではありますが、新しい切り口として面白く感じます。
抑うつリアリズム理論
この理論は、ローレン・アローイとリン・イボンヌ・エイブラムソンによって提唱されました。この理論は、心理学の中でも実験心理学の分野から生まれてきました。
【実験】ランダムな信号の点滅に対してボタンを押すゲームを行い、参加者の反応を観察しました。
1. 健常者:良い成績を自分の洞察力や実力のおかげだと捉える傾向がありました。
2. うつ病傾向のある人:良い成績を単なる運や偶然の結果だと評価する傾向がありました。
この実験結果から、うつ病傾向のある人の方が現実をより正確に認識していると考えられ、抑うつリアリズム理論が提唱されるに至りました。しかし、この理論には批判もあります。実験の設定が現実世界を適切に反映していない可能性や、抑うつの診断方法に疑問が残ることなどが指摘されています。そのため、理論の妥当性については現在も議論が続いています。
「気分は沈んでいるけど賢いかも?」そのうつ器質により、世の中を正確に見極めることや鋭い感性を持ち合わせ、指導力や創造性や才能で重要な業績を残した歴史的人物は少なくはないのです。リンカーン、チャーチル、ガンティ、ナポレオン、ルーズベルト、トルストイ、ナイチンゲール、ゴッホ、ヘミングウェイ、ベートーベン、徳川家康、夏目漱石、樋口一葉、与謝野晶子、石川啄木…等々、真偽はさておき。病状の程度によっては自4に至ることもあるのでその程度については議論はこれからも重要です。
とても辛いことに直面すると、落ち込み泣き悲しむという一定期間の抑うつ状態を経て、やがて現実を受け入れてスッキリしたという経験は誰しもあるでしょう。視点を変えると、抑うつ状態が生じるということは(=泣き悲しむ)、概ね客観的な現状の認識を受け取った証拠とも言えるということです!
泣いてスッキリすると思い込んでいましたが、泣く感情が生じたということ自体がリアルとして受け取れている証拠とも言えるという説でしたー。面白い👍
終末期のふわんふわんとうつうつのまとめ
《オハナな管理人日誌 2025.1.27》
【まとめ】終末期の不安と抑うつ
4を前にした人の心としての不安と抑うつの理解
- 不安や抑うつは、がんの進行や再発の時期の30%くらいに見られる
- 「適応障害」が「適応反応症」と言い換えられたように、精神疾患ではなくストレスに対する反応である
- 不安があることで「早く物事が進む」という側面がある
- 抑うつがあることは事実を事実の通りに受け取れている証拠ともいえる
終末期の不安と抑うつに対して臨床家に勧められること
- 適度な不安や抑うつの表出があった場合、つらい感情があってよかったという前提に立ち、「感情にそのもの」について話題にする(不安や抑うつの表出をなくそうとしなくても良い)
- 「感情に手当てをする」イメージを持つ
- 2週間以上継続して気分が落ち込んだままで楽しい時がない症状があれば、薬物療法や精神科医への紹介を考える
不安がないようにと考えがちな私たしのナース脳に、稲妻が走る思いです。よく考えると不安には意味があり、軽いうつには役割があります。不安や抑うつがあって当然だという前提を踏まえて、不安や抑うつをぶった斬って成敗するのではなく、感情に手当をするイメージを持つことが大切。ただ、長引く抑うつは専門家に相談を提案することは注意しましょう。
終末期のうつうつの治療について
《オハナな管理人日誌 2025.1.28》
うつ病による健康損失への影響はがん以上であり、今後も影響が拡大することが予測されています。うつ病は治療できる病気で、積極的に治療を受けるべき疾患だというのは言うまでもありません。前回のお話にありましたが、2週間以上継続して気分が落ち込んでいる症状があれば治療を受けることが重要です。
ただし、うつ症状の薬物療法は即効性に欠けるため、生命予後が週単位であれば効果が期待できないのです。さらに、薬物によってせん妄が強くなり、最期までせん妄状態でその人らしさが失われたまま旅立つことにもなりかねません。終末期のうつ症状に関しては予後や、本人家族が望んできる過ごし方、何を優先するのかをよく相談することが大切です。
たとえ、うつ病に対する治療を行わない場合でも
●うつ病に伴う苦痛が最小になるような、夜間の睡眠の確保、場合によっては日中数時間の確保(うつが忘れられる時間を作る)
●うつ症状=難治性の苦痛と捉え、苦痛緩和ケアとして、日常のケアとして快につながることを提供する、患者の尊厳を大事にした関わりをすることは常に大切なこと
日常の心地の良いケアを丁寧な思いやりで優しさを込めて提供することが、どの局面やどの苦痛においても緩和ケア支援として原点回帰するのは、とても意味深く感じます。
ははは、今日の講義の着地点もやはりこの論点でしたね。
それに気がつけることがどんなに重要か伝えていくのも役割でしょうね。緩和ケアに限らずです。
まとめ
バーチャルシェアハウス オハナなおうちは、みんなの居場所です。今日も楽しい時間をありがとうございました。会えてうれしかったです。いつでも寄ってくださいね。リビングルームにはコメント欄がありますので、何かリアクションしていただけたら励みになります。お気をつけてお帰り下さいね。また、お待ちしてます。