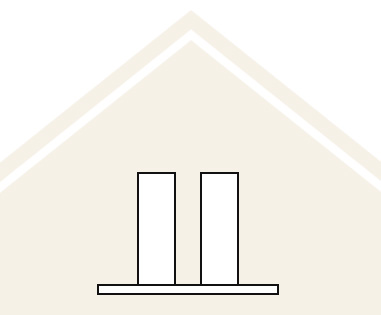マイナンバーカードの有効期限って、何年?本体と電子証明書の違いをわかりやすく解説【そっとケアQ #5】
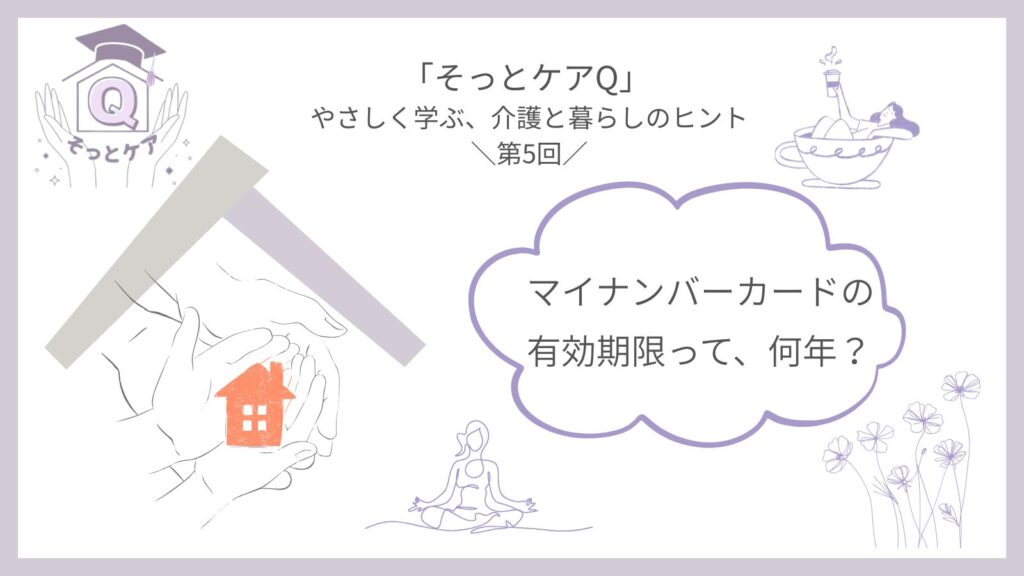
目次
マイナンバーカードの有効期限切れで困らないために
「マイナンバーカードって10年有効なんでしょ?」
「でも電子証明書は5年って聞いたけど…?」
そんな“ちょっとややこしい”疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
今日は、おうる先生と一緒に「マイナンバーカードの有効期限」をわかりやすく整理してみましょう
Q1. マイナンバーカード本体の有効期限は?
A. 年齢によって異なります。
- ⚫︎発行時に20歳以上の方 → 発行日から10回目の誕生日まで
- ⚫︎発行時に20歳未満の方 → 発行日から5回目の誕生日まで
身分証明として使える“カード本体”は10年(未成年は5年)なんじゃ。長いようで、うっかり忘れてしまう人もおるから注意するんじゃよ
Q2. 電子証明書の有効期限は?
A. 年齢に関わらず5回目の誕生日までです。
- ⚫︎署名用電子証明書(確定申告などで使用)
- ⚫︎利用者証明用電子証明書(マイナポータルやコンビニ交付で使用)
カードと証明書は“別々の有効期限”を持っているのがややこしいところじゃな
Q3. 有効期限が切れると何が困る?
主にオンラインサービスが利用できなくなります。
- ⚫︎e-Taxでの確定申告
- ⚫︎マイナポータルへのログイン
- ⚫︎コンビニでの証明書交付
健康保険証としての利用は、期限切れ後も3ヶ月間は猶予があるんじゃ。ただし、それを過ぎると完全に使えなくなるので要注意じゃぞ
Q4. これからの変更点は?
- ⚫︎2025年3月:マイナンバーカードと運転免許証の一体化スタート
- ⚫︎2026年:新仕様カードが登場予定
運転免許との一体化や、新しいカードへの切り替えも予定されているから、これからも“最新情報を確認する習慣”が大切なんじゃ
📝まとめ
- ⚫︎マイナンバーカード本体は10年(未成年は5年)
- ⚫︎電子証明書は5年
- ⚫︎期限切れで困るのはオンライン申請・マイナポータル・コンビニ交付など
- ⚫︎マイナ保険証は3ヶ月の猶予あり
- ⚫︎2025年以降は免許証一体化&新カード登場
👉 更新は有効期限の2〜3ヶ月前から市区町村窓口で可能です。
更新手続きで必要なもの
マイナンバーカードの更新手続きに必要なものは以下の通りです。
- ⚫︎有効期限通知書
- ⚫︎マイナンバーカード
また、マイナンバーカードに搭載されている電子証明書の更新も同時に行う場合は、署名用電子証明書の暗証番号が必要となる場合があります。特に、住所変更ワンストップサービスを利用したい方や、マイナポータルと連携手続きをする方は、署名用電子証明書の暗証番号を準備しておく必要があります。
更新手続きに関して
- ⚫︎手続き場所:更新手続きは、お住まいの市区町村の窓口で行います。
- ⚫︎更新のタイミング:マイナンバーカードの有効期限が満了する直前の誕生日から3ヶ月前から更新手続きが可能です。通常、有効期限の2~3ヶ月前を目途に有効期限通知書が送付されます。
- ⚫︎有効期間:
- マイナンバーカード自体の有効期間は、発行日から10回目の誕生日までです(20歳未満の場合は5回目の誕生日まで)。
- 電子証明書の有効期間は、年齢に関わらず発行日から5回目の誕生日までです。
- ⚫︎電子証明書の重要性:電子証明書の有効期限が切れると、マイナポータルを通じたオンライン講習の受講や、運転免許情報の確認、住所変更ワンストップサービスなどが利用できなくなります。健康保険証としての利用は、有効期限が切れてから3ヶ月間は可能ですが、それ以外のマイナンバーカードの機能は利用できなくなるため、速やかに更新手続きを行うことが推奨されます。
- ⚫︎マイナ免許証との連携:現行のシステムでは、マイナンバーカードを更新した場合、運転免許の情報は自動的に引き継がれません。そのため、マイナ免許証を取得している方は、マイナンバーカード更新後に再度一体化の手続きをやり直す必要があります。このシステムの改善は本年秋に予定されています。マイナ免許証の更新に伴う免許情報の再記録は、運転免許試験場、運転免許更新センター、指定警察署で予約なしで行うことができます。
🏠オハナの縁側から、ひとこと
医療機関で、マイナンバーカードを保険証として利用する方も増えてきました。
けれど、いざ受診しようとしたときに「更新を忘れていた!」と気づき、慌ててしまうこともあるかもしれません。
マイナンバーカードは徐々に浸透してきていますが、「有効期限がある」ことを意外と知らない方も多いのではないでしょうか。
更新を忘れると不安が積み重なってしまいますが、あらかじめ知っておけば安心です。
「まだ大丈夫かな?」と一度確認してみること──それが、日々の暮らしを支える第一歩になるのかもしれません
「まだ大丈夫かな?」と一度確認してみることが、日々の暮らしを支える第一歩になるのじゃな。
出典:総務省・デジタル庁・厚労省・警視庁など公式情報に基づく内容を整理しています。
関連記事
👉 【そっとケアQ #1】介護保険サービスは本当に1割負担?2割・3割になる条件とは
👉 【そっとケアQ #2】介護保険は何歳から使える?40歳から利用できる条件と特定疾病一覧
👉 【そっとケアQ #3】介護が必要かも…最初に相談するのはどこ?
👉 【そっとケアQ #4】要介護認定のあとに最初に作るものは?